
企業の成長には、生産性の向上や従業員の満足度の向上が不可欠です。しかし、その費用が課題となることも…。そこで活用したいのが、厚生労働省の「業務改善助成金」です。
業務改善助成金は、営業所や工場など事業場ごとで最も低い賃金を引き上げたうえ、業務効率化を図った場合に受けられる助成金。2025年度も申請を受け付けていますが、上限額の変更など2024年度とは異なる点もあります。
この記事では、2025年度の業務改善助成金について、2024年度からの変更点や活用する際に知っておくべきポイントを交えて解説します。
目次
そもそも業務改善助成金とは

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
制度の目的やメリットを確認しておきましょう。
業務改善助成金の目的
業務改善助成金の目的は、日本の経済を活性化させるべく、中小企業の持続的な経営を後押しすることです。そのため、賃金の引き上げと生産性の向上を助成金の支給要件としています。
賃上げは従業員の満足度や生活の質を高め、離職防止につながるほか、優秀な人材の確保もしやすくなり、企業の活力も高めます。さらに業務改善で生産性が上がり、賃上げの原資が得られれば、持続的な成長サイクルが生まれます。
業務改善助成金の活用メリット
業務改善助成金の活用には、具体的に次のようなメリットがあります。
- 従業員のモチベーション向上
- 人材の定着
- 優秀な人材の確保
- 業務改善によるコスト削減
- 売上の増加
- 市場での競争力強化
賃上げによって従業員のモチベーションが上がり、離職せず定着してくれることが期待できます。優秀な人材の確保にも、賃金引き上げの実績は好材料です。
業務改善で効率化できれば、コストの削減もでき、売上は増加するでしょう。そうなれば市場での競争力も高まります。
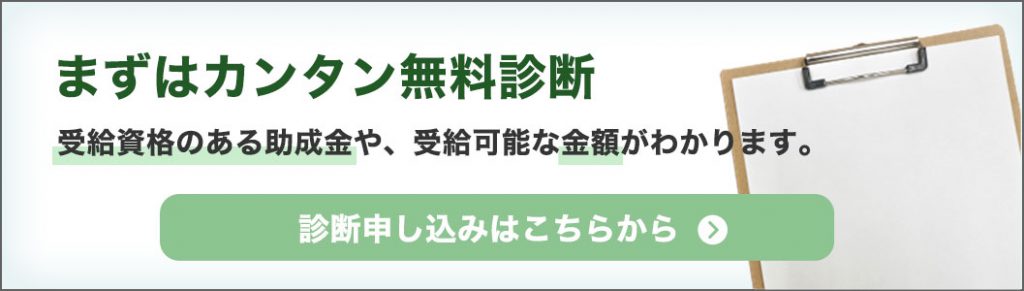
ココが変わった!2024年度からの主な変更点

2025年度の業務改善助成金は、2024年度(令和6年度)と比較して、制度の一部が改訂されています。今年度の主な変更点を見ていきましょう。
申請上限額の変更
これまでは「事業場単位」、つまり営業所や支店、工場など事業を行う場所ごとの助成上限が、年間600万円でした。
しかし2025年度は「事業主単位」での上限が年間600万円となっています。1つの企業が複数の拠点で賃上げなどを実施しても、会社全体で600万円までしか支給されません。
みなし大企業は対象外

この助成金は中小企業や小規模事業者を対象としていますが、2025年度は「みなし大企業」が支給の対象外となりました。
「みなし大企業」とは、企業規模は中小企業に該当するものの、実質的には大企業の支配下にある企業のことです。たとえば、親会社である大企業から多大な出資を受けている、大企業の役員が役員の過半数を占めている場合などが当てはまります。
必要雇用期間の延長
この助成金では、事業場内の最低賃金で働く人の給料を一定以上増やすことが必要で、雇用を継続している期間についても定められています。
この期間が、2024年度は「3カ月以上」だったのですが、2025年度は「6カ月以上」となりました。つまり、より長く雇用している従業員の賃上げが支援の対象となっています。
助成区分の変更と生産性要件の廃止
2024年度は、事業場内最低賃金の額に応じて3段階の助成区分が設けられていました。2025年度は1,000円を基準とした2段階の区分に変更されています。
また、生産性要件を満たした場合の助成率引き上げもなくなりました。
助成区分や金額、助成率についてはこの後の章で具体的に説明します。
事業完了期限は1月31日

生産性向上のために導入する機器等の納品や支払い完了日、もしくは賃金引き上げの就業規則を改定した日のいずれか遅い日が「事業完了期限」となります。
2024年度は、この期限が当初「交付決定の属する年度の1月31日」とされましたが、途中で2月28日まで延長されました。
しかし2025年度は、事業完了期限を2026年(令和8年)1月31日としています。やむを得ない事情と見なされれば3月31日まで延長できる可能性もありますが、早めの計画がおすすめです。
業務改善助成金の対象と申請期間

業務改善助成金を受けるには、複数の要件を満たす必要があります。1つでも満たさなければ対象外となるので注意が必要です。
対象事業者と申請の単位
支給対象となる事業者の要件は、主に次の3つです。
- 中小企業・小規模事業主であること
(みなし大企業を除く) - 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が50円以内であること
- 解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
申請にはまず、これらの要件を満たし、かつ事業場内最低賃金の30円以上の引き上げ計画と、設備投資等の計画を立てることが必要です。
申請は、会社(事業主)単位ではなく、工場や支店など「事業場」ごとに行います。
賃上げ要件達成のルール

受給には、事業場内の最低賃金を30円以上引き上げる必要があります。これは、事業場内の全員が新たな最低賃金以上となることも含みます。
後で具体的に紹介しますが、引き上げる賃金の額や賃金を引き上げる人数などによって、助成の上限額が違ってきます。
この「賃金を引き上げる人数」に含める労働者は、次のいずれかでなくてはなりません。
- 事業場内最低賃金の労働者
- 最低賃金の引き上げによって、賃金額が追い抜かれる労働者
たとえば、事業場内最低賃金が「1,000円」の事業場で「30円コース」を申請するとしましょう。
この事業場で、もともとの賃金が1,020円の人を1,040円にします。この場合、新たな最低賃金の1,030円以上とはなりますが、賃上げ幅は20円しかありません。そのため、対象人数に含めることはできません。
対象となる設備投資などの要件

助成金を受けるには、賃金の引き上げ要件を満たしたうえで、生産性向上につながる設備投資などを行う必要があります。その費用に一定の助成率をかけた金額が、助成金額となります。
対象となるのは、次のような設備の導入やコンサルティングです。
| 設備投資等 | 具体例 |
|---|---|
| 機器・設備の導入 | ・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮 ・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮 |
| 経営コンサルティング | ・国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フローの見直し |
| その他 | ・顧客管理情報のシステム化 ・店舗改装による配膳時間の短縮 ・タブレット型セルフオーダーシステムの導入による注文処理時間の短縮 |
ポイントは、生産性や労働能率のアップにつながる経費であることです。業種によって対象となる経費はさまざまなので、事前に社会保険労務士などに相談することをおすすめします。
申請期限と賃金引き上げの期間

業務改善助成金は、申請期間が第1期と第2期に分けられています。
第1期・第2期のそれぞれ、申請期間と賃金の引き上げ期間は次のとおり定められています。
| 期別 | 申請期間 | 賃金引き上げ期間 |
|---|---|---|
| 第1期 | 令和7年4月14日 ~6月13日 | 令和7年5月1日 ~6月30日 |
| 第2期 | 令和7年6月14日 ~地域別最低賃金改定日の前日 | 令和7年7月31日 ~地域別最低賃金改定日の前日 |
いずれも、事業完了期限は前述のとおり、令和8年1月31日です。
第3期以降の申請を受け付ける可能性もあり、その場合は厚生労働省のホームページにて告知されます。
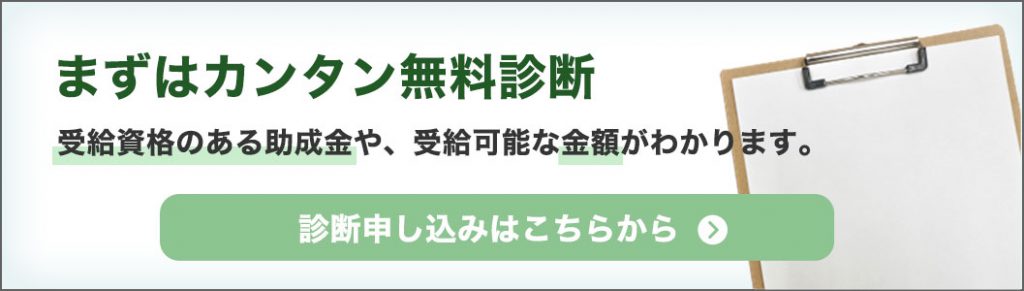
4つの助成コースと上限額、助成率

業務改善助成金の助成率や上限額は、引き上げる賃金の額と対象人数、事業場の規模(従業員人数)によって異なります。
助成コースと上限額
最低賃金の引き上げ額によって、次の4つのコース区分があります。
| コース区分 | 事業場内最低賃金の引き上げ幅 |
|---|---|
| 30円コース | 30円以上の引き上げ |
| 45円コース | 45円以上の引き上げ |
| 60円コース | 60円以上の引き上げ |
| 90円コース | 90円以上の引き上げ |
引き上げる人数と、事業場の従業員数によって、助成の上限は次のように異なります。
| コース区分 | 引き上げる労働者数 | 助成の上限額 | |
|---|---|---|---|
| 右記以外 | 事業場規模30人未満 | ||
| 30円コース | 1人 | 30万円 | 60万円 |
| 2~3人 | 50万円 | 90万円 | |
| 4~6人 | 70万円 | 100万円 | |
| 7人以上 | 100万円 | 120万円 | |
| 10人以上※ | 120万円 | 130万円 | |
| 45円コース | 1人 | 45万円 | 80万円 |
| 2~3人 | 70万円 | 110万円 | |
| 4~6人 | 100万円 | 140万円 | |
| 7人以上 | 150万円 | 160万円 | |
| 10人以上※ | 180万円 | 180万円 | |
| 60円コース | 1人 | 60万円 | 110万円 |
| 2~3人 | 90万円 | 160万円 | |
| 4~6人 | 150万円 | 190万円 | |
| 7人以上 | 230万円 | 230万円 | |
| 10人以上※ | 300万円 | 300万円 | |
| 90円コース | 1人 | 90万円 | 170万円 |
| 2~3人 | 150万円 | 240万円 | |
| 4~6人 | 270万円 | 290万円 | |
| 7人以上 | 450万円 | 450万円 | |
| 10人以上※ | 600万円 | 600万円 | |
※印は、「特例事業者」が「10人以上」に対して引き上げを行った場合のみ、適用される上限額です。特例事業者については後の章で紹介します。
引き上げる額が高いほど、引き上げる人数が多いほど、上限額は高く設定されています。事業場規模は30人未満と小規模の方が、高い上限額となります。
助成率と助成額の計算方法

設備投資などに要した費用に、次の助成率をかけた額が支給金額となります。助成率は申請時の事業場内最低賃金の額が1,000円未満か以上かで異なります。
| 事業場内最低賃金 | 助成率 |
|---|---|
| 1,000円未満 | 5分の4 |
| 1,000円以上 | 4分の3 |
助成額は、「設備投資等の費用×助成率」の額または上記の上限額の「いずれか低い方」です。
例を挙げて見てみましょう。
- 事業場内最低賃金:980円(1,000円未満)
- 8人の従業員を980円から1,070円に引き上げ
(90円コース) - 設備投資等にかかった経費は600万円
この例の場合、「設備投資等の費用×助成率」は「600万円×5分の4」で「480万円」。助成上限額は、上の表から「450万円」となります。
支給額は、安い方の450万円です。
特例事業者への優遇措置

助成コースと上限額の章でもお伝えしたように、業務改善助成金には、「特例事業者」に対する特例措置が設けられています。
特例事業者とは
次の2つの要件のいずれかに当てはまる場合、「特例事業者」と見なされます。
| ①賃金要件 | 事業場内最低賃金が1,000円未満である |
|---|---|
| ②物価高騰等要件 | ・申請前3カ月間のうち1カ月の利益率が前年同月に比べて3%以上低下した ・前項の低下要因が、原材料費の高騰など、社会的・経済的環境変化などの外的要因である |
特例事業者が10人以上の賃金引き上げを行った場合、助成の上限額が高くなります。
助成額の特例
助成上限額の拡充について、あらためて特例事業者への拡充部分をまとめてみましょう。
| コース区分 | 10人以上引き上げた場合の上限額 | |
|---|---|---|
| 右記以外 | 従業員30人未満 | |
| 30円コース | 120万円 | 130万円 |
| 45円コース | 180万円 | 180万円 |
| 60円コース | 300万円 | 300万円 |
| 90円コース | 600万円 | 600万円 |
特例事業者に当てはまる場合、90円コースで10人以上の賃金を引き上げると、上限額がこの助成金最大の600万円となります。
助成対象経費の特例

特例事業者のうち、②の物価高騰等要件を満たす場合には、助成対象経費についても拡充されます。
具体的には、通常は対象とならない次のような経費も、助成対象となる可能性があります。
【特例事業者のみ認められる経費】
- 定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車、貨物自動車
- パソコン、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規購入
いずれも、生産性向上につながる設備投資であること、という条件は変わりません。単に「足りないから」などの理由で購入したのでは対象外です。
業務改善助成金の申請から受給までの流れ

助成金の支給には、次のような段階を踏む必要があります。計画的に進めていきましょう。
- 交付申請書・事業実施計画書等を管轄の労働局に提出
- 労働局による審査→交付決定
- 事業(賃金の引き上げ、設備導入・支払い)を実施
- 事業実績書や支給申請書などを労働局に提出
- 労働局による審査→交付額の確定
- 助成金の振り込み
申請から受給まで、数カ月から半年程度の時間がかかります。とくに年度末にかけては申請が集中し、審査に時間がかかる可能性も。
予算次第では申請期間内でも募集が締め切られるため、早めの計画をおすすめします。
業務改善助成金を活用する際の重要ポイント

業務改善助成金の申請や活用にあたっては、押さえておくべき重要事項がいくつかあります。助成金の確実な受給のため、確認しておきましょう。
交付決定前の設備導入は対象外
労働局による交付決定が下りる前に設備導入(納品)や支払いなどを行うと、申請後であっても助成の対象から外れてしまいます。交付決定を待って導入しましょう。
発注だけなら、交付決定より前に行っても問題ありません。
賃金引き上げの日付に注意
地域別最低賃金の改定に伴って事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げしないと、助成の対象になりません。発行年月日は、地域により異なることにも注意が必要です。
たとえば地域別最低賃金の発効日が10月1日なら、9月30日までに引き上げを行う必要があります。
就業規則への記載が必須
賃金の引き上げについては、引き上げを実行するだけは不十分です。就業規則や労働協約に、引き上げ後の最低賃金を記載することが必要です。
複数回の賃金引き上げは対象外
賃金の引き上げを複数に分けてしまうと、助成の対象となりません。
たとえば、10円の引き上げ後に20円の引き上げを行い、計30円を引き上げた、と言っても認めてはもらえません。
計画的に一度で行いましょう。
申請期間中に募集終了となることも
助成金の支給は、厚生労働省の予算によって実施されています。そのため、多くの募集があるなどして予算がなくなれば、申請期間中であっても早期に終了されます。
出遅れないよう、早めのスタートをおすすめします。
過去に受給済でも申請可能
助成金の中には、過去に受給した事業主を対象外とするものもあります。
しかし業務改善助成金は、過去に受給している場合でも助成対象となり得ます。積極的に検討してみてください。
最新の要綱・要領を要確認
助成金のルールは、毎年いくつかの変更が行われていますし、年度の途中でも変更されることがあります。申請するなら、常に最新情報をチェックし、失敗のないようにしましょう。
社会保険労務士などの専門家にサポートしてもらえば、その点も安心です。
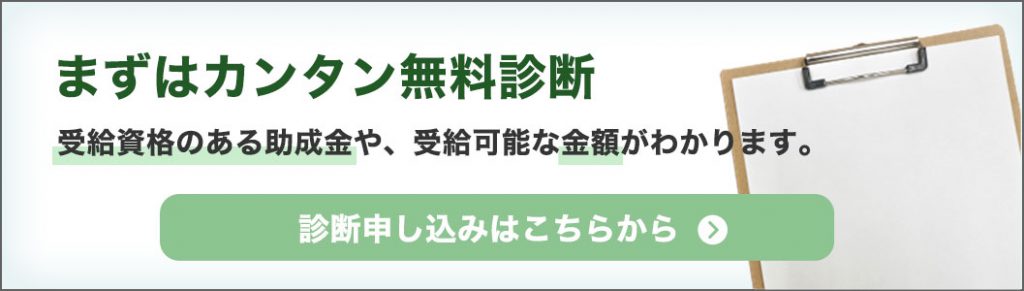
2025年度も業務改善助成金を活用しよう

2025年度の業務改善助成金は、2024年度に比べ、事業主単位での申請上限額が設定されたり、助成区分が見直されたりといった変更が行われています。
賃金の引き上げは、従業員のためにとどまらず企業全体がパワーアップするための重要な投資です。この助成金を賢く利用して、会社の成長と労働環境の改善を実現させましょう。
具体的な申請手続きや準備については、助成金制度に詳しい専門家に相談するのがおすすめです。当サイトを運営する「社会保険労務士事務所Bricks&UK」には、数多くの企業の助成金受給をサポートした実績があります。
ぜひお気軽にご相談ください。
就業規則を無料で診断します
労働基準法等の法律は頻繁に改正が行われており、その都度就業規則を見直し、必要に応じて変更が必要となります。就業規則は、単に助成金の受給のためではなく、思わぬ人事労務トラブルを引き起こさないようにするためにも大変重要となります。
こんな方は、まずは就業規則診断をすることをおすすめします
- 就業規則を作成してから数年たっている
- 人事労務トラブルのリスクを抱えている箇所を知りたい
- ダウンロードしたテンプレートをそのまま会社の就業規則にしている
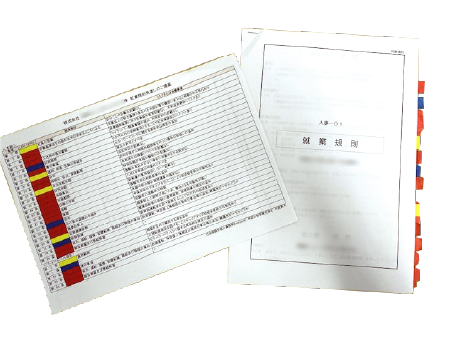













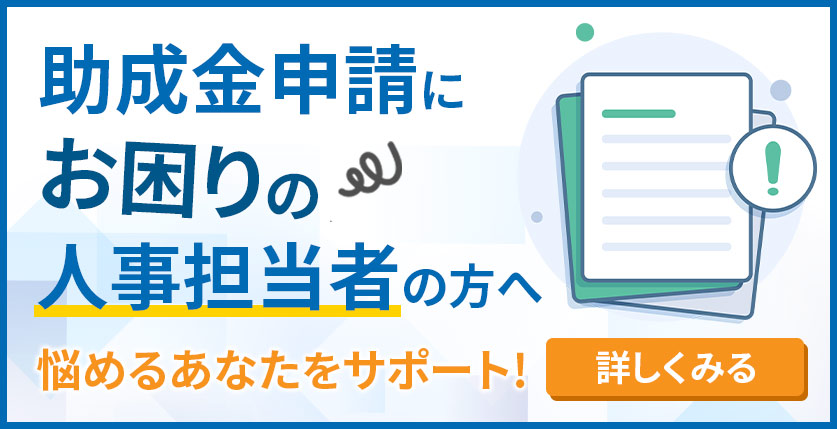
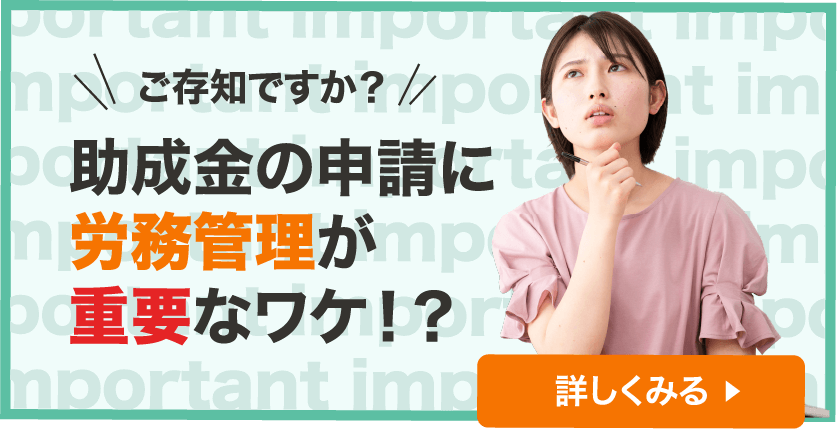
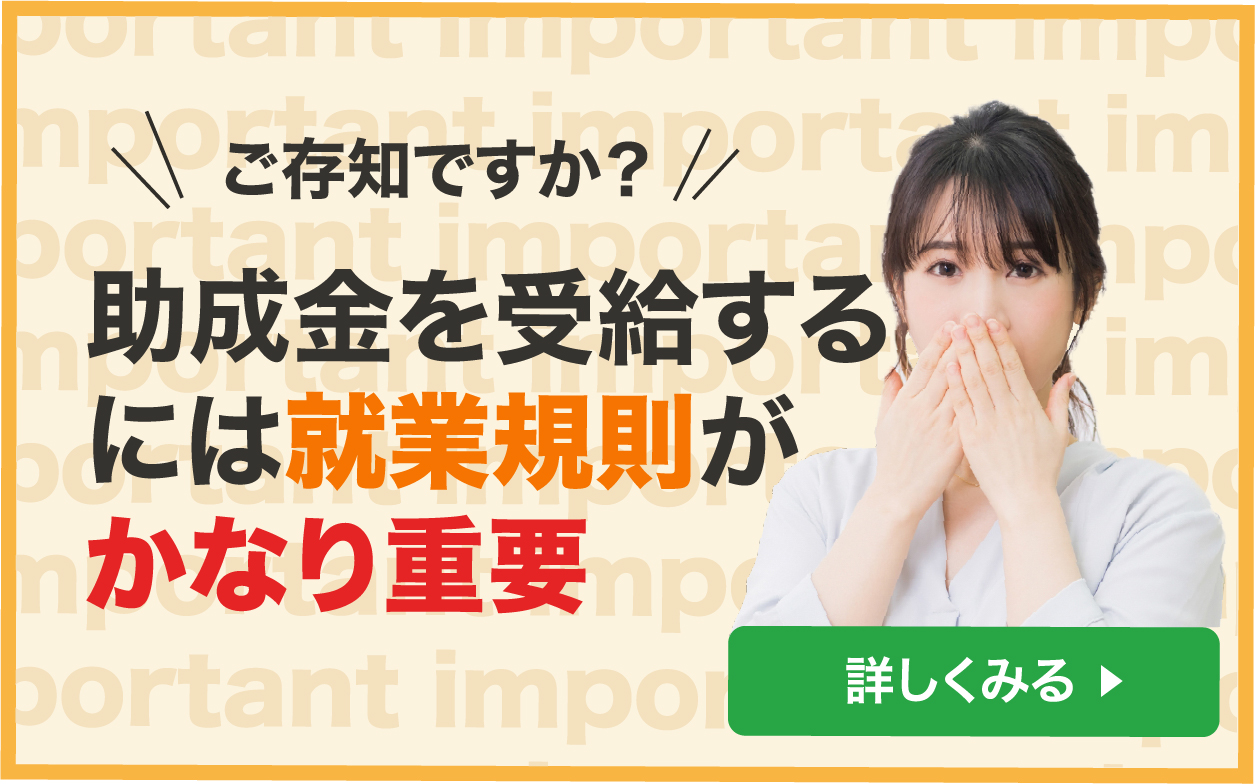

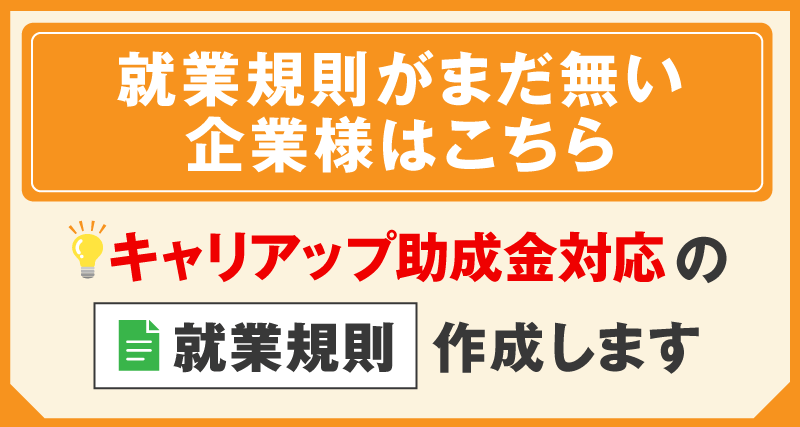
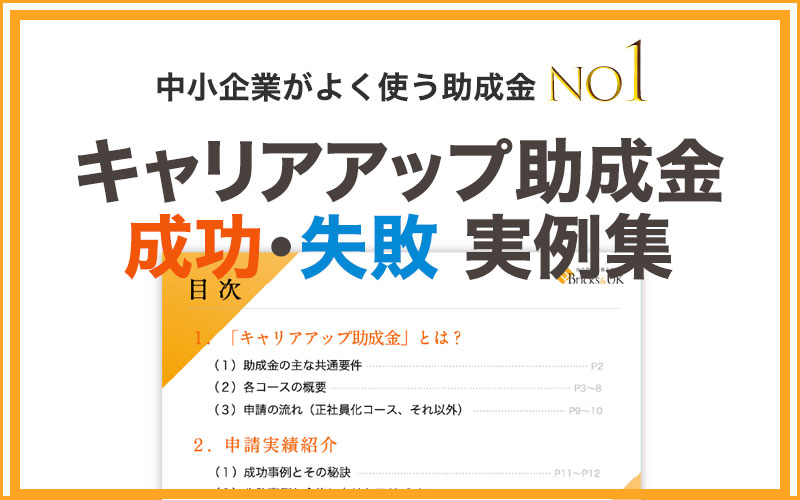


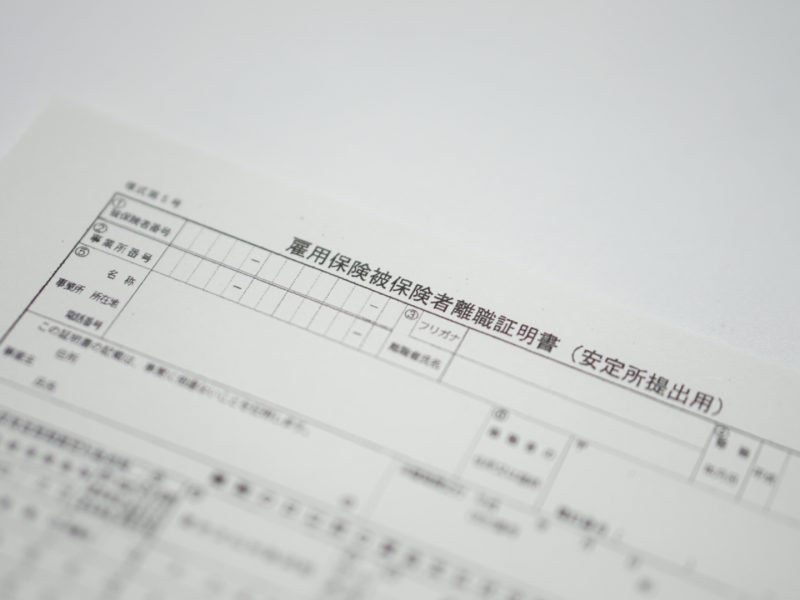

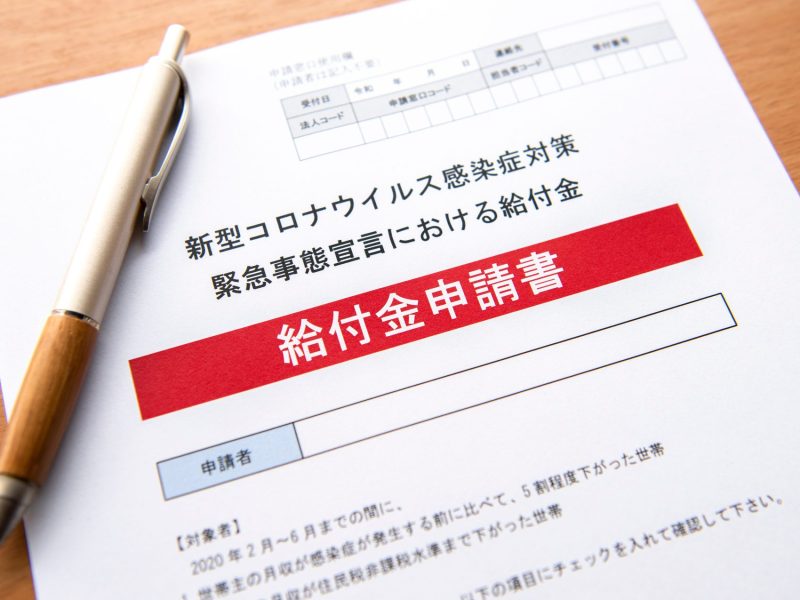
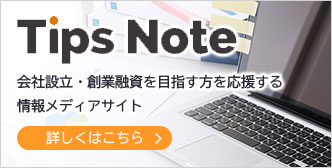


監修者からのコメント 業務改善助成金は、乗用車やパソコンの購入にも活用できるという特性から、令和6年度より急速に注目を集めている人気の助成金です。
本助成金を活用するには、事業所内の最低賃金を引き上げる必要があるため、固定費の増加というデメリットも伴いますが、「働き方改革推進支援助成金」などの類似制度と比べて、求められる取り組み(最低賃金の引き上げ)が比較的簡素であり、助成金の上限額も引き上げやすい点が特長です。
例年、9月以降は地域別最低賃金の引き上げを契機として申請が集中し、申請件数の急増により労働局での審査が長期化する傾向があります。
ご活用を検討されている場合は、お早めにご契約中の社会保険労務士へご相談いただくことをおすすめします。