
育児・介護休暇や短時間勤務など、家庭の事情に応じた柔軟な働き方ができる環境づくり。この取り組みで活用できるのが、両立支援等助成金です。
両立支援等助成金は2025年度も継続されていますが、育児・介護休業法の改正に伴い、各コースそれぞれで要件などが変更されています。申請するなら、最新情報の把握も必須です。
この記事では、両立支援等助成金の各コースについて、その主な要件と支給額、2025年度の変更点を解説します。
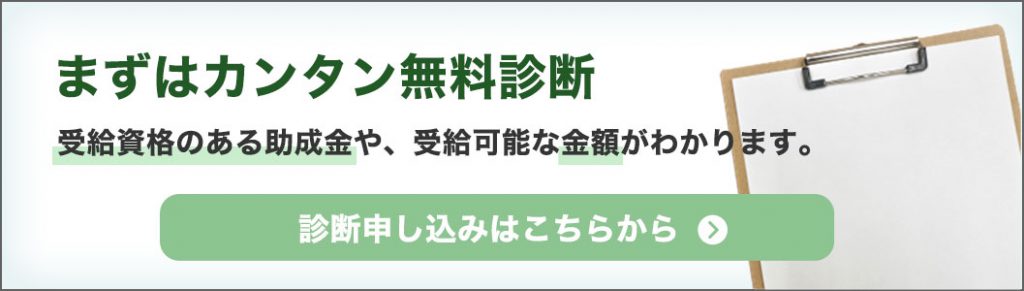
目次
両立支援等助成金とは

両立支援等助成金は、従業員が育児や介護など家庭の事情にかかわらず長く安心して働ける環境づくりを行った場合に受けられる助成金です。中小企業の事業主を対象としています。
環境づくりとは、たとえば男性が育休を取りやすい業務体制を整備する、柔軟な働き方ができる時差出勤などの制度を設けるといった取り組みを指します。
対象となる取り組みに応じて、次の6つのコースが設けられています。
- 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
- 介護離職防止支援コース
- 育児休業等支援コース
- 育休中等業務代替支援コース
- 柔軟な働き方選択制度等支援コース
- 不妊治療および女性の健康課題対応両立支援コース
各コースの要件や2025年の変更点について、順に見ていきましょう。
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

出生時両立支援コースとは、育休を取りやすい雇用環境を整備し、男性従業員が実際に育休を取得した場合に受けられる助成金です。
助成には、男性の育休取得による「第1種」と、男性育休取得率の上昇による「第2種」の2種類があります。
助成の種別と主な要件
第1種と第2種、それぞれ主に次のような要件があります。
第1種:男性従業員の育休取得
- 1)育児・介護休業法等による雇用環境整備の措置を2つ以上行う
- 2)育休取得者の業務を代替する従業員の業務見直しについて規定を作り、業務体制を整備
- 3)男性従業員が、一定日数以上の育休を子の出生後8週間以内に開始する
「1」の「育児・介護休業法等による雇用環境整備の措置」とは、育休や産後パパ育休に関する次の4つをいいます。
- ①研修の実施
- ②相談体制の整備
- ③取得事例の収集と従業員への提供
- ④制度や取得促進に関する方針の周知
すでに、これらのうちいずれかの措置を講じることは義務化されています。しかし、このコースの受給には1つでなく複数の措置が必須となっています。4つすべてを行うと、支給額の加算も受けられます。
「3」の「一定日数」とは、育休取得1人目は5日以上、2人目は10日以上、3人目は14日以上を指します。
第2種:男性の育休取得率の上昇等
第2種では、第1種と同じく雇用環境整備の措置を2つ以上実施すること、業務代替者の業務見直しに関して規定を作り、体制を整備することのほか、次のいずれかを達成する必要があります。
- 申請年度の前年度の男性育休取得率が前々年より30%以上アップかつ取得率が50%以上
- 申請年度の前々年度で子が生まれた男性従業員が5人未満かつ申請前年度と前々年度の育休取得率が連続70%以上
支給額
出生時両立支援コースの支給額は、種類ごとに次のようになっています。
| 種別 | 要件 | 支給額 |
|---|---|---|
| 第1種 | 対象労働者が子の出生後8週以内に育休を開始 | 1人目:20万円 2・3人目:10万円 |
| 第2種 | 育休取得率30%以上アップ&50%以上を達成 等 | 60万円 |
第2種の申請は1回限りです。第2種の申請後に第1種を申請することはできません。
加算措置
要件を満たせば、次のような加算も受けられます。
| 加算の要件 | 加算額 |
|---|---|
| 第1種:1人目の申請時、雇用環境整備措置を4つ以上実施 | 10万円 |
| 第2種:申請時にプラチナくるみん認定事業主である | 15万円 |
| 共通:育児休業等に関する情報公表加算 | 2万円 |
第1種の1人目については、雇用環境整備措置を4つ以上行うことで最大30万円が支給されます。育児休業等に関する情報公開を行うと、1~3人目のいずれか1回に限り、2万円の加算が受けられます。
育児休業等に関する情報公表とは、自社の男性従業員の育休取得状況などについて、厚労省が運営する「両立支援のひろば」「一般事業主行動計画公表サイト」で公表することを指します。
2025年度の変更点
出生時両立支援コースは、毎年のように要件が変更されています。2025年度の変更点は、次のとおりです。
| 従前 | 2025年より |
|---|---|
| 第2種の申請には第1種の受給が必須 | 第1種を受給していなくても第2種の申請が可能 |
| 第1種申請時で子が生まれた男性従業員が5人未満だった場合、育休取得率70%以上、かつ次の事業年度から3年間のうち2年連続で取得率70%以上が必須 | 支給年度の前々年の時点で子が生まれた男性従業員が5人未満だった場合、直前2年の育休取得率が連続70%以上であれば対象 |
| 第1種申請の対象者以外で、1日以上の育休を取得した男性労働者が2名以上必要 | 左記については不問 |
いずれも第2種についての要件が緩和され、育休取得率アップの取り組みをよりバックアップする形となっています。
介護離職防止支援コース

介護離職防止支援コースは、従業員が家族の介護のために離職を余儀なくされることを防ごうと取り組む事業主を対象とした助成金です。
介護休業の取得促進や両立支援制度の導入、業務を代替する従業員への手当支給などの取り組みで、助成が受けられます。
助成の種別と主な要件
介護離職防止支援コースでは、取り組みの種類ごとに3種類の助成があります。対象と要件は次のとおりです。
1)介護休業
対象従業員に介護休業を取得させた場合の助成です。
- 介護休業の取得や職場復帰支援の方針を社内周知
- 従業員と面談、介護支援プランを作成・実施
- 対象者が連続5日以上の介護休業を取得、復帰後も支給申請日まで継続雇用
2)介護両立支援制度
勤務時間に融通を利かせるなどした場合の助成です。
- 介護休業の取得や職場復帰支援の方針を社内周知
- 従業員と面談、介護支援プランを作成・実施
- 介護両立支援制度のいずれかを対象者が一定基準以上利用、支給申請日まで継続雇用
ここでいう「介護両立支援制度」とは、次の制度を指します。
・所定外労働の制限制度 ・時差出勤制度 ・深夜業の制限制度 ・短時間勤務制度 ・在宅勤務制度 ・フレックスタイム制度 ・法を上回る介護休暇制度 ・介護サービス費用補助制度
3)業務代替支援
休業や時短勤務などにより必要となる業務代替に関する助成です。
業務代替支援は、さらに次の2つに分けられています。
| 対象の取り組み | 要件 |
|---|---|
| 新規雇用 | ・対象者が介護休業を5日以上連続で取得 ・代替要員を新規雇用か派遣で確保 |
| 手当支給等 | ・業務代替者への手当制度等を就業規則等に規定 ・対象者が介護休業を連続5日以上取得または短時間勤務制度を合計15日以上利用、代替者に業務手当等を支給 |
「手当支給等」では、業務を代替する従業員に手当を支給するだけでなく、手当の支給を就業規則や労使協定に規定しておく必要があります。
支給額
取り組みの種類や内容によって、支給額は次のように決められています。
いずれも、休業取得や制度の利用者1人あたりの金額です。
| 種別 | 要件 | 支給額 | |
|---|---|---|---|
| 1)介護休業 | 介護休業の取得&職場復帰 | 40万円 | |
| 2)介護両立支援制度 | A:制度1つ導入&利用 | 20万円 (合計60日以上の制度利用:30万円) | |
| B:制度2つ以上導入&1つ以上利用 | 25万円 (合計60日以上の制度利用:40万円) | ||
| 3) 業務代替支援 | 新規雇用 | 代替要員の新規雇用(派遣を含む) | 20万円 (連続15日以上の休業:30万円) |
| 手当支給等 | A:介護休業取得(連続5日以上)の代替者に手当を支給 | 5万円 (連続15日以上の休業:10万円) | |
| B:短時間勤務(合計15日以上)の代替者に手当を支給 | 3万円 | ||
2の介護両立支援制度と3の業務代替支援では、対象者の制度利用日数あるいは介護休業の取得日数によって、表のとおり支給額がアップします(短時間勤務の手当支給等を除く)。
また、介護離職防止支援コースでは、1~3のいずれかの対象となる場合に仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備①~④のすべてを行った場合、「環境整備加算」が受けられます。
- ①研修の実施
- ②相談体制の整備
- ③取得事例の収集と従業員への提供
- ④制度や取得促進に関する方針の周知
| 環境整備加算 | 10万円 |
|---|
2025年度の変更点
2025年度、介護離職防止支援コースでは、次の点が変更となっています。
1)介護休業の支給額変更
従前は、休業取得時に30万円、職場復帰時に30万円の支給が受けられました。しかし2025年度は、休業の取得と職場復帰がセットで40万円の支給となっています。
2)介護両立支援制度の要件緩和
従前は、両立支援制度を20日以上利用しないと支給対象となりませんでした。また、支給額は一律30万円でした。
2025年度は、導入する制度の数によって支給額が分かれているものの、日数の指定はありません。支給額は20万円~25万円と少し減ったものの、60日以上の利用で増額も受けられます。
3)業務代替支援の拡充
2024年は加算措置とされていた、業務代替者の新規雇用と休業中の手当支給が基本の制度に含まれました。
また、介護休業中だけでなく短時間勤務時の業務代替に対する手当も、対象者が合計15日以上の短時間勤務制度を利用すれば、助成対象となります。
4)環境整備加算の要件変更
これまで、「介護休業(取得時)」または「介護両立支援制度」への加算措置として、15万円の「個別周知・環境整備加算」がありました。
これには、対象者に自社制度や休業取得時の待遇の説明を行うこと、社内で雇用環境整備の措置を2つ以上行うことが要件でした。
2025年度は、雇用環境整備措置を4つすべて行うことを要件として、10万円の加算が受けられます。実質的には、要件が厳しくなり、加算額は減ったと言えます。
育児休業等支援コース

育児休業等支援コースは、育休取得や職場復帰がスムーズにできる職場環境を整え、従業員が実際に育休を取得した場合に受けられる助成金です。
助成の種別と主な要件
育児休業等支援コースでは、育休を取得させた時、職場に復帰をさせた時のそれぞれで支給が受けられます。
主な要件を見ていきましょう。
1)育休取得時
- 育休の取得・職場復帰支援に関する方針の周知
- 従業員との面談、育休復帰支援プランの作成・実施
- 対象者の育休(または産休)の開始前日までに引き継ぎを実施、対象者が連続3カ月以上の育休(産休を含む)を取得
産休から引き続き育休に入る場合は、引き継ぎは産休開始日の前日までに行い、産休を含めて3カ月以上の休業が要件となります。
2)職場復帰時
職場復帰による支給は、上記1の「育休取得時」と同じ従業員の復帰時に限られます。
- 対象者の育休中に職務や業務の情報・資料の提供を実施
- 育休終了前に上司か人事労務担当者による面談の実施、結果を記録
- 原則として原職等に復帰させ、支給申請日までの間6カ月以上継続雇用
本人の希望により原職以外の職で復帰することになった場合、面談記録で希望があった旨を確認できれば対象となり得ます。
しかし、希望であっても無期雇用から有期雇用に契約変更した場合は対象外となります。
また、たとえば時短勤務を希望したからといって本人が望まない雇用形態・給与形態への変更を強要するなどの不利益な取り扱いをした場合も、支給対象から外れます。
支給額
育児休業等支援コースの支給額は次のとおりです。
| 助成種別 | 支給額 |
|---|---|
| 育休取得時 | 30万円 |
| 職場復帰時 | 30万円 |
2025年度の変更点
育児休業等支援コースについては、2025年もコース特有の変更はありません。
育休中等業務代替支援コース

育休中等代替支援コースは、育休や短時間勤務の制度を使う当の従業員ではなく、その業務を代わりに行う従業員に対し、手当を支給した場合、もしくは新規雇用や派遣で代替要員を確保した場合に支給が受けられる助成金です。
助成の種別と主な要件
育休に対する手当支給と短時間勤務に対する手当支給、代替要員の新規雇用、それぞれで要件が次のように異なります。
1)手当支給等(育児休業)
- 代替業務の見直し・効率化への取り組みの実施
- 業務代替者への手当制度等を就業規則等に規定
- 対象者が7日以上の育休を取得、復帰後も支給申請日まで継続雇用
- 業務代替者への手当支給等
業務代替者への手当支給については、支給した手当の金額によって助成金の支給額 が異なります。
2)手当支給等(短時間勤務)
- 代替業務の見直し・効率化への取り組みの実施
- 業務代替者への手当制度等を就業規則等に規定
- 対象者が短時間勤務を1カ月以上利用、支給申請日まで継続雇用
- 業務代替者への手当支給等
業務代替者への手当支給については、支給した手当の金額によって助成金の支給額が変わります。
3)新規雇用(育児休業)
- 育休取得者の代替要員を新規雇用または派遣の受け入れで確保
- 対象者が7日以上の育休を取得、復帰後も支給申請日まで継続雇用
- 代替要員が育休中の業務を代替
業務を代替した期間によって、支給額が変わります。
支給額
支給額は次のとおりです。
| 種別 | 要件 | 支給額 |
|---|---|---|
| 1)手当支給等 (育児休業) | 育休時の業務代替者に手当を支給 | 最大140万円 (A+B) A:業務体制整備経費…最大20万円 B:業務代替手当…最大120万円 (手当支給総額の4分の3) ※うち最大30万円の先行支給あり |
| 2)手当支給等 (短時間勤務) | 短時間勤務の業務代替者に手当を支給 | 最大128万円 (A+B) A:業務体制整備費…最大20万円 B:業務代替手当…最大108万円 (手当支給総額の4分の3) ※うち最大23万円の先行支給あり |
| 3)新規雇用 (育児休業) | 育休取得の業務代替要員を新規雇用か派遣で受け入れ | 最大67.5万円 (代替期間に応じた額) ・最短(7日以上14日未満):9万円 ・最長(6カ月以上):67.5万円 |
1と2の業務体制整備経費については、労務コンサルを社会保険労務士など外部の専門業者に委託した場合に、支給が最大の20万円になります。
育休・短時間勤務の制度利用者が有期雇用契約だった場合には、10万円の加算が受けられます。ただし、業務代替期間が1カ月以上ある場合に限ります。
2025年度の変更点
2025年度は、支給額が増額されています。また、手当支給等の助成についてのみ、対象となる事業主の「中小企業」の範囲が拡充されました。
他のコースでは、常時雇用する労働者数について、たとえば飲食業を含む小売業は50人以下、卸売業については100人以下など、中小企業法が定める区分に沿った要件となっています。
しかし、育休中等業務代替支援コースの「手当支給等」での助成は、「業種を問わず一律300人以下の事業主が対象」となり、門戸が広げられた形です。
柔軟な働き方選択制度等支援コース

柔軟な働き方選択制度等支援コースでは、次に挙げる5つの制度のうち2つ以上を導入した上、従業員が実際に利用した場合に助成が受けられます。
- フレックスタイム制度/時差出勤制度
- テレワーク等
- 短時間勤務制度
- 保育サービスの手配、費用補助制度
- 子の養育を容易にするための休暇制度/法を上回る子の看護等休暇制度
主な要件
支給の主な要件は、次のようなものです。
- 柔軟な働き方選択制度等を2つ以上導入
- 導入した制度の利用に関する方針の社内周知
- 従業員との面談を実施、プランを作成・実施
- 制度の利用開始から6カ月間に、対象者が制度を一定基準以上利用
制度の導入は2つ以上が必須ですが、利用は1つ以上でOKです。
「一定基準」は、たとえばフレックスタイム制度や時差出勤制度、育児のためのテレワークの場合、合計20日以上の利用が条件などと決められています。2024年からの変更はありません。
支給額
支給額は、導入する制度の数によって次のように異なります。
| 支給要件 | 支給額 |
|---|---|
| 2つ以上の制度を導入、 対象者が制度を利用 | 20万円 |
| 3つ以上の制度を導入、 対象者が制度を利用 | 25万円 |
2025年度の変更点
このコースについては、2025年4月の時点では2024年度からの変更はありません。しかし、育児・介護休業法の改正により、2025年10月1日から柔軟な働き方を実現させるための措置等を講じることが義務化されます。
それにより、支給の要件である制度導入の基準も引き上げとなる可能性が高いと考えられます。
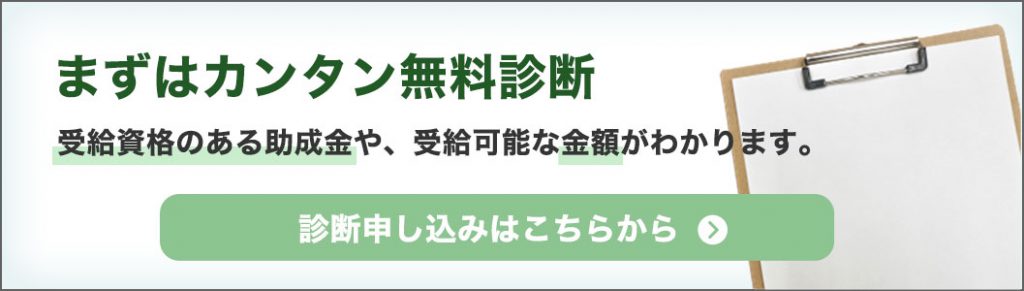
不妊治療および女性の健康課題対応両立支援コース

このコースでは、不妊治療や月経(PMS=月経前症候群を含む)や更年期といった女性の健康問題と仕事の両立のため、休暇などの制度を導入し、従業員に利用させた場合に受けられる助成金です。
主な要件
支給の主な要件は次の項目です。
- 次のA~Cについて、それぞれの両立支援制度、制度利用の手続きや賃金の取り扱いを就業規則等に規定
- A)不妊治療のための制度
- B)月経に起因する症状のための制度
- C)更年期に起因する症状のための制度
- 従業員からの相談に対応する「両立支援担当者」を選任
- 対象者がA~Cそれぞれの両立支援制度を合計5日(5回)利用
対象者は、利用の開始日から支給申請の日まで雇用保険の被保険者として継続雇用されていなくてはなりません。
両立支援制度とは、次のようなものを指します。
・休暇制度 ・所定外労働制限制度 ・時差出勤制度
・短時間勤務制度 ・フレックスタイム制度 ・在宅勤務等
支給額
不妊治療および女性の健康課題対応両立支援コースの支給額は次のとおりです。
| 支給要件 | 支給額 |
|---|---|
| A)不妊治療のための両立支援制度を5日(回)利用 | 30万円 |
| B)月経による症状への対応のための支援制度を5日(回)利用 | 30万円 |
| C)更年期による症状への対応のための支援制度を5日(回)利用 | 30万円 |
2025年度の変更点
このコースは、2024年までは「不妊治療両立支援コース」であり、不妊治療と仕事との両立支援制度のみを対象とした制度でした。
2025年度から、不妊治療だけでなく、月経やPMS、更年期障害と仕事との両立支援に対しても助成の対象となっています。
また、不妊治療のための休暇を取得後、連続20日以上の不妊治療休暇を取った場合に加算がありましたが、この加算は廃止されています。
2025年の両立支援等助成金の申請もBricks&UKにおまかせ

労働者人口が減る一方の今、従業員の誰もが仕事と家庭とのバランスを取り、長く活躍してくれると会社としても助かりますよね。
両立支援等助成金は、整備が不可欠な両立支援制度の創設や活用で助成金を受けられるため、活用しない手はありません。
助成金の申請には、最新情報や要件の把握が不可欠です。当サイトを運営する社会保険労務士事務所Bricks&UKでは、助成金に精通した社労士が申請をサポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。












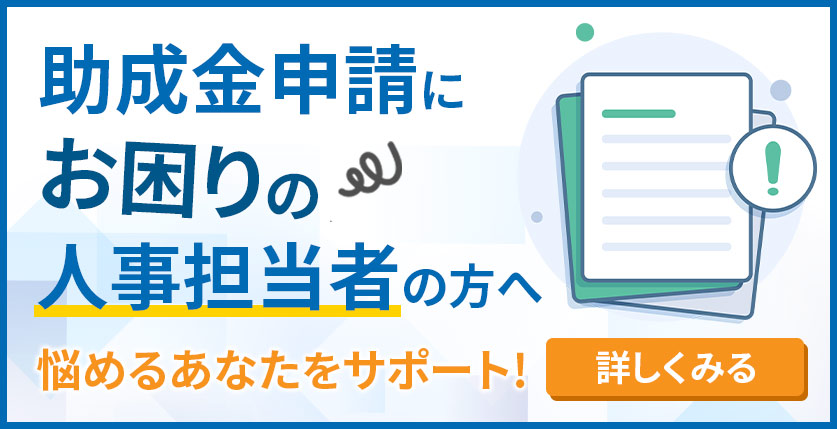
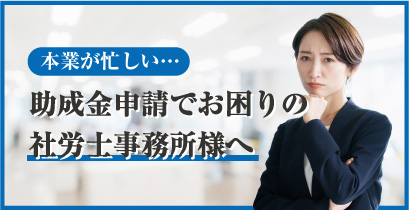
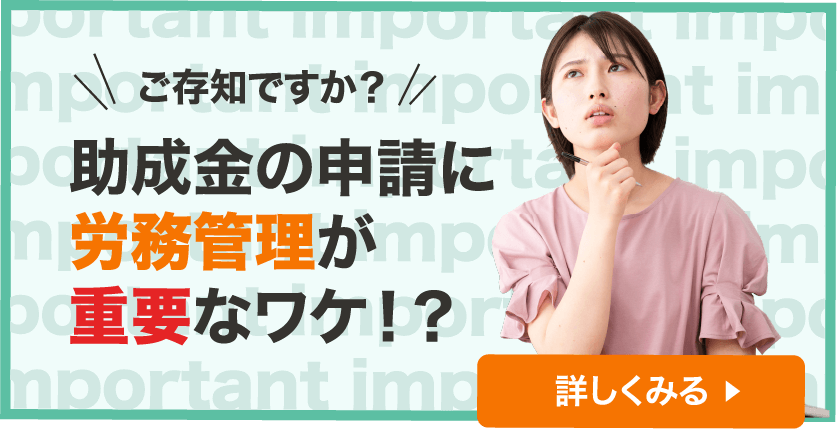
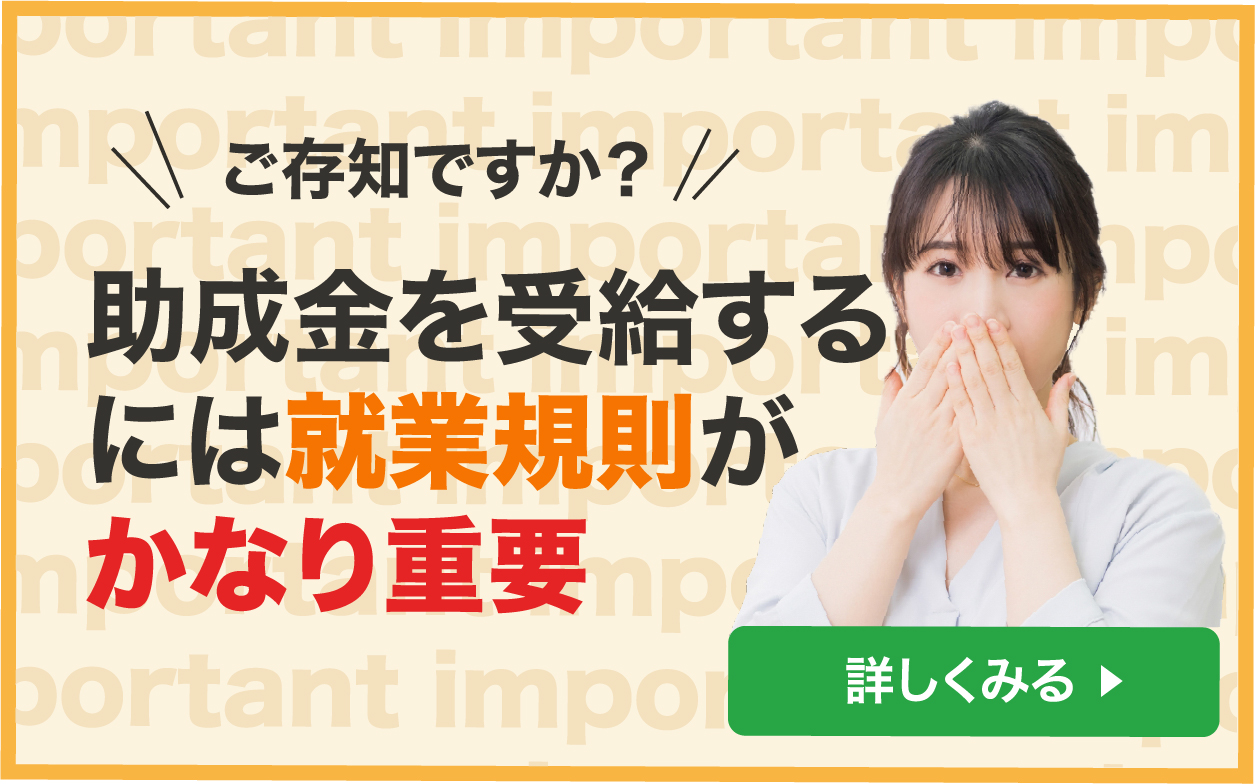

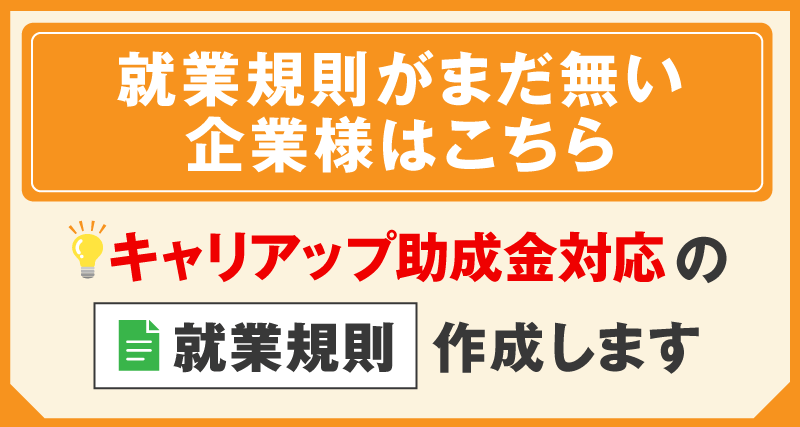
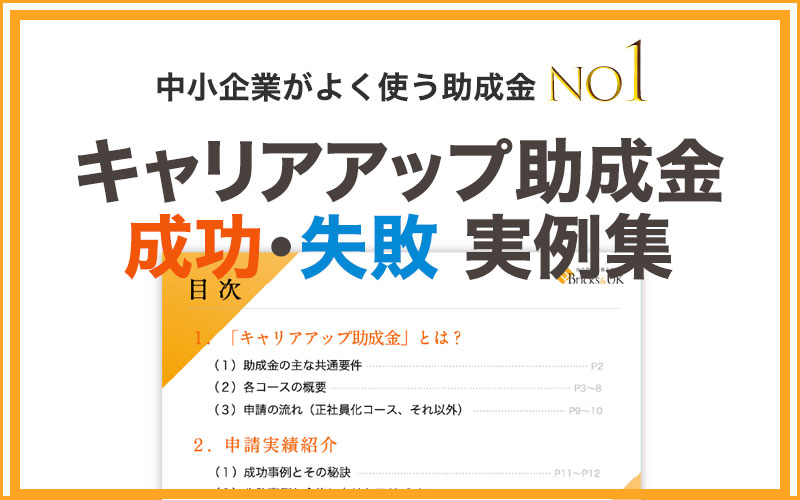

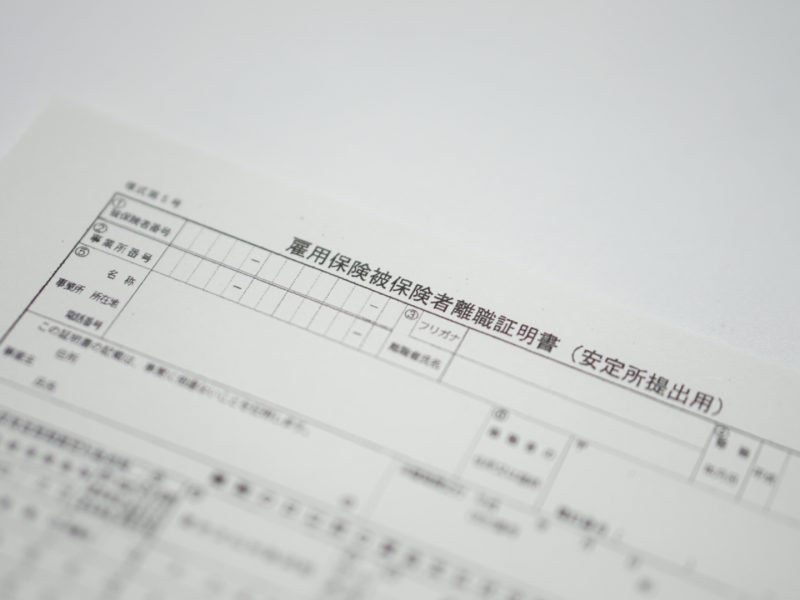

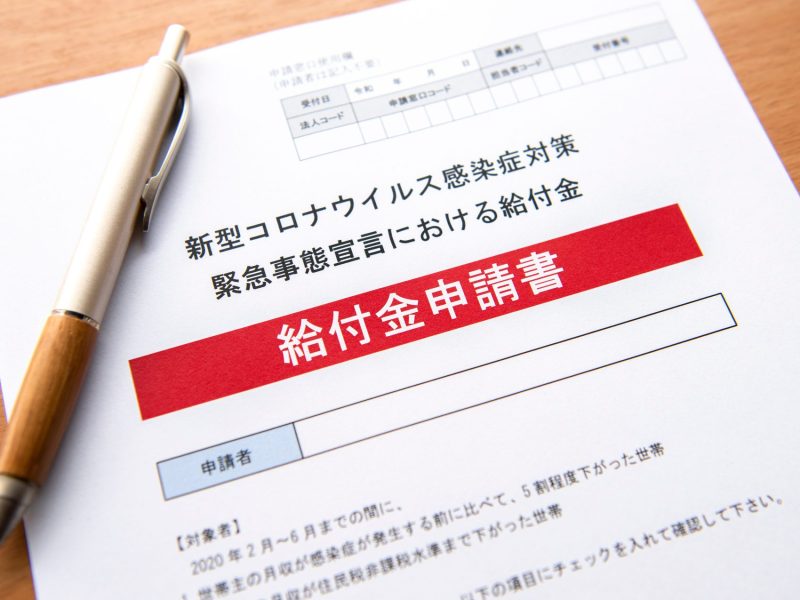
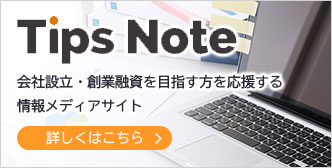


監修者からのコメント 近年、男性の育休取得が急増加する一方で、女性の育休取得率が若干下がり続けています。
世間一般の風潮として、男女共に育児休業等を活用しつつ、仕事と育児・介護の両立を目指すことが、ごく通常の考え方となりつつあるといえるのではないでしょうか。
一方で、実績として従業員の誰も育児休業等を利用したことのない企業や、育児や介護を理由にやむを得ず仕事を辞める選択を取る方が一定数存在するのも事実です。
両立支援等助成金は、育児休業等を従業員に適切に利用してもらえるよう、助成金を機に内部体制を整えてもらいたいという趣旨の制度です。
従業員から育児休業・介護休業の利用の申し出がありましたら、本助成金をきっかけに内部体制の整備を進めていただき、育児休業・介護休業の取りやすい職場環境を整えていただければと思います。