
パート・アルバイトなどの非正規雇用労働者を正社員に登用しようとする場合に、各人の適性や能力を見極め、かつ強化することができるのが、国がすすめる「有期型実習訓練」です。
短期間でバランスの良い研修が実施できるだけでなく、「人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)」という助成金を申請することもできます。
しかし、訓練を行って助成金を受け取るにはまず有期型実習訓練に関する計画を立て、あらかじめ労働局に確認をしてもらわなければなりません。
そこでこの記事では、有期実習型訓練を実施して人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)を受け取る方法について、ポイントを押さえて解説していきます。
目次
有期実習型訓練とは?

「有期実習型訓練」とは、パートやアルバイトなどの非正規雇用者を対象とした訓練の1つです。特に正社員経験の少ない非正規社員を対象としており、正社員化するにあたって必要なスキル・知識の習得を目的としています。
訓練を通して従業員のスキルを見極められるので、パート・アルバイトの正社員化を合理的に進めることが可能です。訓練終了後には「ジョブ・カード」をもとに訓練対象者を評価します。ジョブ・カードとは、職業能力の証明などに使えるツールとして厚生労働省が普及をすすめるものです。
この有期実習型訓練を行うことによって受けられるのが「人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)」という助成金です。助成金を活用すれば、訓練にかかる費用や、訓練対象者の賃金を一部補填できます。
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)について
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)では、訓練内容や対象となる従業員・事業主に関していくつもの条件が設定されています。
また、人材開発支援助成金の支給要件は令和3年4月に一部改正されました。この章では、助成金の申請条件や支給額などのほか、最新の変更内容もあわせて説明していきます。
人材開発支援助成金「特別育成訓練コース」とは
「人材開発支援助成金」は、労働者のキャリア形成を支援するための助成金制度です。中でも「特別育成訓練コース」は、非正規労働者の正社員化・処遇改善を目的としています。
支給対象となるのは非正規従業員を対象に訓練や研修を実施した事業主です。訓練にかかった費用や、訓練期間中の賃金が一部助成されます。
対象となる訓練について(有期実習型訓練)

有期実習型訓練を実施して人材開発支援助成金「特別育成訓練コース」を受給する場合は、次のような条件に沿った訓練を実施しなければなりません。
- 訓練期間が2カ月以上6カ月以内であること
- OJT(実務を通した訓練)とOff-JT(実務外での訓練・研修)とを組み合わせて行うこと
- 訓練をした合計時間が6カ月あたりの時間数に換算して425時間以上であること
- 訓練をした時間に対するOJTの割合が1割以上9割以下であること
- 訓練修了後は「ジョブ・カード」を使い、職業能力を評価すること
特に特徴的なのは、ジョブ・カードを利用する点です。ジョブ・カードを活用した訓練をするには、厚生労働省などに登録された専門のコンサルタントと従業員との個人面談が必要です。必要な日程を見積もり、人材の手配などをしていきます。ジョブ・カードの様式は、厚生労働省のホームページからダウンロード可能です。
また、OJTとOff-JTの内容にも、それぞれ細かい条件があります。
【Off-JTの条件】次のいずれかに該当する訓練であること
- 外部の職業訓練施設や学校に委託する訓練
- 外部講師に委託する訓練
- 都道府県から認定された認定職業訓練
- 上記以外で、特別な免許や実務経験を持つ人(※)が実施する訓練
※印の免許や実務経験を持つ人とは、専修学校の専門課程教員、職業訓練指導員免許、1級検定の合格者などが当てはまります。
【OJTの条件】次のいずれかに該当する訓練であること
- 適格な(訓練日の出勤状況、出勤・退勤時刻が確認できる)担当者の指導のもとに実施する
- 指導担当者は、事業主や役員・従業員など、当該事業所の関係者から選ぶ
有期実習型訓練の内容をどのように計画すべきかわからない場合は、全国の「キャリア形成サポートセンター」で相談・支援を受けられます。訓練カリキュラムの作成や評価方法などに悩んでいる場合は、積極的に活用しましょう。
助成金の支給額(賃金助成、実施助成、経費助成の3種類について)

人材開発支援助成金の支給額は、OJT・Off-JTの実施時間や訓練者の人数をもとに算定します。支給額にはOff-JTの賃金助成/経費助成、OJTの実施助成の3種類の区分があり、それぞれの区分の合計金額が支給されます。
区分ごとの支給額は次の表のとおりです。
| 区分名 | 支給金額 | 支給上限 |
| 賃金助成 | Off-JTの実施・1人1時間につき760円(475円) 生産性向上時は960円(600円) |
1人1200時間分まで |
|---|---|---|
| 経費助成 | Off-JTの合計訓練時間が ・20時間以上〜100時間未満の場合: 10万円 (7万円) ・100時間以上〜200時間未満の場合: 20万円(15万円) ・200時間以上の場合: 30万円(20万円) |
実費の範囲内 |
| 実施助成 | OJTの実施・1人1時間につき 760円 (665円) 生産性向上時は960円(840円) |
1人680時間分まで |
表のカッコ内は大企業への支給額です。
賃金助成・実施助成は参加者1人あたりの時給を一部補助する制度ですが、1人あたりの助成に上限が設定されています。また、経費助成では実際に訓練にかかった費用以上の助成を受けることはできません。
また、1年度における1事業所あたりの支給額は1000万円が限度となっています。
受給額の計算にあたっては、対象者が実際に訓練を受けた時間を記録しておかなくてはなりません(申請書類に要記入)。対象となる受講者がOJTとOff-JTそれぞれで予定訓練時間の8割以上を受講していない場合、助成金の支給は受けられません。
有期実習型訓練の対象となる労働者の要件

有期実習型訓練の対象となる労働者は、次の条件をすべて満たす人です。
・自社で雇用するパート・アルバイトなどの非正規雇用労働者である(新規・既存雇用者とも対象)
・訓練終了日または支給申請日の時点で、訓練実施の事業主のもと雇用保険の被保険者になっている
・過去6カ月以内に、別の公共職業訓練や有期実習型訓練などを受けていない(他の事業所での経験含む)
・ジョブ・カード作成アドバイザーが有期実習型訓練の必要性を認め、実際にジョブ・カードを作成した
「ジョブ・カード作成アドバイザー」とはジョブ・カードを活用したキャリア相談ができる人で、厚生労働省や関係団体に登録されています。従業員が有期実習型訓練の対象となるかどうかは、「ジョブ・カード作成アドバイザー」との面談による判断が必要です。
面談は、原則として対象者とジョブ・カード作成アドバイザーが個別に面談する方式で実施します。令和3年4月からは条件が緩和され、テレビ電話等での面談も認められるようになりました。ただし、グループワークなどの集団形式による面談は認められていません。
また、「有期実習型訓練が必要」と判断されるには、次の項目のいずれかに該当している必要もあります。
・訓練を実施する分野で、キャリア面談の実施日から過去5年以内に通算3年以上の正規雇用歴・自営などの就労歴がない
(なおかつ、過去10年以内に同一企業で6年以上継続して正規雇用された経験や自営等の経験がない)
・過去5年以内に半年以上のあいだ休業をしていた
・単純作業に従事していて、体系立てられた座学の職業訓練を受けたことがない
・訓練予定の分野で通算3年以上の正規雇用経験があるが、1年未満で離転職を繰り返すなどした
有期実習型訓練自体は正規雇用された経験の浅い労働者を対象としていますが、正規雇用歴のある場合でも「有期実習型訓練への参加が必要」と認められる場合があります。従業員の職務経験を細かく把握し、スキルアップが必要な人にもれなく訓練の機会を提供しましょう。
有期実習型訓練の対象となる事業主の要件

事業主として有期実習型訓練の対象となるには、まず雇用保険の適用事業主である必要があります。それに加えて、以下の条件を満たしていなければなりません。
・非正規従業員を雇用している、あるいは新たに雇用する
・職業訓練計画を作成し、管轄の労働局から受給資格の認定を受けている
・認定された訓練計画に沿って訓練を実施した
・訓練期間中に、対象労働者への賃金を適正に支払っている
・訓練対象者への賃金支払い、訓練状況、訓練にかかった経費などを明記した書類を整備している
訓練の実施内容などに特に不正がない場合でも、経費や訓練状況などをしっかり記録していないと支給されません。必要書類はこのあと説明しますが、書類の管理、記録もれには十分に注意する必要があります。
さらに、訓練計画書の提出から過去6カ月間の、従業員の離職状況に関連する次のような条件もあります。
・雇用保険被保険者を事業主都合で離職させていない
・「特定受給資格離職者」となった労働者数が3人以下、または申請日時点の雇用保険被保険者数の6%以内である
特定受給資格離職者とは、倒産・事業縮小などに伴う離職や労働者自身に責がない解雇などによる離職者をいいます。過去に倒産や解雇等によって退職させた職員がいないか、過去の記録を事前に確認しておきましょう。
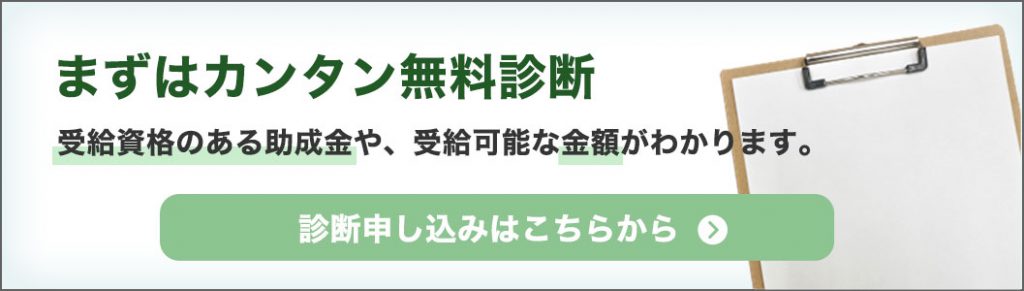
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の申請の流れと必要書類
ここからは、助成金申請に関わる各手続きの流れや注意点について説明します。
有期実習型訓練には、「基本型」「キャリアアップ型」の2種類があります。「基本型」は新たに雇用した従業員が対象、「キャリアアップ型」では、既に雇用している従業員が対象です。
【基本型とキャリアアップ型の違い】
| 基本型 | キャリアアップ型 | |
| 対象者 | 新規雇用した非正規従業員 | 訓練前から雇用している非正規従業員 |
|---|---|---|
| 手順 | 訓練計画届を労働局に提出 ↓ ジョブ・カード作成アドバイザーとの面接 |
ジョブ・カード作成アドバイザーとの面接 ↓ 訓練計画届を労働局に提出 |
双方で手続きの順番が異なる点にも注意しましょう。なお、基本型の従業員とキャリアアップ型の従業員の両方が訓練対象になっている場合は、別々に手続きすることが必要です。
訓練計画届の作成・提出

基本型、キャリアップ型のいずれにしても、有期実習型訓練を実施する前に訓練計画を作成・提出しなければなりません。
計画は「人材開発支援助成金(特別育成訓練コース(有期実習型訓練))計画届」にまとめ、以下の添付書類とともに提出します。訓練開始日から数えて1カ月前の日までに、管轄の労働局に提出し、確認を受けてください。
訓練計画届の提出時に必要となる添付書類
・ジョブ・カード様式3-3-1-1:企業実習・OJT用(写)
・訓練対象者全員分の「有期実習型訓練に係る訓練カリキュラム」(様式第1-3号(別添様式1))
(キャリアアップ型の場合は、ジョブ・カード作成アドバイザーによる面談済みのもの)
・有期実習型訓練に係る訓練計画予定表(様式第1-3号(別添様式2))
・訓練期間中の対象労働者の労働条件が確認できる書類
(雇用契約書、労働条件通知書など)
・ジョブ・カード様式1-1(キャリア・プランシート)(写)
・ジョブ・カード様式2(職務経歴シート)(写)
・ジョブ・カード様式3-1(職業能力証明(免許・資格)シート)(写)
・ジョブ・カード様式3-2(職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート)(写)
このほか、労働局が必要と判断した書類の提出を求められることもあります。また、次のようなケースではそれぞれに記載の書類が必要です。
【事業主が中小企業の場合】
・中小企業事業主であることを確認できる書類
(登記事項証明書、事業所確認票など)
【基本型の場合】
・訓練対象者の雇用形態がわかる書類
・訓練の趣旨・評価基準を説明したことが確認できる書類
(訓練対象者本人の署名入り確認書など)
【Off-JTを外部機関や講師などに委託しない場合】
・Off-JTの担当講師の要件を確認する書類
労働局に提出する添付書類の様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。書類は様式の変更ができないものが多いので注意してください。また、ジョブ・カードは原本ではなく写しを提出しましょう。
各書類は期間を過ぎると提出できなくなります。書類の作成や準備スケジュールには十分注意してください。
キャリア面談の実施〜有期実習型訓練

訓練の前に、訓練対象となる従業員に対してジョブ・カード作成アドバイザーによる面接を行います。面談時には「ジョブ・カード」を作成し、訓練内容や計画に基づいたカウンセリングが実施されます。
訓練が必要だと判断されたら、訓練計画届に基づいて訓練を実施しましょう。訓練は、計画届を提出した日から6カ月以内に開始しなければなりません。
訓練の変更
計画届の確認を受けた後に訓練内容などを変更する場合は、「人材開発支援助成金(特別育成訓練コース(有期実習型訓練))計画変更届」の提出が必要です。指定された添付書類と一緒に、管轄の労働局に提出してください。
提出期限は、変更前の訓練実施日か変更後の訓練実施日のうち、いずれか早い方の日の前日までです。
訓練終了〜支給の申請
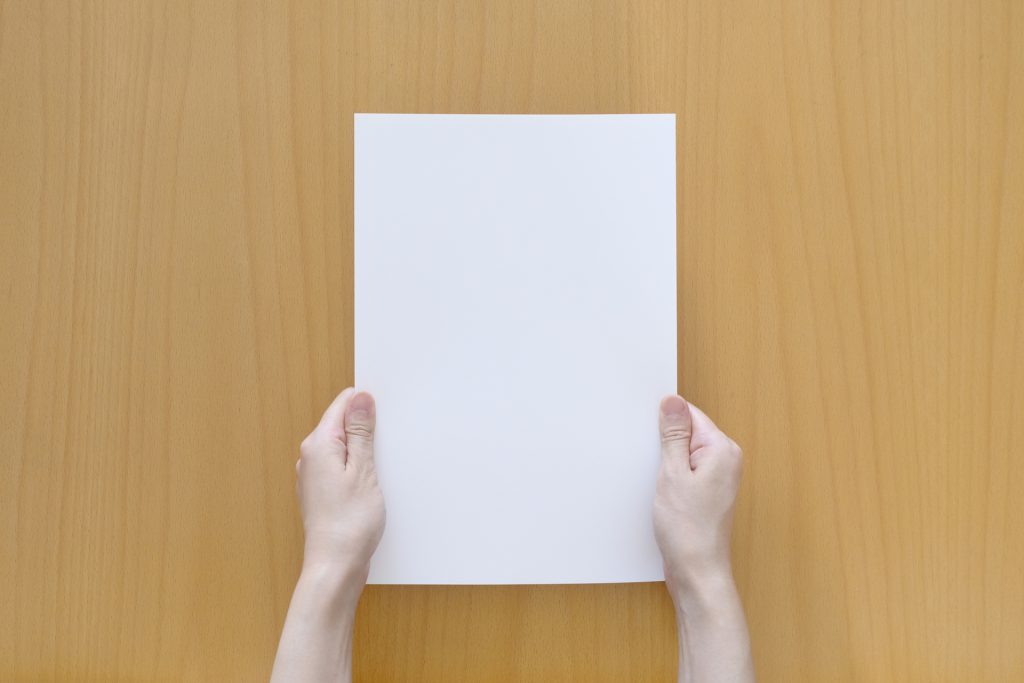
職業訓練が終了したら、終了日の翌日から2カ月以内に助成金の申請を行います。申請書類を労働局に提出し、審査を受けましょう。申請に必要な書類は次のとおりです。
・人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)支給申請書(様式第5号)
・支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
・特別育成訓練コースの内訳(様式第5号(別添様式1))
・賃金助成及び実施助成の内訳(様式第5号(別添様式2))
・経費助成の内訳(様式第5号(別添様式3-1))
・Off-JT実施状況報告書(様式第5号(別添様式4-1))
・OJT実施状況報告書(様式第5号 (別添様式4-2))
・訓練中の出勤状況がわかる書類(出勤簿など)
・訓練中の賃金支払状況がわかる書類(賃金台帳など)
・経費負担の状況がわかる書類(領収書、請求書、会計台帳など)
・訓練対象者ごとのジョブ・カードの様式3-3-1-1(企業実習・OJT用)(写)
・不正受給に関与していた場合に連帯債務を負うこと等についての承諾書(様式第5号(別添様式7))
・その他、労働局が必要と判断した書類(就業規則など)
必要書類は10種類以上に及ぶため、できるだけ早めに整理しておきましょう。賃金や経費などの関連書類は、内訳だけでなく証拠となる書類(領収書など)も必要です。
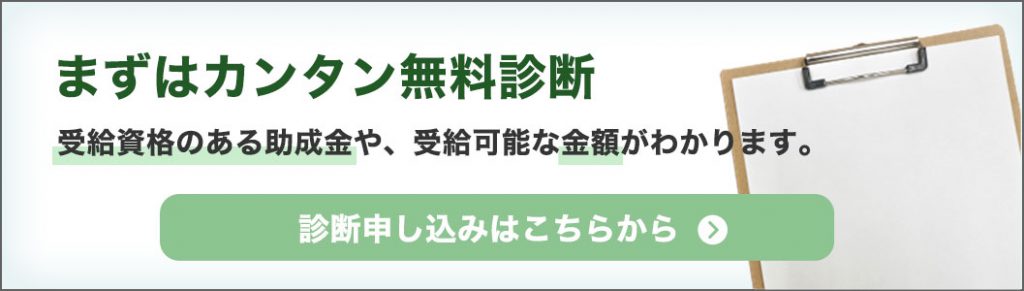
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)のメリット・デメリット

では改めて、人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)を利用するメリットとデメリットについて確認しておきましょう。
メリット

有期実習型訓練を行って人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)を受けることには、主に次の3つのメリットがあります。
- 訓練の受講者を正社員化する場合、別の助成金も申請できる
- 助成金の受給額が訓練時間に比例して多くなる
- 人材育成にかかるコストを一部補填できる
助成金は同時に複数申請できないものが多い中、人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)では「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」も例外的に追加で申請可能です。別に計画書を準備するところから始める手間はありますが、両方の助成金が受け取れるのであれば積極的に活用したいところです。
また訓練時間に比例して支給額が多くなる点もポイントです。最大で1000万円の支給が受けられることもあり、人材育成のために積極的に訓練を設計できます。
デメリット

人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の利用では、主に申請手続きの面でデメリットがあります。
- 申請の手順が複雑で分かりにくい
- 申請手順が間違っていると受給できない
初めて申請する場合には特に、各人ごとのカリキュラムの作成や訓練日誌の作成・確認に手間がかかります。
書類の準備や確認事項も多いため、多忙だったり社内リソースがなかったりする場合には外部の専門家に頼るのがおすすめです。
助成金の申請ならBricks&UKにおまかせ

人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)を活用すれば、訓練を通じて従業員の正社員化を進められます。また、訓練を実施し助成金を受けると、訓練に要した費用や賃金の一部を補填できるメリットがあります。ただし、手続きが複雑でわかりにくいというデメリットもあります。
手続きに不安がある場合は、助成金の専門家である社会保険労務士に依頼するのがおすすめです。当社Bricks&UKでは、有期実習型訓練のカリキュラムや評価シートの作成支援なども承っています。
自社が申請できる助成金が他にないかも知りたい、効率よく手続きを行いたいという場合には、ぜひBricks&UKまでお問い合わせください。
就業規則を無料で診断します
労働基準法等の法律は頻繁に改正が行われており、その都度就業規則を見直し、必要に応じて変更が必要となります。就業規則は、単に助成金の受給のためではなく、思わぬ人事労務トラブルを引き起こさないようにするためにも大変重要となります。
こんな方は、まずは就業規則診断をすることをおすすめします
- 就業規則を作成してから数年たっている
- 人事労務トラブルのリスクを抱えている箇所を知りたい
- ダウンロードしたテンプレートをそのまま会社の就業規則にしている
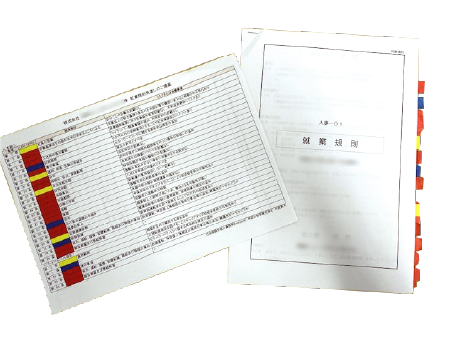













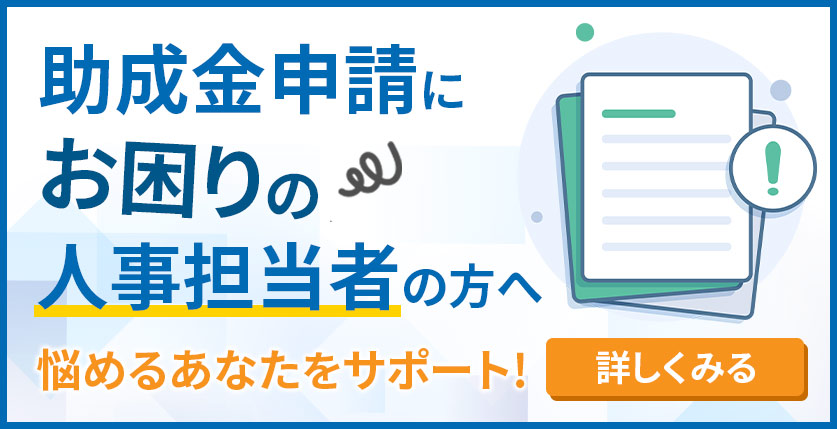
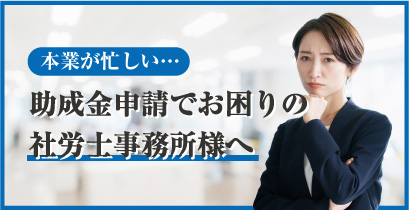
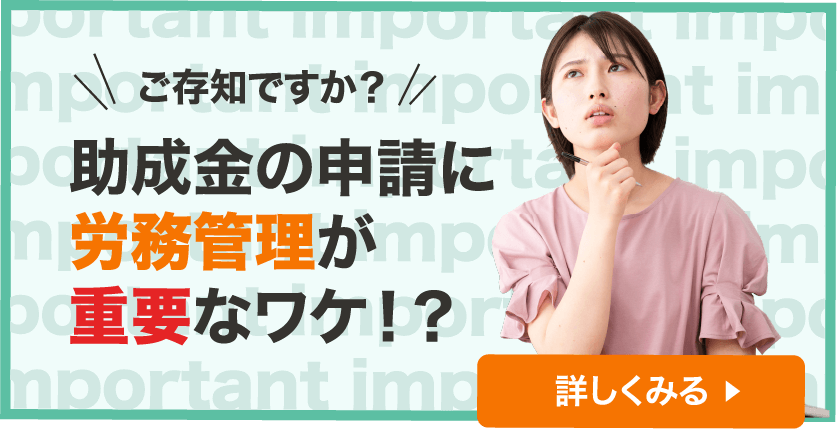
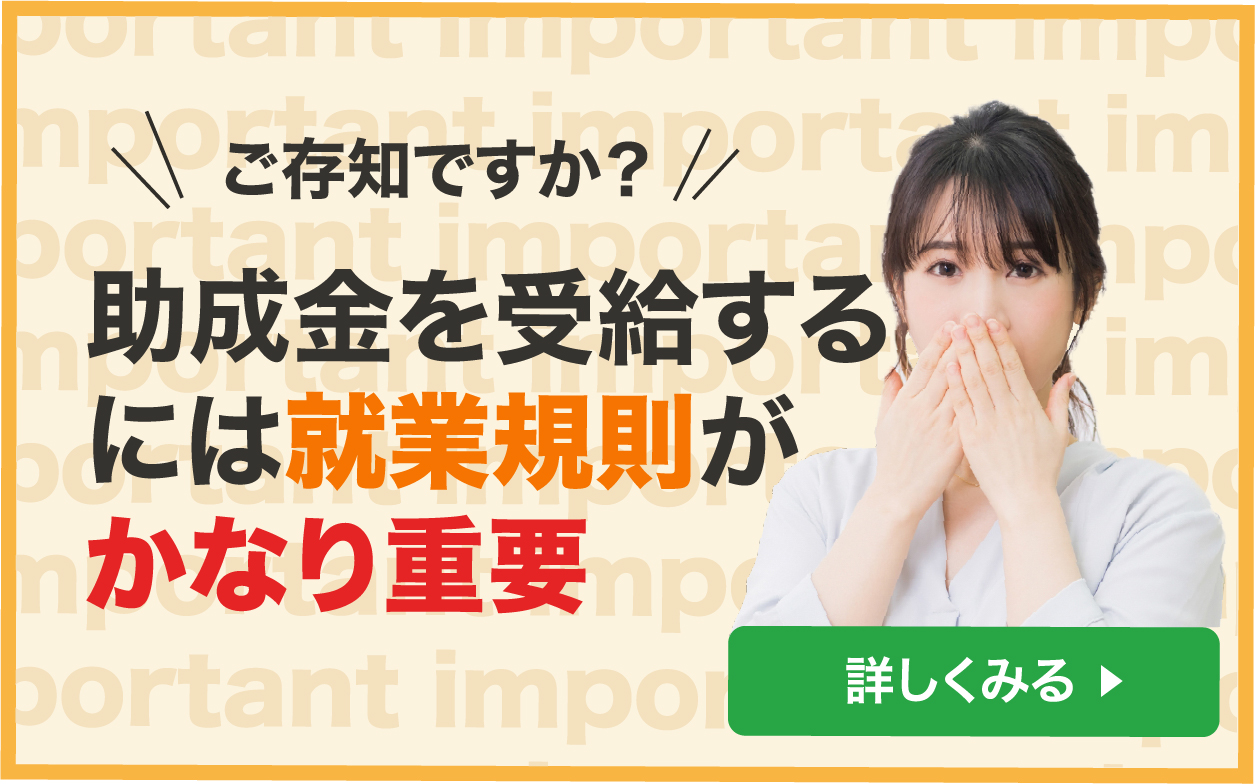

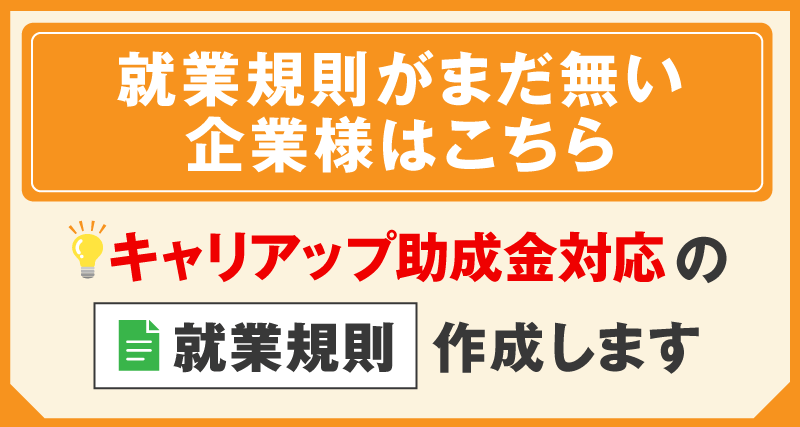
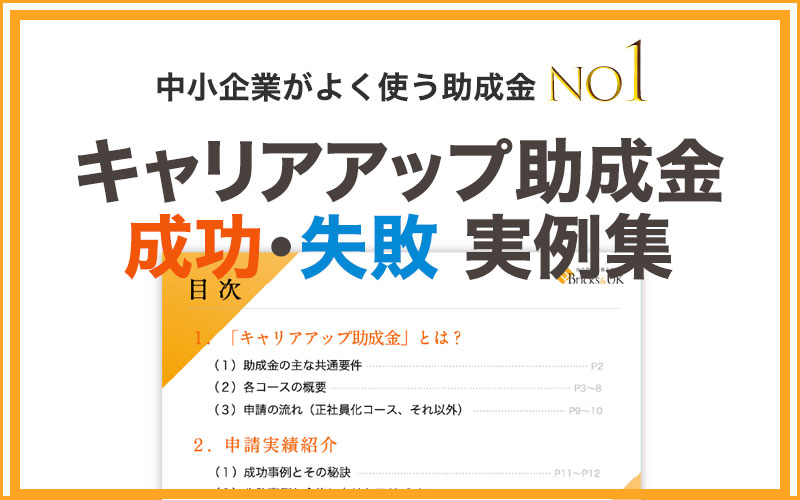


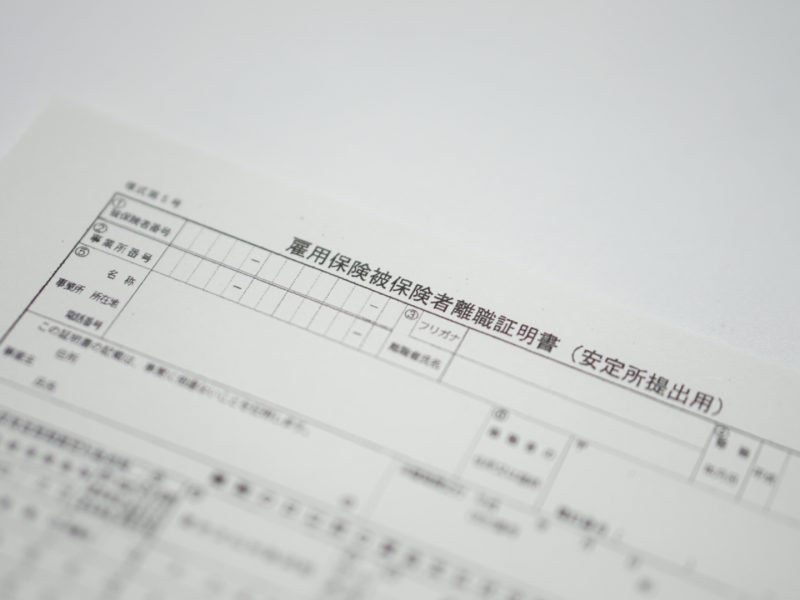

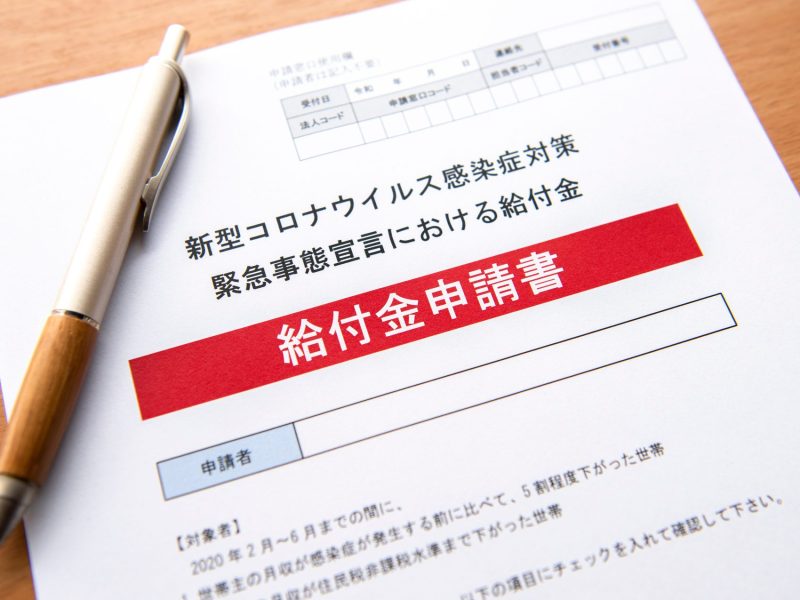
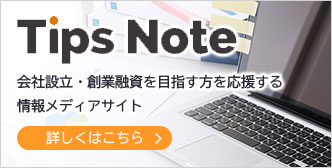


監修者からのコメント 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)は助成金をもらいながらOJTができる優れた制度です。 訓練の評価もジョブカードを活用して行うことができ、今後の課題確認や目標設定につなげることができます。 一方で、訓練の計画届を提出するまでに作成しなければならない書類が多く、手順も煩雑なため申請を断念される事業主様も少なくありません。 弊社Bricks&UKでは訓練計画届の提出代行もサポートしております。 お気軽にお問い合わせください。