
母子家庭の母親は、子育てのために時短勤務や突然の早退、欠勤など、勤怠が不安定になることは避けられません。そのため、就職したくてもなかなか難しい現状にあります。
しかし多様な働き方が認められるべきとされる今、企業には、母子家庭の母などのひとり親のほか高齢者、障害者など、一般的に「就職が困難な人」を積極的に採用することが求められています。そして国は、採用した事業主に助成金を支給する制度を整えています。
この記事では、母子家庭の母を雇用した事業主が受けられる「特定求職者雇用開発助成金」の「特定就職困難者コース」をわかりやすく解説します。
目次
特定求職者雇用開発助成金とは

特定求職者雇用開発助成金は、一般に「就職が難しい」とされる高齢者や障害者、母子家庭の母等の雇用を促すために設置された助成金です。
該当する人を雇い入れ、継続雇用することで助成金が受けられます。ただし、雇い入れにはハローワーク等を経由することなど、さまざまな要件があります。
対象者によって複数のコースがあり、現在あるのは次のコースです。
- 特定就職困難者コース
- 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
- 就職氷河期世代安定雇用実現コース
- 生活保護受給者等雇用開発コース
- 成長分野等人材確保・育成コース
このうち、母子家庭の母等を雇う場合に使えるのが、「特定就職困難者コース」です。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の対象

特定求職者雇用開発助成金の特定就職困難者コースは、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワークや民間の職業紹介業者の紹介で、継続雇用を前提に雇い入れた事業主が受けられる助成金です。
支給の要件などについて、詳しく見ていきましょう。
支給対象となる労働者の要件
特定就職困難者コースで助成の対象となるのは、次のような「就職困難者」を雇い入れた場合です。
- 母子家庭の母等
- 父子家庭の父(児童扶養手当の受給者に限る)
- 満60歳以上の高年齢者
- 身体障害者、知的障害者、精神障害者
- ウクライナ避難民、補完的保護対象者
ただし「満60歳以上の高年齢者」を除き、雇い入れ日現在で満65歳未満に限られます。
ここでいう「母子家庭の母等」とは、離婚や死別などにより配偶者のいない女性、もしくは、配偶者が心身の障害で労働能力がなく扶養する必要がある女性、かつ20歳未満の子または一定の障害がある子を養う母親をいいます。
一定の障害とは、視力なら良い方の視力が0.07以下など、障害者手帳の級とは異なる区分で定められたものです。
また、令和4年5月30日より当面の間、ウクライナ避難民も対象者に含まれます。また、令和5年12月1日より当面の間、補完的保護対象者についても対象となっています。
補完的保護対象者とは、難民法の難民には該当しないものの、身の危険などの理由で人道的に他国での保護が必要と認められた人です。
対象労働者についての不支給要件
就職困難者に該当する場合でも、次のいずれかに該当する労働者の雇い入れは助成の対象外となります。
- 紹介された時点で在職している
- 過去3年間に事業所と雇用や派遣、請負などの関係にあった
- 事業主の3親等以内の親族である
- 助成対象期間の途中などで離職した
- 性風俗関連営業の接待業務などに従事している
離職について、労働者側に責任がある事由での解雇などやむを得ない場合は、離職日を含む支給対象期を除き、支給対象となり得ます。
支給の対象となる事業主の要件
事業主についても、次のような要件があります。
●雇用保険の適用事業主である
●対象者をハローワーク等の紹介により採用する
●対象者を正規あるいは無期、自動更新の有期契約で雇用する
●雇い入れ後、継続して2年以上雇用することが確実である
●対象労働者に賃金を支払っている
雇用形態について、令和5年10月から、有期雇用契約での雇い入れの場合、当人が望む限り更新が可能な「自動更新」であることが条件となっています。雇用契約書に「自動更新」を明記しなくてはなりません。
事業主についての不支給要件
上記に該当していても、次のいずれかに当てはまる場合は支給の対象外です。
●当人についてハローワーク等の紹介前から選考に入っていた
●雇い入れ前後6カ月間に事業主都合による解雇者を出した
●雇い入れより前に同コース等での支給決定がなされた人を、過去3年間の助成対象期間中に事業主都合で解雇・雇い止め等した
●雇い入れ前後6カ月間の倒産や解雇などによる離職者数が、雇い入れ日時点の被保険者数の6%を超えている
●労働保険料を滞納している
このほか、賃金の支払いに遅れがあったり、紹介時と異なる労働条件での雇い入れなど労働者への不利益があったりした場合にも、助成金は支払われません。
特定就職困難者コースの受給金額

事業主が対象労働者に支払った賃金の助成として、半年の支給対象期間ごとに助成金が支給されます。
金額は、対象労働者の区分(母子家庭の母等や障害者など)と、短時間労働者であるかどうか、また企業規模によっても異なります。
母子家庭の母や高年齢者、ウクライナ避難民などを雇用した場合の支給額は次のとおりです。
【母子家庭の母等を雇い入れた場合の支給額】
| 企業規模区分 | 支給総額 | 支給対象期ごとの支給額×支給回数 | |
|---|---|---|---|
| 短時間労働者以外 | 中小企業 | 60万円 | 30万円×2期 |
| 大企業 | 50万円 | 25万円×2期 | |
| 短時間労働者 | 中小企業 | 40万円 | 20万円×2期 |
| 大企業 | 30万円 | 15万円×2期 |
短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者のことです。
助成金は、6カ月ごとの支給対象期に区切り、母子家庭の母等の場合は2回支給されます。申請もこの支給対象期ごとに行わなくてはなりません。
ただし、所定労働時間より実労働時間が著しく短い場合や、週あたりの賃金額が「最低賃金×30時間」を下回る場合には、減額されることがあります。
また、支給対象期に支払った賃金の額が上記より低い場合には、その賃金と同じ額が支給の上限です。
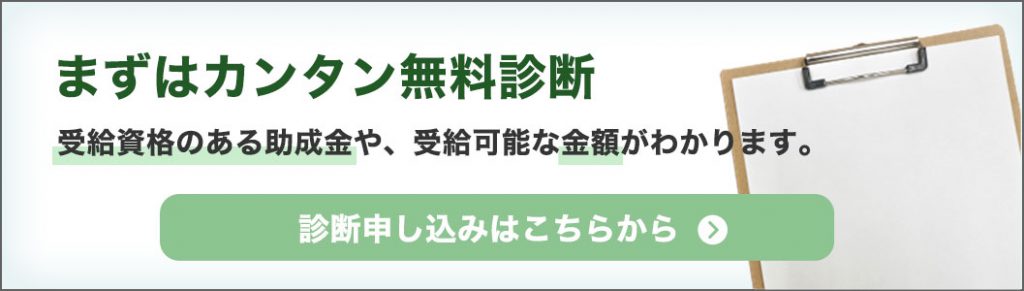
特定就職困難者コースの申請の流れと必要書類

特定求職者雇用開発助成金の特定困難者コースを受給するには、申請書類を用意して期限内に申請する必要があります。
助成金申請の流れ
支給申請は、支給対象期ごと、そして各支給対象期の末日の翌日から2カ月以内に、労働局またはハローワークに書類を提出して行います。
では改めて、対象となる労働者の雇い入れから支給申請までの流れを見ていきましょう。
- ハローワーク等に求人広告を出す
- ハローワーク等の紹介で対象者を雇い入れる
- 対象者を雇用保険に加入させる
- 労働局による確認後、制度の周知文と支給申請書が交付される
- 雇い入れから6カ月を経過した翌日以降に1期目分の支給申請をする
- 労働局により審査・支給決定がされる(通知書が届く)
- 1期目分の助成金が口座に振り込みされる
上記のステップのうち、「4」の「雇い入れ日時点」で要件を満たしているかどうかの確認が行われます。該当しない場合には、その旨が文書で通知されます。
「6」の申請後の審査でも、前述の通り不支給要件に当てはまったり、期間内に従業員の解雇等や対象者の離職があったりした場合には不支給となります。
2期目分の申請は、1期目終了後さらに6カ月が過ぎ、かつ2カ月以内の間に、同じように支給申請を行います。
申請は1期ごとに必要です。2期目が終わるころには1期目の申請締め切りが過ぎていることになるので注意してください。
助成金申請に必要な書類
特定就職困難者コースの申請は、支給対象期で異なる様式の申請書を労働局長に提出します。
- 第1期支給申請書(様式第3号困)
- 第2期支給申請書(様式第4号困)
また、添付必須書類として次の書類の提出が必要です。
・労働時間や手当ごとの区分がわかる賃金台帳またはその写し
・支給対象期の出勤状況がわかる出勤簿等またはその写し
・雇い入れ日時点で対象労働者であると証明する書類(★)
・週の所定労働時間や雇用契約期間がわかる雇用契約書か雇入通知書の写し
・対象労働者雇用状況等申立書
・有料・無料職業紹介事業者等の発行した職業紹介証明書
(ハローワーク以外での雇い入れの場合)
・支給要件確認申立書
★印の「対象労働者であると証明する書類」については、母子家庭の母等の場合は次のようなものが該当します。
・遺族年金の受給権者が所持する国民年金証書(写)
・児童扶養手当の受給が証明できる書類(写)
・母子福祉資金貸付金の貸付決定通知書(写)
・通勤定期乗車の特別割引制度に基づき市区町村長などが発行する特定者資格証明書(写)
・母子家庭の母等に対する手当や助成制度の受給が確認できる書類(写)
さらに、必要に応じて就業規則や総勘定元帳、離職者がいた場合の労働者名簿などが必要となることもあります。何が必要となるかはケースバイケースとなるので注意が必要です。
条件を満たせば助成額が1.5倍となる可能性も

「特定就職困難者コース」の対象となる母子家庭の母を雇い入れ、次の条件にも当てはまる場合には、当コースの1.5倍となる助成金が受けられる可能性があります。
いずれも、助成額は90万円(45万円×2期)です(短時間の場合は60万円、30万円×2期)。
未経験者に育成訓練+賃上げを行った場合

次の条件を満たせば、特定求職者雇用開発助成金の「成長分野等人材確保・育成コース」の「人材育成」の助成が受けられます。
- 未経験分野への就職を希望する就職困難者を採用する
- 人材開発支援金を活用した訓練を行う
- 賃金を引き上げる
賃金は、雇い入れ日から3年以内に、基本給(毎月決まって支払われる賃金)を5%以上引き上げる必要があります。
デジタル・グリーン分野の業務に従事させる場合

次の条件を満たす場合には、同「成長分野等人材確保・育成コース」の「成長分野」の助成が受けられます。
- 対象労働者を「デジタル・グリーン分野(成長分野等)」の業務に従事させる
- 対象者に対し、雇用管理の改善または職業能力開発の取り組みを行う
- 上記に関する実施結果報告書を提出する
「デジタル分野」の業務とは、厚労省による職業分類表の「情報処理・通信技術者」や、データサイエンティスト、ウェブデザイナーに該当するものをいいます。
「グリーン分野」は、職業分類表の「研究・技術の職業」に該当する、脱炭素・低炭素化などに関するものをいいます。
これらは、少し関与すればいいというものではなく、主な業務がいずれかの分野に該当する必要があります。
人材育成の助成を受けるには、人材開発支援助成金の要件も満たす必要があります。2種類の助成金を申請することとなり手続きが複雑化するため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
特定就職困難者コースを申請する際の注意点

特定求職者雇用開発助成金「特定就職困難者コース」を受給するには、要件を満たし、必要書類をすべて揃える必要があります。
上で紹介した主な要件はもちろん、全助成金に共通の要件等もあるので、支給要綱をしっかりと見ておくことが必要です。
最後に、特に注意すべき点について押さえておきましょう。
直接的な応募では対象外となる
助成金の対象となるのは、「ハローワーク等」を経由した雇用に限られます。たとえば知人の紹介や、求人サイトを経由した応募、自社サイトからの直接的な応募などは助成の対象外です。
「ハローワーク等」とは、地方運輸局(船員として雇い入れる場合)、や民間の有料・無料職業紹介事業者などが当てはまります。そのため、まずはハローワーク等に求人を出すところから始める必要があります
紹介で初めて知り得た人に限る
助成金を受けるには、対象者を紹介されて初めて雇用契約を結ぶ場合に限られます。過去3年間にアルバイト勤務や派遣での雇用、委託契約などがあると対象外です。また、研修などの参加も対象となりません。
ハローワーク等で紹介される以前に雇用しようとしていた人がたまたま母子家庭の母などであった場合などに、形式的に紹介の形を取ったとしても、この助成金の対象とはなりません。
受給には法令の遵守が大前提
助成金の申請には、労働法など各種の法令を遵守していることが大前提です。助成金とは一見関係のないことでも、不支給となるケースがあるので注意しなくてはなりません。
たとえば、雇用契約時に労働条件通知書を交付していなかったり、出勤簿など必要とされている帳簿を付けていなかったり。就業規則の内容が最新の法令に基づいていない場合にも、支給対象外となるおそれがあります。
また、時間外手当など賃金の未払いがあったり、労働保険料を滞納していたりしてもいけません。過去に不正受給などがあった場合にも不支給となります。
助成金の申請ならBricks&UKにおまかせ

特定求職者雇用開発助成金は、就職が困難な人を雇用する事業主に支給されるインセンティブ的な性質を持つ助成金です。母子家庭の母親を雇う場合、この助成金の特定就職困難者コースが利用できます。
ただ、受給には細かな要件等があり、手続きに手間や時間がかかります。専門知識がないと難しい部分も多々あるので、申請する際は助成金のプロである社会保険労務士に相談することをおすすめします。
当サイトを運営する「社会保険労務士事務所Bricks&UK」では、助成金の要件を満たす環境整備や就業規則の整備など、基礎的な段階からサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。
就業規則を無料で診断します
労働基準法等の法律は頻繁に改正が行われており、その都度就業規則を見直し、必要に応じて変更が必要となります。就業規則は、単に助成金の受給のためではなく、思わぬ人事労務トラブルを引き起こさないようにするためにも大変重要となります。
こんな方は、まずは就業規則診断をすることをおすすめします
- 就業規則を作成してから数年たっている
- 人事労務トラブルのリスクを抱えている箇所を知りたい
- ダウンロードしたテンプレートをそのまま会社の就業規則にしている
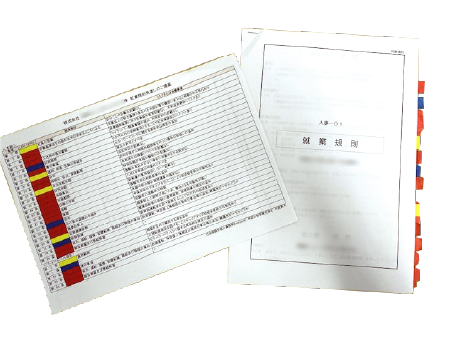













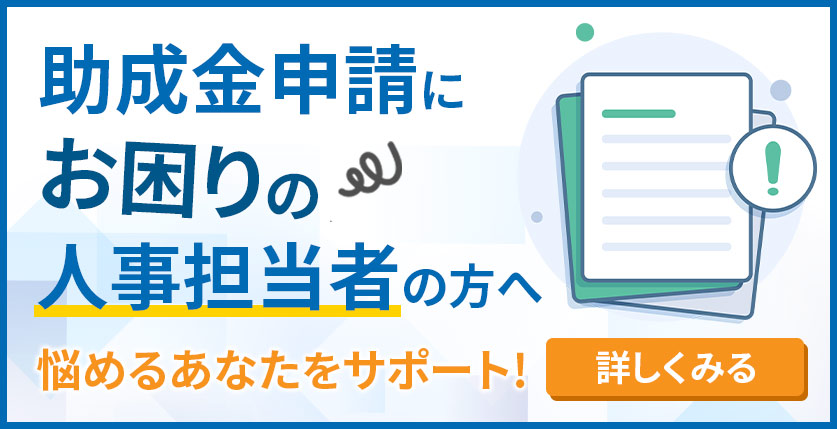
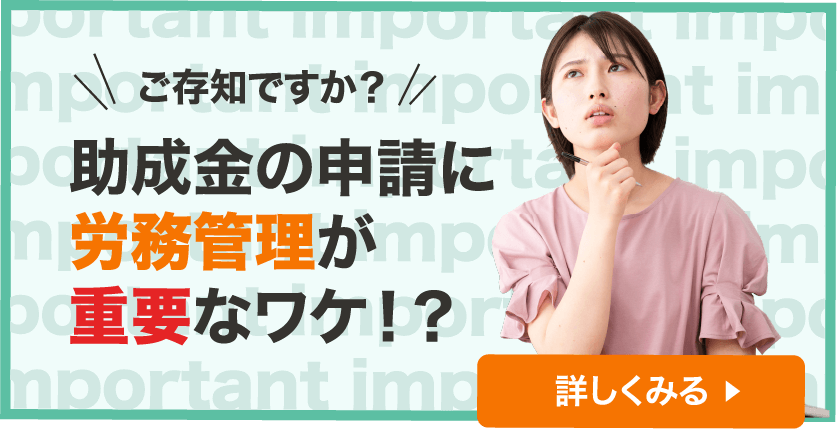
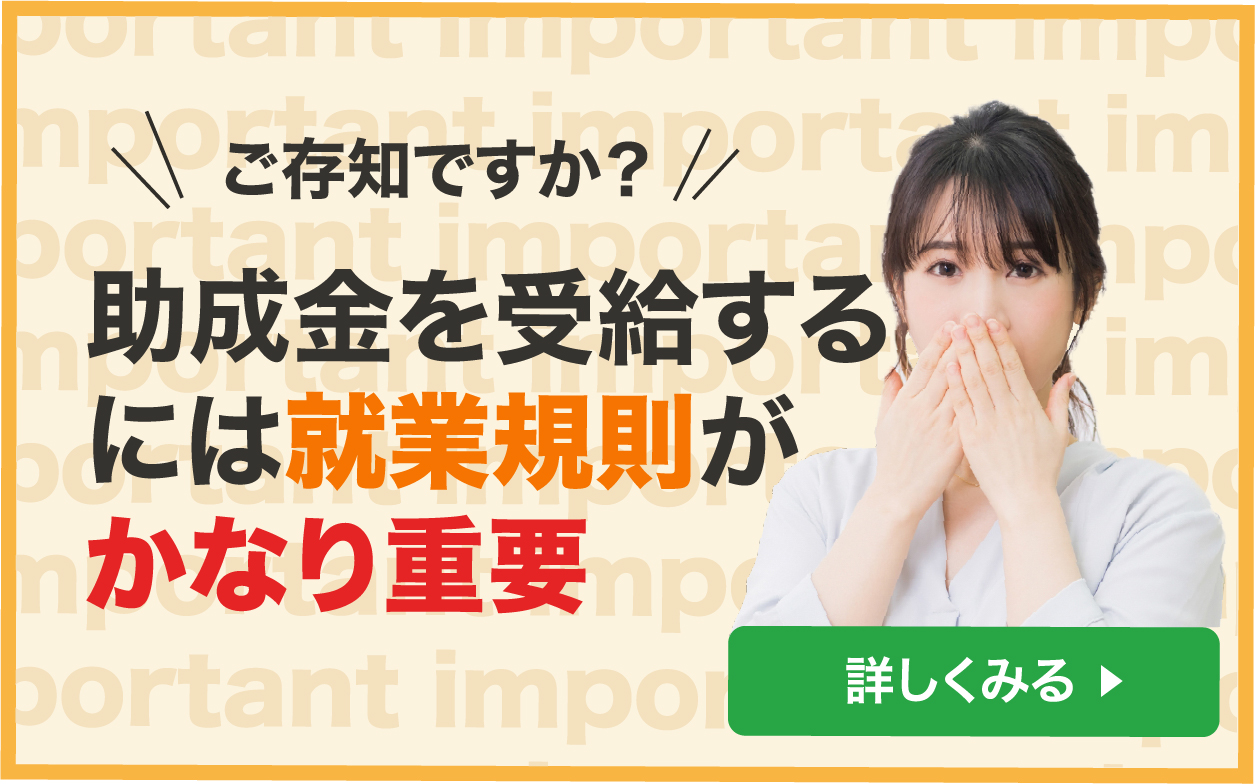

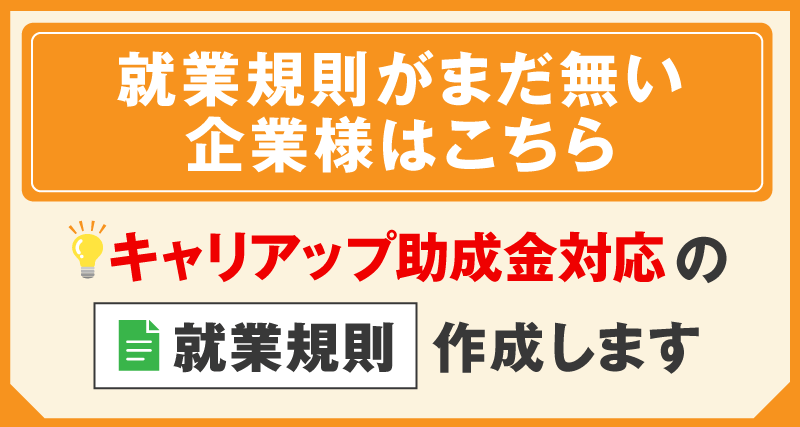
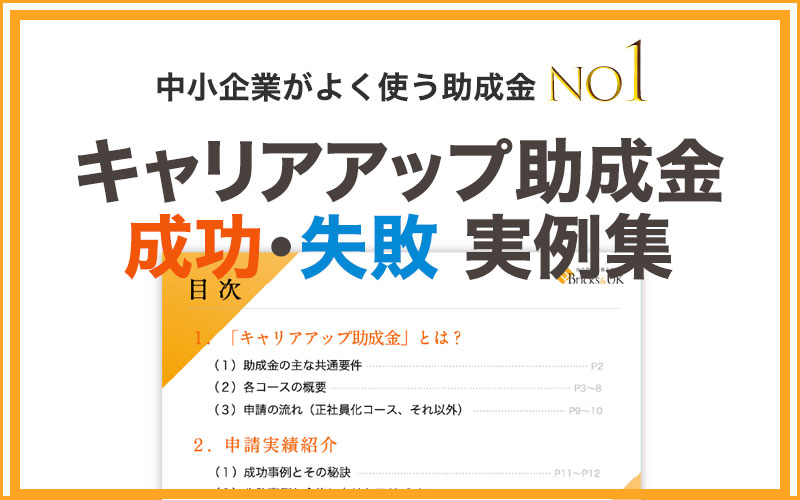

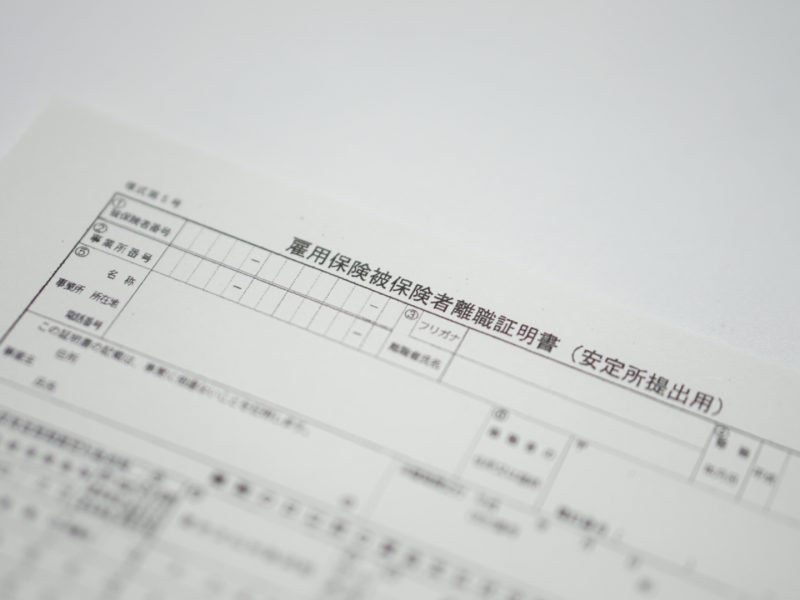

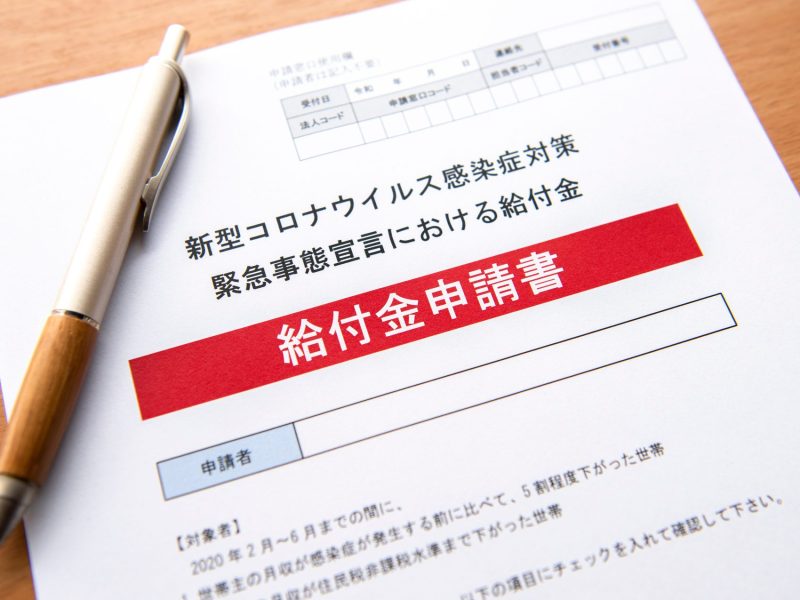
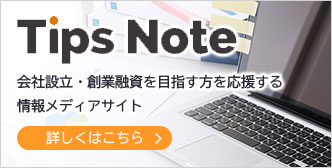


監修者からのコメント 特定求職者雇用開発助成金は、助成金が初めてという事業主様でも比較的取り組みやすい助成金です。 揃える資料は多いですが、申請書の記入例もありますので、丁寧にすすめていけば失敗することも少ないかと思います。 弊社でも多くの申請代行のご依頼をいただいております。 とにかく時間がない!手間をかけたくない!という事業主様はご連絡ください。 弊社にて申請をサポートさせていただきます。