
人手不足や技術革新が進む中、従業員のスキルアップは企業にとって不可欠です。しかしスキルアップのための教育にも、結構なコストがかかります。
そこで活用したいのが「人材開発支援助成金」です。2025年度も申請を受け付けていますが、一部要件などが変更されているので要注意。最新情報を把握した上で申請準備を始めなくてはなりません。
この記事では、2025年度の人材開発支援助成金について、6つのコース内容や2024年度からの変更点、申請時の注意点などを解説します。
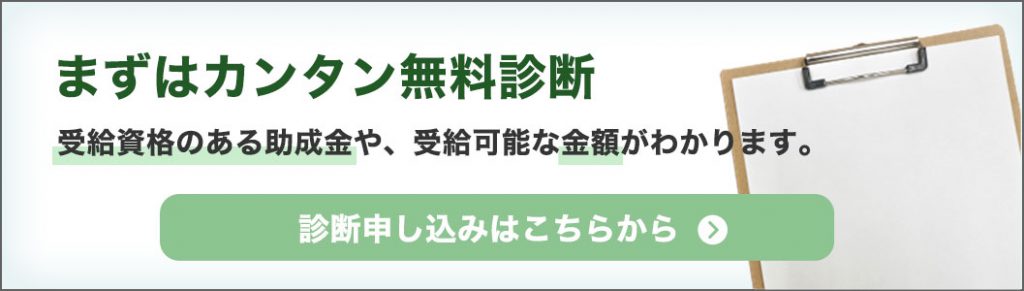
目次
人材開発支援助成金とは

人材開発支援助成金は、従業員に職業能力開発のための教育訓練を行った事業主に対し、その費用の一部を助成する制度です。
従業員のスキルアップを図ることで企業の生産性向上を促し、雇用の安定を図るのが制度の目的です。対象によって異なる、複数の訓練コースが設けられています。
助成は次の2つの項目について行われます。
- 訓練経費への助成・・・教育訓練にかかる教材費や受講料などの費用を助成
- 賃金助成・・・従業員が訓練を受けている間の賃金の一部を助成
申請は、まず訓練計画を立てて管轄の労働局に提出します。訓練を実施してその費用や賃金を支払ったのち、支給申請を行う流れです。
2025年度の全訓練コースと助成の対象

2025年度、人材開発支援助成金には次の6つのコースが設けられています。対象はコースにより異なりますが、いずれも「職務に関連した知識・技能を習得するための訓練」でなくてはなりません。
| コース名 | 概要・主な対象 |
|---|---|
| 人材育成支援コース | 10時間のOFF-JT、新卒者や有期契約労働者に対するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練 |
| 教育訓練休暇等付与コース | 教育訓練のための有給の休暇制度を導入し、実際に取得して訓練を受けた従業員がいること |
| 人への投資促進コース | 次のような訓練が対象 ・高度なデジタル知識・技能の習得や、成長分野等での人材育成 ・IT未経験者を即戦力化するOJT&OFF-JT ・サブスクリプション型の研修サービスを利用 ・従業員が自発的に受講、事業主が費用を負担 ・教育訓練のための長期休暇制度や短時間勤務等を導入、実際に取得して訓練を受けた従業員がいる |
| 事業展開等リスキリング支援コース | 新たな事業展開等のために必要な知識や技能の習得(リスキリング)、DXの推進 |
| 事業展開等リスキリング支援コース 建設労働者認定訓練コース | 建設労働者のスキルアップのため、厚労省認定の職業訓練を実施 |
| 建設労働者技能実習コース | 建設労働者のスキルアップのため、実習を実施 |
中でも最も活用しやすいのは、幅広い業種や職種に対応している人材育成支援コースです。幅広い分野の研修やセミナーで活用できます。
建設労働者に特化したコースは、たとえば認定訓練コースであれば足場の組み立てなどの作業主任者、施工管理などに関する訓練が当てはまります。
技能実習コースは、フォークリフトや玉掛けなどの技能講習などに使えます。
2024年度からの主な変更点

2025年度(令和7年4月1日以降)、人材開発支援助成金では次のような見直しが行われています。
- 一部コースの賃金助成額引き上げ
- 有期契約労働者等に対する助成の強化
- 助成金申請手続き・必要書類の簡素化
一部コースの賃金助成額引き上げ
2025年度は、次のコースで賃金助成の金額が引き上げられています。
- 人材育成支援コース
- 人への投資促進コース(長期教育訓練休暇等制度)
- 事業展開等リスキリング支援コース
拡充の対象となるのは、助成金の申請前に労働局に出す「職業訓練実施計画書」や「訓練実施計画届」の提出日が令和7年4月1日以降の場合に限ります。
拡充の内容を、コース別に見ていきましょう。
人材育成支援コース
| 対象 メニュー | 引き上げ前 | 引き上げ後 | ||
|---|---|---|---|---|
| 賃金助成額 | 賃上げ要件を満たす場合 | 賃金助成額 | 賃上げ要件を満たす場合 | |
| 人材育成訓練 | 760円(380円) | 960円(480円) | 800円 (400円) | 1,000円(550円) |
| 認定実習併用職業訓練 | ||||
| 有期実習型訓練 | ||||
賃上げ要件を満たす場合とは、次のいずれかに該当する場合を指します。
- 訓練受講後の賃金が、訓練実施前と比べて5%以上アップしている
- 資格等手当の支払いを就業規則に規定、手当を含めた賃金が訓練前と比べて3%以上アップしている
人への投資促進コース(長期教育訓練休暇等制度)
| 引き上げ前 | 引き上げ後 | |||
|---|---|---|---|---|
| 通常分の賃金助成額 | 訓練後に賃金を増額した場合 | 通常分の賃金助成額 | 訓練後に賃金を増額した場合 | |
| 中小企業 | 960円 | ― | 1,000円 | ― |
| 大企業 | 760円 | 960円 | 800円 | 1,000円 |
助成額の引き上げは、昨今の賃金上昇を踏まえたものです。これにより、長期的な視点で従業員のスキルアップが支援しやすくなっています。
事業展開等リスキリング支援コース
| 賃金助成額 | ||
|---|---|---|
| 引き上げ前 | 引き上げ後 | |
| 中小企業 | 960円 | 1,000円 |
| 大企業 | 480円 | 500円 |
一部コースの非正規雇用労働者への助成強化

人材育成支援コースでは、有期雇用契約者など正社員以外を対象とする助成メニューが次のように整理され、経費助成率も見直されました。
| 助成メニュー | 対象 | 見直し前 | 見直し後 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 経費助成率 | 賃上げ要件を満たした場合 | 経費助成率 | 賃上げ要件を満たした場合 | ||
| 人材育成訓練 | 有期契約労働者等に訓練を実施 | 60% | 75% | 70% | 85% |
| 正規雇用に転換等した | 70% | 100% | |||
| 有期実習型訓練(※) | 正規雇用への転換等をしなかった | 60% | 75% | ||
| 正規雇用に転換等した | 70% | 100% | 75% | 100% | |
有期契約の従業員に訓練を実施した場合の助成率や、有期実習型訓練を実施した場合の助成率がアップしています。
賃上げ要件を満たす場合とは、次のいずれかに該当する場合を指します。
- 訓練修了後の賃金が、訓練実施前と比べて5%以上アップしている
- 資格等手当の支払いを就業規則に規定、手当を含めた賃金が訓練前と比べて3%以上アップしている
有期実習型訓練については、「実施はしたが結果として正社員化に至らなかった」という場合もあるでしょう。
その場合でも、一定の要件を満たせば「人材育成訓練」(正規雇用に転換した場合)の助成対象となる可能性があります。
助成金申請手続き・必要書類の簡素化

2025年度の人材開発支援助成金は、申請の手続きが一部簡素化されています。手間が省ける部分もありますが、注意点もあります。
簡素化の内容
- 申請様式の共通化・記載事項の削減
- 添付書類の整理・統合
- 自動計算機能の実装
具体的には、変更となったのは「人材育成支援コース」「人への投資コース(長期教育訓練休暇等制度を除く)」「事業展開等リスキリング支援コース」の一部の申請様式です。これまで3コース別々の様式だったのが共通になり、記載事項も減りました。
また、添付書類も一部整理・統合され、何が必要かがわかりやすくなっています。さらに、賃金助成や経費助成の内訳、OFF-JT実施状況報告書については、自動計算機能により手間が省けるようになっています。
計画書の取り扱い変更
手続きの簡素化に伴い、労働局では事前に計画届の内容を確認することがなくなり、「受付」だけが行われることになりました。
記入もれや書類の添付もれについての確認はありますが、その時点での支給・不支給の判断はされず、支給申請時に一括して行われます。
そのため、計画届を提出したからといって、助成金が必ず支給されるとは限らないことに注意が必要です。
たとえば計画届の内容不備によって対象外となる場合など、以前は事前に知ることができました。しかし変更後は、支給申請後まで知ることができません。
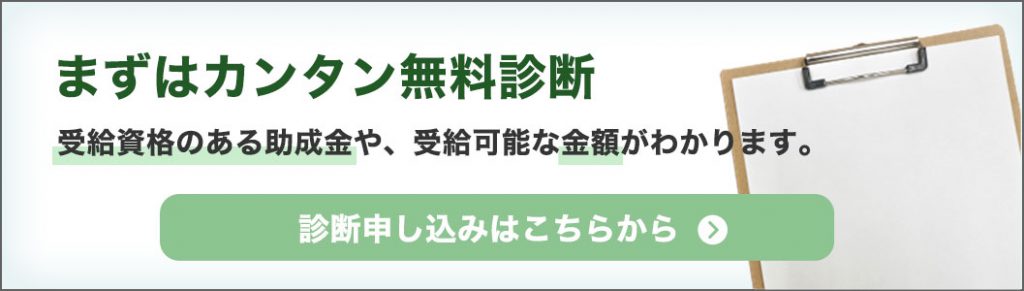
その他の見直しポイント
上記で紹介した以外にも、制度を活用しやすくするため、不正受給を防止するための細かな見直しが行われています。
1つ1つ見ていきましょう。
eラーニング・通信制訓練の要件明確化
支給対象となる訓練の要件が具体化されました。計画書の提出時点で、教育訓練の概要や訓練機関の連絡先を自社のホームページに明確に掲載する必要があります。
これにより、社内に広く公平に訓練の情報を周知すること、制度の透明化を図れます。
また、訓練の進捗管理を行うLMSなどに必要な最低限の情報について、「訓練終了日および訓練の進捗率または進捗状況がわかるもの」と要件化されました。
教育訓練機関の要件強化
教育訓練を実施する機関については、計画提出日までに、教育訓練事業が定款や登記簿の事業目的に記載されていることが必須となりました。ただし、大学などの一部の訓練期間は除きます。
これには、より信頼性の高い教育訓練機関を対象とし、不正目的の一時的ななりすまし等を防ぐ目的があると考えられます。
計画届の提出期間の変更
計画書の提出期限は、これまでは「訓練開始日の1カ月前まで」という決まりでした。2025年度は、「期限」でなく「期間」として「訓練開始日から起算して6か月前から1カ月前の間」となっています。
これにより、より早くから訓練計画を立てられるようになりました。助成金事務局にも、提出が期限直前に集中することを避け、事務負担を軽減したい狙いがあると考えられます。
中小企業かどうかの判定時期変更
中小企業かそうでないかによって、助成率や助成額が異なるコースも多いため、申請者が中小企業かどうかの判断は重要です。
以前はこの判断を計画提出時にしていましたが、2025年度は支給申請を行う時点で判断されることとなりました。
転勤時の対応について
訓練実施期間の途中で、対象となる従業員が他の事業所に転勤となる場合もあるでしょう。
2025年度は、事業所の転勤があったとしても助成対象となります。
テレワークによる訓練での要件緩和
これまでは、OFF-JTやOJTをテレワークで行う場合、会社がテレワーク制度を導入していることがわかる就業規則等の提出が必要でした。
2025年度はこの提出が不要となっています。
人への投資促進コースのOJT指導者の要件緩和
通信情報業でない場合、IT指導者について設けられていた「IT分野の実務経験5年以上」などの要件が廃止されました。
人への投資促進コースの対象労働者の要件緩和
長期教育訓練休暇等制度の対象者について、これまでは「計画届の提出日時点で」6カ月以上被保険者であること、というのが条件でした。
2025年度は、「対象となる従業員が休暇を取得する時点で」6カ月以上の被保険者期間があればよいことになりました。
訓練経費の負担に関する取扱いの明確化

経費の負担については、もともと実質的に減額となる金銭の支払いがある場合は支給対象外とされています。これは、減額等による負担軽減によって「訓練等に要した経費を、支給申請までに事業主が全額を負担すること」という要件を満たさなくなるからです。
令和6年11月5日付けで、この「事業主が全額を負担すること」についての取り扱いが、より明確にされています。厳格化されたと言ってもよいでしょう。特に次の項目に当てはまる場合、支給対象経費とは見なされません。
- 教育訓練機関等から申請事業主への入金額(クーポンやサービスの提供等も含む)と助成金支給額の合計が調整経費と同額の場合
- 教育訓練機関等から、訓練に関する広告宣伝業務(レビューの投稿やインタビューなど)の対価として金銭を受け取った場合
- 教育訓練機関等から、「研修の費用負担は不要」などと提案を受け、提案の前後に「営業協力費」「協賛費」など名目を問わず金銭を受け取った場合
- その他、訓練等に付随して教育訓練機関等と締結した契約に基づき金銭を受け取った場合
「教育訓練機関等」には、教育訓練機関と関連のある法人・個人、業務上の関係がある法人・個人、支払いに関して事業主に金銭等を提供する法人・個人も含まれます。
申請前に押さえておきたい重要ポイント

人材開発助成金の申請には、2025年度からの変更点の他にも注意すべきことがあります。特に次の3つは押さえておきましょう。
訓練費用は「立て替え払い」が必要
助成金は、訓練にかかった経費やその間の賃金を事業主が支払ったと確認した上で支給されます。つまり、後払いで受け取る形です。
助成金をもらい、そのお金で訓練を行うのではなく、まずは支出が先です。資金繰りにも注意が必要ですし、「立て替え」ても、要件を満たさなければ対象外となってしまいます。
ちなみに訓練費用については、事業主による全額負担が必要です。
書類の提出期限は厳守
計画届や支給申請書の提出には、それぞれ期間や期限が設けられています。期間が始まる1日前でも期限を過ぎた1日後でも受け付けされないので要注意です。
特に書類を郵送する場合は、投函や消印でなく労働局に到着した日が期限内でなくてはなりません。スケジュールに余裕をもって、申請手続きを行いましょう。
申請期間中の「解雇」に注意

人材開発支援助成金を含め、雇用関係の助成金については、特定の期間中に会社都合による従業員の解雇や退職勧奨があると、支給対象から外れることがあります。
受給後にそれがわかった場合にも、返還が求められる可能性があります。雇用の安定も図るようにしてください。
訓練実施中の記録や証拠書類は徹底管理
助成金の支給申請には、訓練が職務に必要なものであること、適正に実施されたこと、経緯や賃金の支払いが完了していることなどを証明するたくさんの書類が必要です。
必要となるのは、賃金台帳などのほか、訓練機関と交わした契約書、請求書や領収書、受講のカリキュラムや受講者の名簿、訓練の実施状況を証明するものなど。
すべて記録・保管しておかないと、支給の対象とはなりません。
労働関連の法令遵守は必須
人材開発助成金は、雇用保険を財源とする公的な制度であり、事象主が労働法を遵守していることが大前提です。
そのため、労基署から法令違反を指摘されていたり、賃金の未払いがあったりするような場合には、助成の対象外となります。普段の雇用管理もしっかりしておきましょう。
スムーズな受給には専門家の力も必須
助成金の支給要件や申請手続きには多くの決まりがあります。制度改正や細かなルールの変更、審査の厳格化などもあり、準備不足や認識不足で支給対象外となってしまう可能性も。
準備といっても、本業と並行して進めるのは容易ではありません。負担が大きい上に、要件や必要書類の見落としなども起こりがちです。
スムーズな申請と確実な準備には、助成金に詳しい専門家のサポートが一番の助けとなります。
申請に専門家を活用する3つのメリット

人材開発支援助成金の申請には、助成金の専門家である社会保険労務士に依頼するのがおすすめです。プロの手を借りることで、主に3つの大きなメリットがあります。
確実な準備で受給の可能性が高まる
人材開発支援助成金には、コースごとに細かな要件や必要書類が定められています。すべての支給要件を満たさねば支給はされませんが、完璧な準備には知識や情報も必須です。
助成金の専門家、中でも実際に申請実績が豊富にある社会保険労務士であれば、知識や最新情報はもちろんのこと、要件を満たすコツなども心得ています。そのため、受給の可能性は確実に高まります。
本来の業務に集中できる
助成金の申請には、労働局との慣れないやり取りや、数多くの書類作成、スケジュールの管理や訓練実施に関する細かな記録など、やるべきことが山積みです。そのため、助成金に集中すると、本来の業務が後回しになってしまうことも…。
専門家に依頼することで、手続きにかかる自社の労力や時間は最小限に抑えられます。本来の業務に集中できるので、売上の向上や持続的な経営に支障となることもありません。
不正受給を回避し、社会的信頼を守れる
「全部おまかせで助成金がもらえる」「助成金の受け取りはカンタン」「実質無料」などと嘘の宣伝文句で助成金申請を請け負うコンサルティング会社や教育訓練機関があることに注意が必要です。
厚労省は、近年増えた不正受給に対し、厳しい姿勢を見せています。要件の明確化、審査の厳格化のほか、支給後の立ち入り検査なども行われています。
不正受給が発覚した場合には、会社名や事業主名が公表され、助成金の返還・延滞金の支払いを求められます。会社の社会的信頼を守るためにも、信頼できる適正な専門家に依頼しましょう。
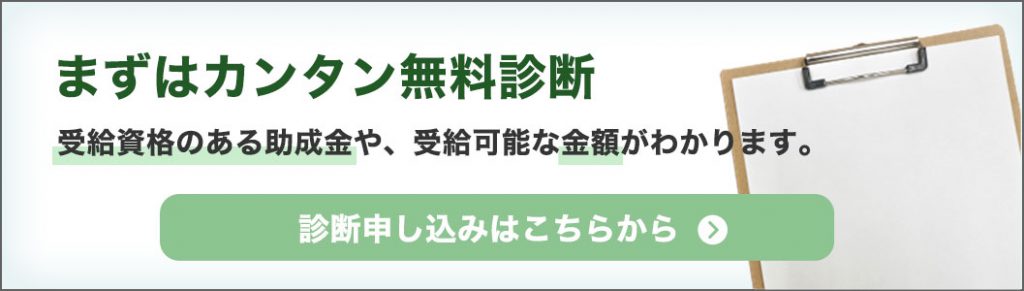
2025年の人材開発支援助成金もBricks&UKにおまかせ

2025年の人材開発支援助成金は、主に非正規労働者への教育訓練や正社員化を促進すべく、助成内容の拡充や制度の変更が行われています。また、提出書類や手続きの簡素化が行われているため、より使いやすくなっていると言っていいでしょう。
とはいえ、要件を満たし、必要書類を完璧に揃えるのは容易でありません。忙しい業務の片手間にできるものではないため、専門家への相談を強くおすすめします。
当サイトを運営する「社会保険労務士法人Bricks&UK」は、助成金の制度にも精通し、多数の申請実績もあります。就業規則の整備・改定など、必要な準備からサポートしますので、まずはお気軽にご相談ください。









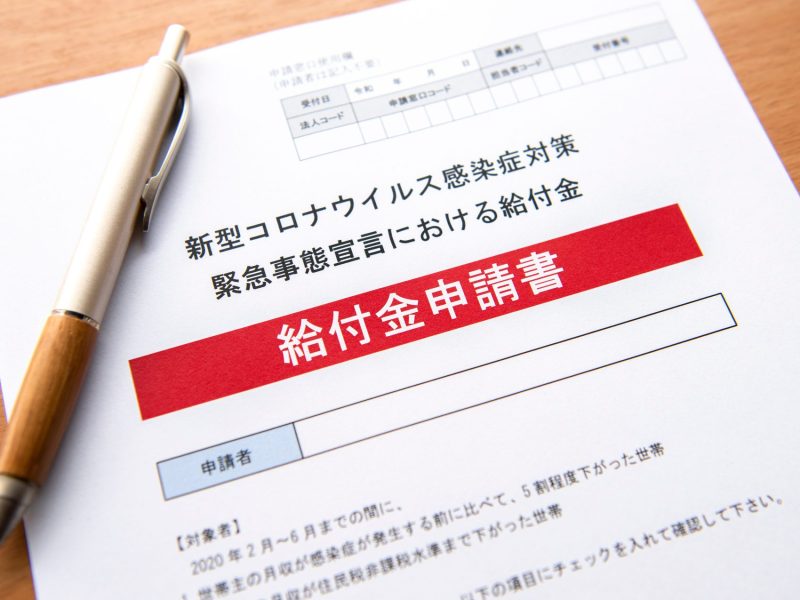


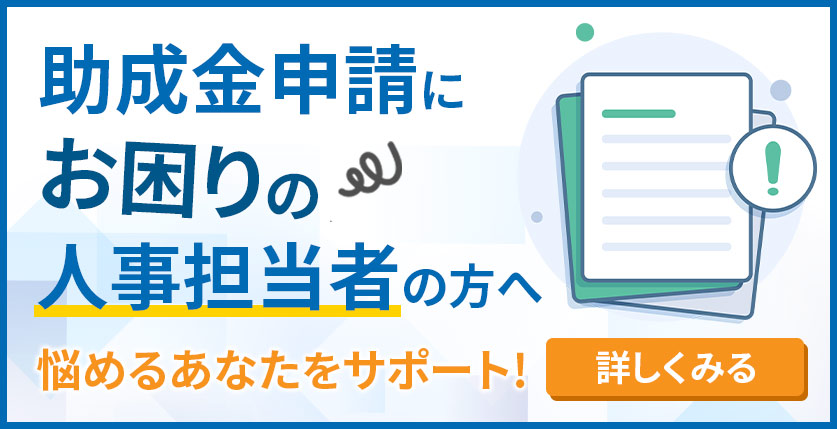
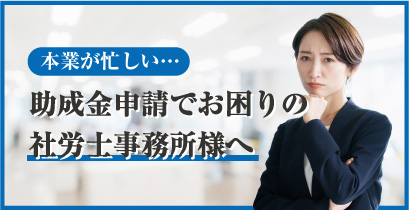
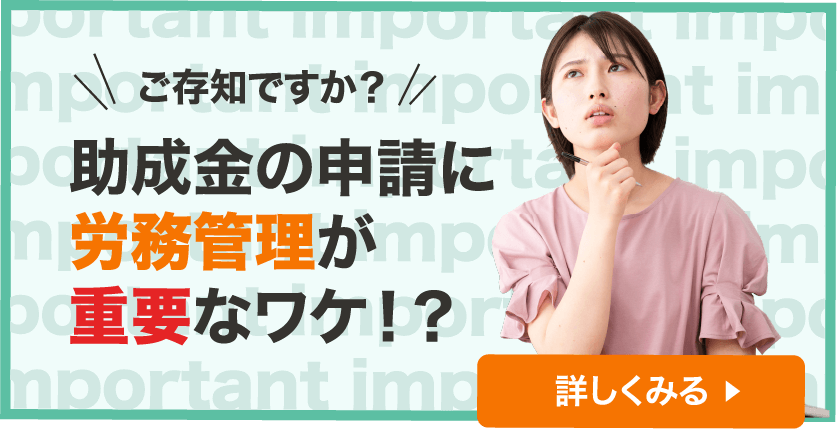
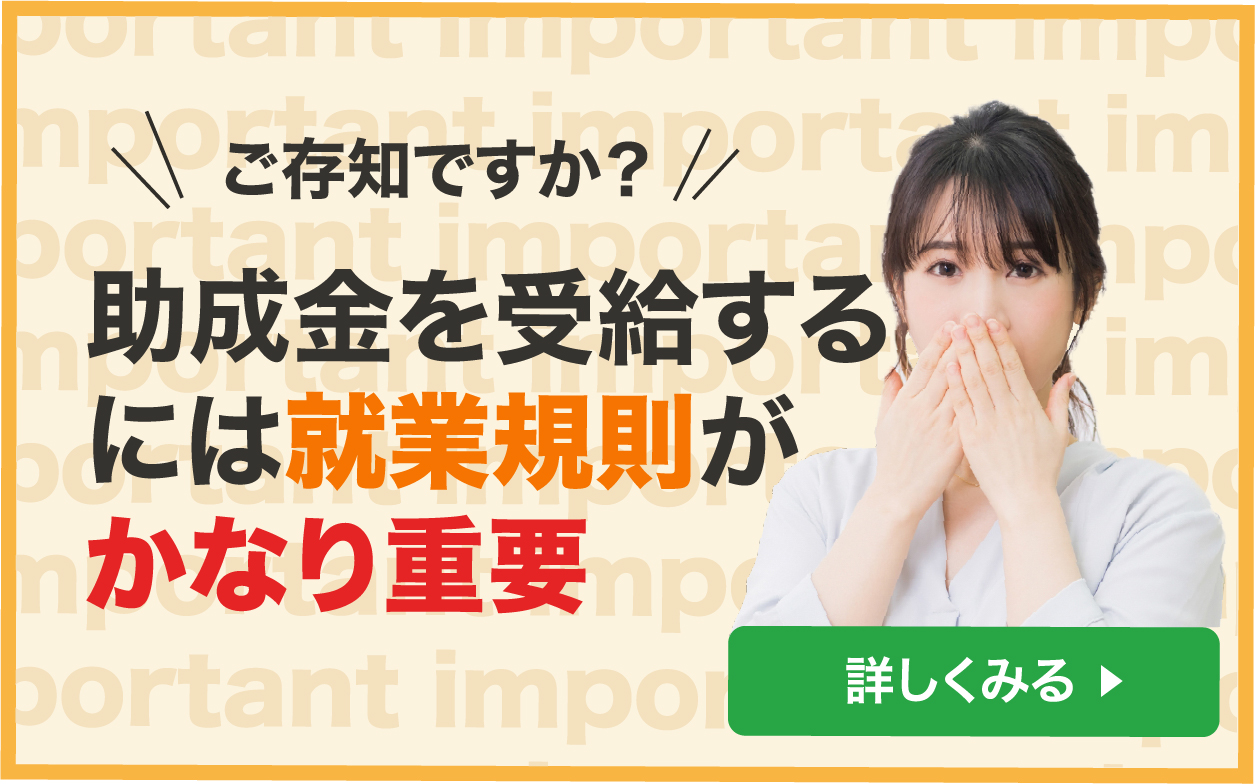

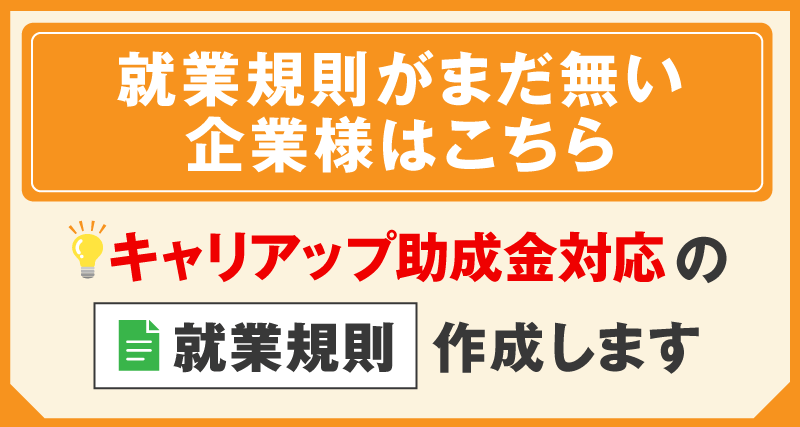
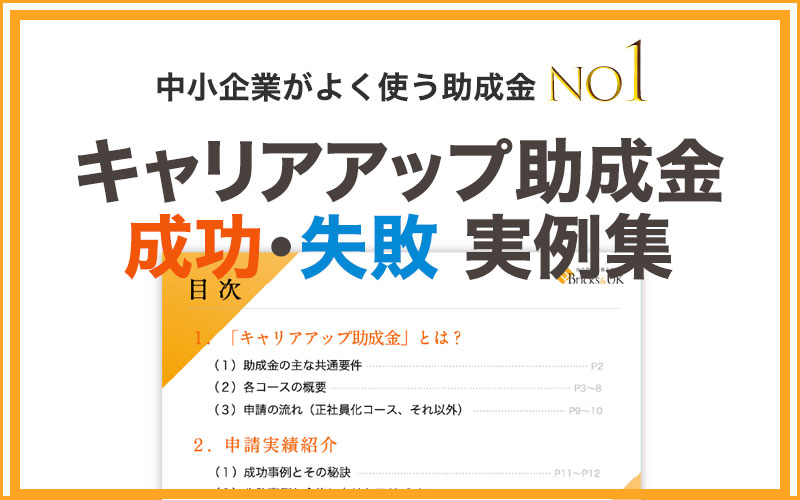


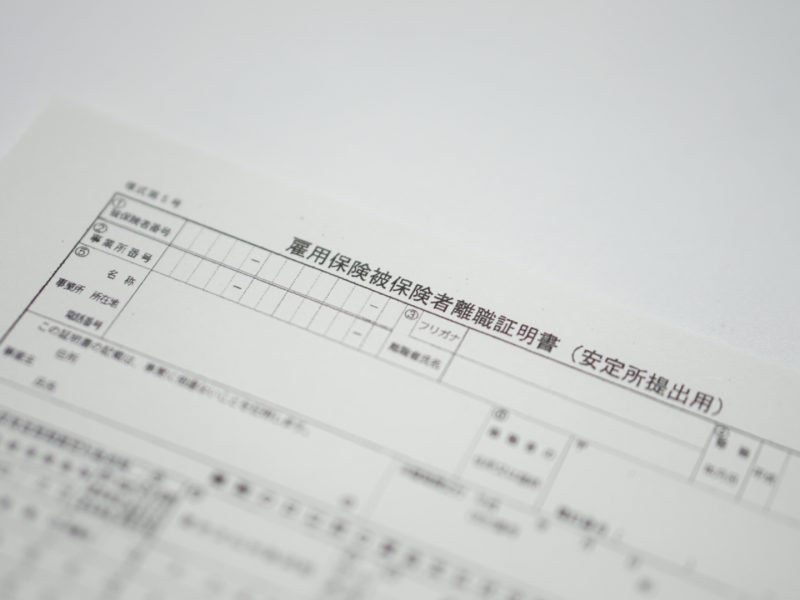

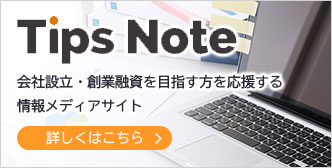


監修者からのコメント 人材開発支援助成金は、訓練時間中の人件費が補助されるというメリットに加え、外部機関を活用することで「教える側の人員を社内で確保する必要がない」という利点もあります。
「従業員に身につけてほしいスキルはあるものの、社内に教えられる人材がいない」「研修のクオリティを一定に保ちたい」といった場合には、本助成金を活用して費用の補助を受けつつ、外部機関を利用して教育訓練を実施することをおすすめします。
ぜひ、社内の教育体制の整備や人材育成の一環としてご活用ください。