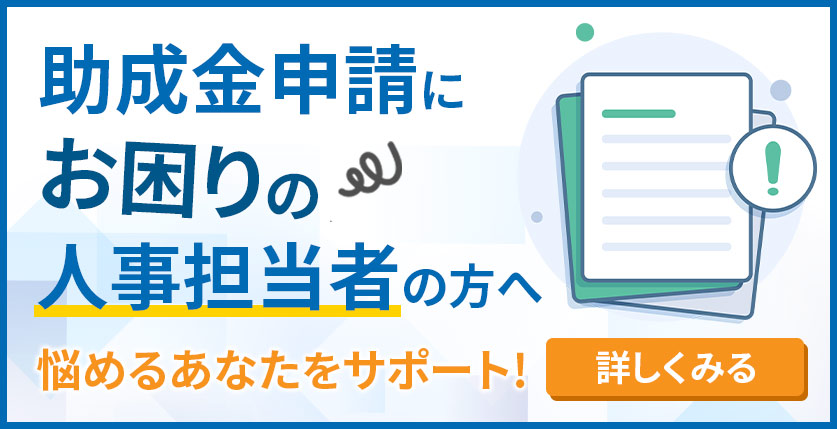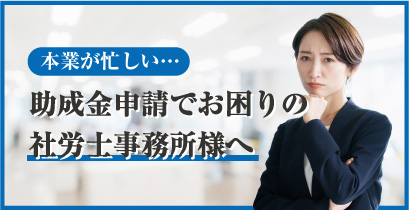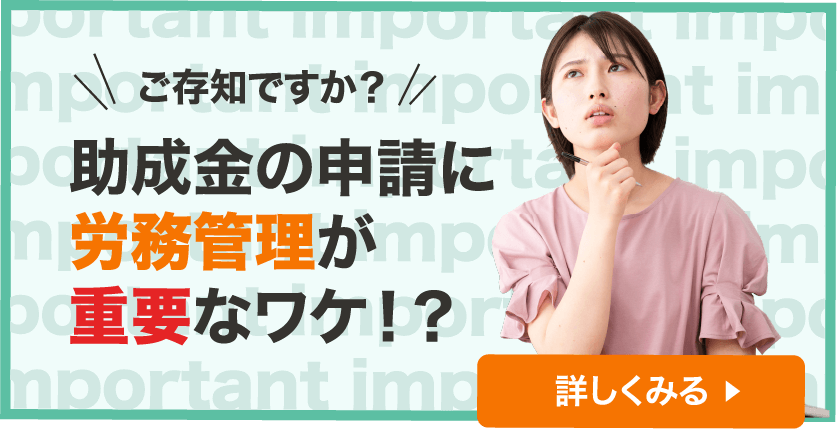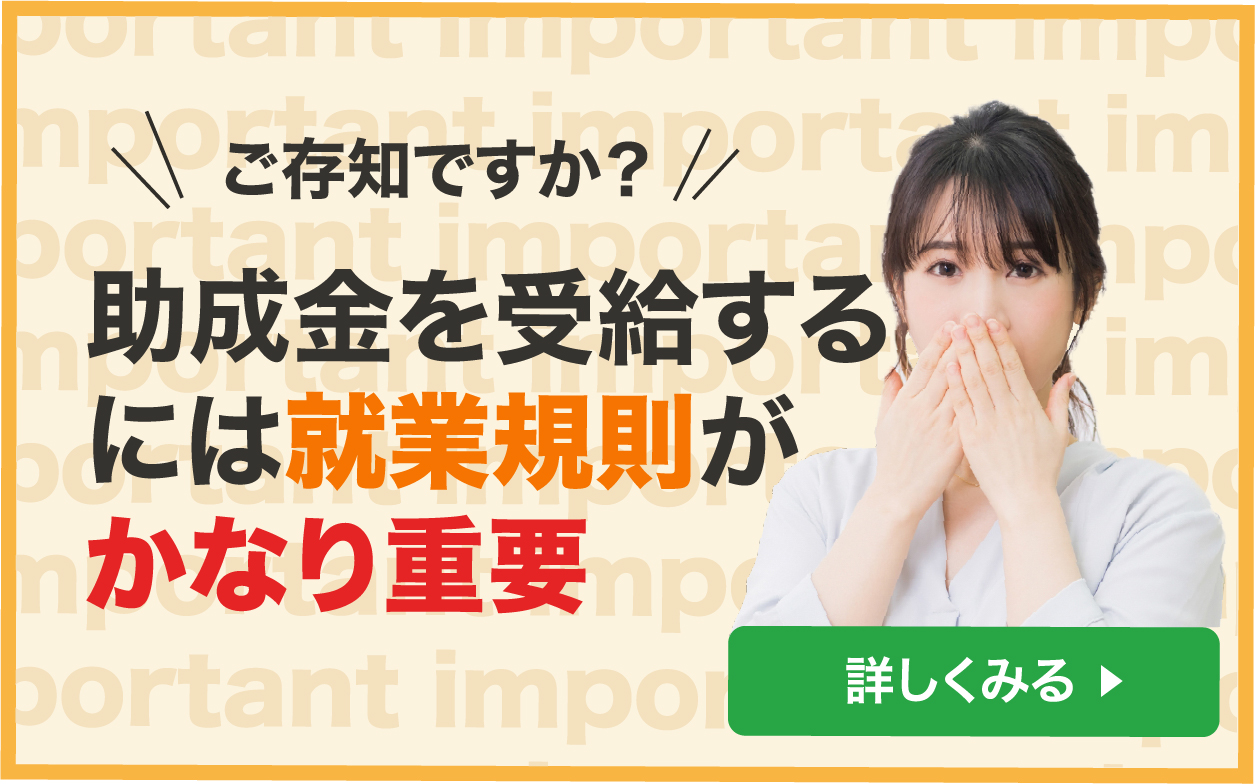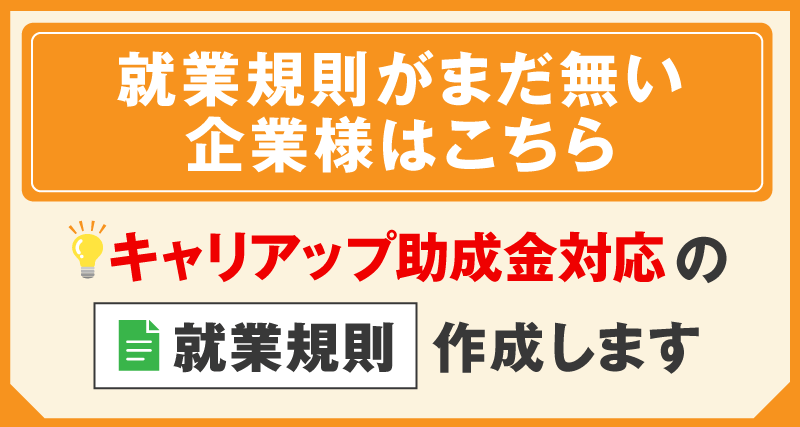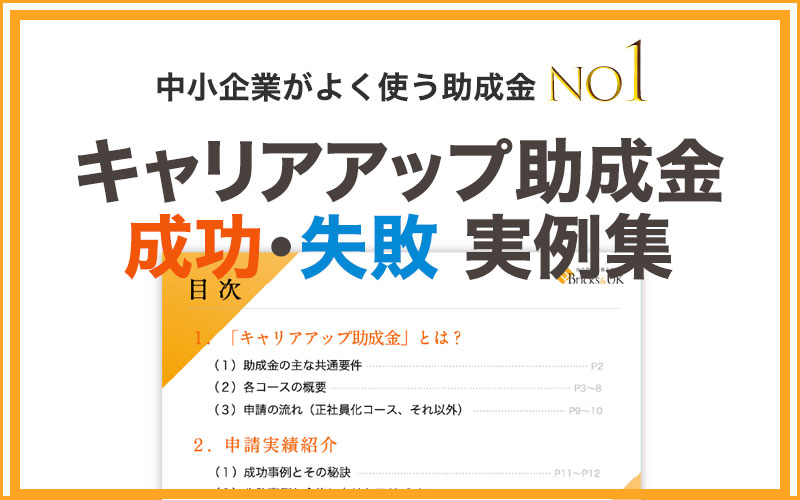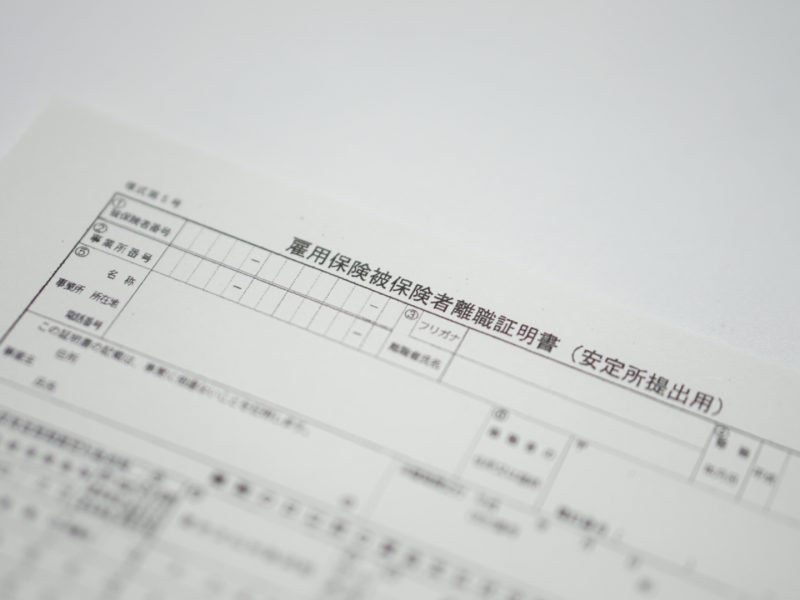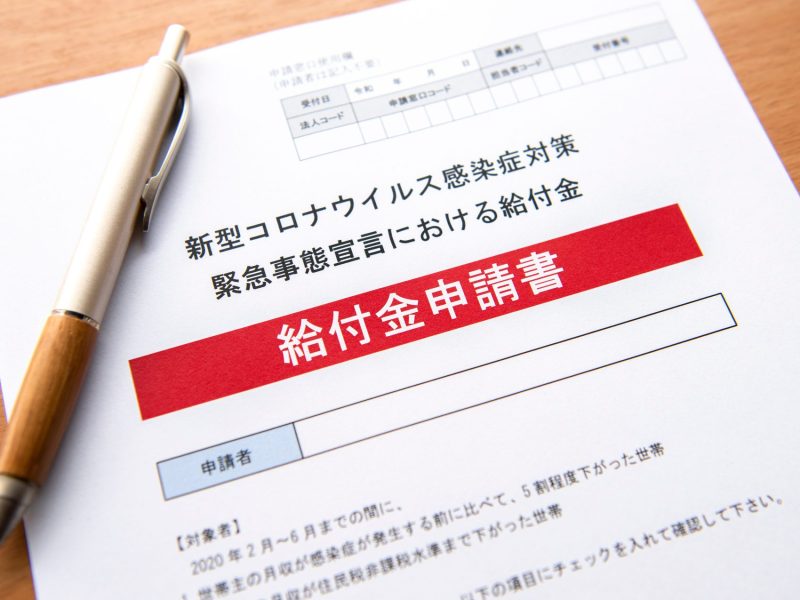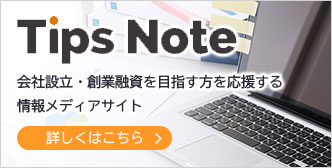業務効率化やインボイス制度への対応など、中小企業の課題解決を支援するIT導入補助金。2025年のIT導入補助金は、3月31日に交付申請の受付が始まっています。
補助額は最大450万円、補助率は申請枠や従業員規模などによっても異なりますが、2分の1~5分の4となっています。
この記事では、IT導入補助金2025の制度の概要や、5つの申請枠の補助内容、申請の流れやスケジュールなどについて解説します。
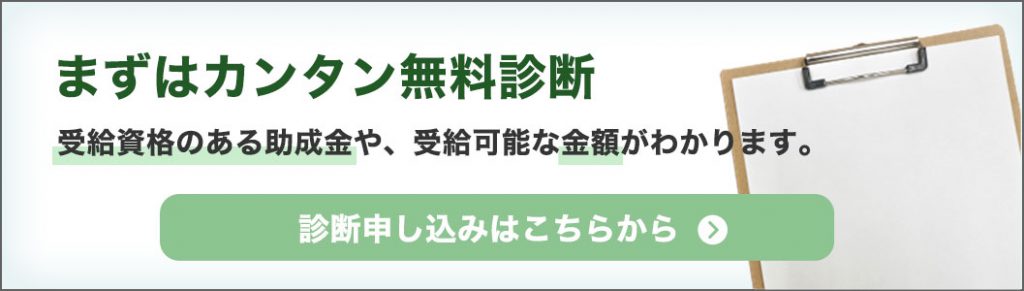
目次
IT導入補助金2025の全体像を把握

まずは制度内容を大まかに把握しておきましょう。
IT導入補助金とは
IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者がITツールの導入にかかった費用を一部補助してくれる制度です。
ただし、生産性向上のための導入であることが条件で、導入するツールもあらかじめ補助金の事務局に登録されたものでなくてはなりません。
導入には、IT導入支援事業者(ITベンダーなど)によるサポートを受けることも必須です。
申請対象となる法人・個人
IT導入補助金を申請できるのは、次の要件を満たす事業主です。法人だけでなく、個人事業主も含みます。
- 中小企業基本法に基づく中小企業・小規模事業者
- 補助金の対象経費を全額自己負担できる事業者
- 生産性向上計画にもとづき、経営改善を目指す事業者
これ以外に、申請枠などによって異なる要件もあります。それについてはこの後の章で説明します。
5つの申請枠・申請類型
IT導入補助金2025には、次の5つの申請枠・申請類型があります。
| 申請枠・申請類型 | 対象 |
|---|---|
| 通常枠 | 在庫管理システムや決済ソフトなど、事業のデジタル化を目的としたシステム・ソフトウェアの導入 |
| インボイス枠 (インボイス対応類型) | インボイス制度に対応した会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、パソコン・ハードウェア等の導入 |
| インボイス枠 (電子取引類型) | インボイス制度に対応した受発注システムを商流単位で導入 |
| セキュリティ対策 推進枠 | サイバー攻撃の増加に伴う潜在的リスクに対処するネットワーク監視システムなどの導入 |
| 複数社連携 IT導入枠 | 複数の中小企業などが連携し、データ分析システムなどを用いて地域DXや生産性向上を図る取り組み |
この後、それぞれの申請枠・類型の補助内容を説明していきます。
通常枠の補助内容

通常枠では、生産性の向上に関する自社の課題やニーズに合うITツールを導入する際の、費用の一部が補助されます。
ITツールの要件
導入するITツールにも条件があります。次のうち1つ以上の業務プロセスを持つソフトウェアでなくてはなりません。
| 種別 | プロセス | |
|---|---|---|
| 業務プロセス | 共通プロセス | (P1)顧客対応・販売支援 |
| (P2)決済・債権債務・資金回収管理 | ||
| (P3)供給・在庫・物流 | ||
| (P4)会計・財務・経営 | ||
| (P5)総務・人事・給与・教育訓練・法務・情シス・統合業務 | ||
| 業務特化型プロセス | (P6)その他業務固有のプロセス | |
| 汎用プロセス | (P7)汎用・自動化・分析ツール ※業務プロセスに付随せず、業種や業務を限定しない専用ソフトウェアで、生産性向上につながるもの | |
ただし汎用プロセスのみでは申請できません。他の業務プロセスとの併用が必須です。
補助対象となる費用
【ソフトウェア(必須)】
ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)
+
【オプション】
・機能拡張 ・データ連携ツール ・セキュリティ
+
【役務】
・導入コンサルティング・活用コンサルティング ・導入設定・マニュアル設定・導入研修 ・保守サポート
補助を受けるには、ソフトウェアの導入が必須です。
補助率・補助額
補助率や補助額は、業務プロセスの数などによって次のとおり異なります。
| 補助率 | 2分の1以内 ※地域別最低賃金+50円以内で3カ月以上雇用する従業員が全体の30%以上の場合:3分の2以内 | |
|---|---|---|
| 補助額 | 1プロセス以上 | 5万円以上150万円未満 |
| 4プロセス以上 | 150万円以上450万円以下 | |
インボイス枠(インボイス対応類型)の補助内容

インボイス対応類型では、インボイス制度に対応するためのITツール、たとえば会計・受発注・決済ソフトやパソコン(PC)、ハードウェアを導入する際に、費用の一部が補助されます。
補助対象となる費用
補助の対象となるのは、次のような費用です。
【ソフトウェア(必須)】
インボイス制度に対応し、かつ「会計」「受発注」「決済」のうち1つ以上の機能があるソフトウェア
+
【オプション】
・機能拡張 ・データ連携ツール ・セキュリティ
+
【役務】
・導入コンサルティング・活用コンサルティング
・導入設定・マニュアル設定・導入研修
・保守サポート
+
【ハードウェア】
PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機
POSレジ・モバイルPOSレジ、券売機
ただし、ハードウェアのみでの申請はできません。また、ハードウェアは、ソフトウェアの使用に必要なものに限ります。
補助率・補助額
会計・受発注・決済ソフトの補助率・補助額は次のとおりです。
| 補助率 | 補助額 |
|---|---|
| 中小企業:4分の3以内 小規模事業者:5分の4以内 | 50万円以下 ※会計・受発注・決済の いずれか1機能以上 |
| 共通:3分の2以内 | 50万円超~350万円以下 ※会計・受発注・決済の いずれか2機能以上 |
補助額50万円超となるには、会計・受発注・決済のうち2機能以上をもつソフトウェアの導入が必須です。
また、この場合の補助率は、50万円以下の部分については上の枠の補助率(4分の3または5分の4以内)となります。
PCやハードウェアなどの導入については、次の補助率・補助額が適用されます。
| 補助対象 | 補助率 | 補助額 |
|---|---|---|
| PC・タブレットなど | 2分の1以内 | 10万円以下 |
| レジ・券売機など | 20万円以下 |
インボイス枠(電子取引類型)の補助内容

この枠は、インボイス対応の受発注ソフトを事業取引の発注者が導入し、受注者側の企業に使わせる場合に対象となります。ほかの枠と同様、経費の一部が補助されます。
補助対象となる費用
次のすべての項目に該当する場合に、補助が受けられます。
- 取引の発注側がITツールを導入し、受注側に与える
- 導入するITツールは、インボイス対応の受発注ソフトである
- 受注側にアカウントを無償で発行できるクラウド型のソフトウェアである
受注側は中小企業・小規模事業者等に限られますが、取引相手の発注側は大企業でも対象となり得ます。
補助率・補助額
補助率は、発注側の企業規模によって、次のように異なります。
| 補助率 | 補助額 |
|---|---|
| 中小企業・小規模事業者等:3分の2以内 上記以外(大企業含む):2分の1以内 | 350万円以下 ※下限なし |
セキュリティ対策推進枠の補助内容

この枠は、サイバーセキュリティ対策を強化するためのITツールを導入する場合に、費用の一部が補助されるものです。
補助対象となる費用
補助対象となるのは、次のすべてに当てはまるITツールの導入です。
- (独)情報処理推進機構(IPA)が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されている
- IT導入補助金事務局に登録済みのIT支援事業者が提供するツールである
- IT導入補助金事務局に登録済みのツールである
「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているだけでは対象とならないことに注意が必要です。
補助率・補助額
セキュリティ対策推進枠の補助率と補助額は次のとおりです。
| 補助率 | 補助額 |
|---|---|
| 小規模事業者:3分の2以内 中小企業:2分の1以内 | 5万円~150万円 |
複数社連携IT導入枠の補助内容

この枠は、次のような複数の企業や事業者が連携してITツールを導入し、地域のDXや生産性の向上を図る場合に対象となります。
- 商店街振興組合や商工会議所など商工団体
- 地域のまちづくりや商業活性化、観光振興を担う中小企業または団体
- 複数の中小企業・小規模事業者がつくるコンソーシアム(共同事業体)
補助対象となる費用
次のような費用の一部が補助されます。
| 基盤導入経費 | 会計・受発注・決済ソフトとそのオプション、役務とその使用に必要なハードウェア(PC、タブレットなど) |
|---|---|
| 消費動向等分析経費 | 異業種間の連携、地域の人流分析、商取引など広範囲のデジタル化に役立つソフトウェアとそのオプション、サービス、ハードウェア (POSシステムや人数計測センサー、データ分析ツールやコンサルティング料など) |
| その他経費 | 参画事業者をとりまとめるための事務費、専門家賃 |
たとえば、商店街にAIカメラを設置して客の流れや属性などを分析し、POSデータ分析システムで店舗ごとの購買データを確認、売れ筋を把握して取扱商品を見直す、などの際に活用できます。
補助率・補助額
補助率や補助額を、経費の種類別に見ていきましょう。
基盤導入経費
補助対象経費のうち、ソフトウェアの導入には次の補助率・補助額が適用されます。
| 補助率 | 補助額 | |
|---|---|---|
| 中小企業:4分の3以内 小規模事業者:5分の4以内 | 50万円以下 × 構成員数 | 3000万円以下 |
| 3分の2以内 | 50万円超~350万円以下 × 構成員数 | |
補助額のうち50万円以下については上の枠の補助率(4分の3または5分の4)、50万円超となる部分は下の枠(3分の2)の補助率です。
ハードウェアについては次のとおりです。
| 補助対象経費 | 補助率 | 補助額 | |
|---|---|---|---|
| PC・タブレットなど | 2分の1以内 | 10万円 × 構成員数 | 3000万円以下 |
| レジ・券売機など | 20万円 × 構成員数 | ||
基盤導入経費と消費動向分析経費の合計で3000万円が上限です。
消費動向等分析経費
データの取得や分析にかかる経費の補助率・補助額は次のとおりです。
| 補助率 | 補助額 | |
|---|---|---|
| 3分の2以内 | 50万円以下 × 構成員数 | 3000万円以下 |
基盤導入経費と合わせて3000万円が上限です。
その他経費
事務費用などその他の経費の補助率・補助額は次のとおりです。
| 補助率 | 補助額 |
|---|---|
| 3分の2以内 | 200万円以下 |
ただし、その他経費の補助上限額は、次のいずれか低い方の金額です。
- 基盤導入経費と消費動向分析経費の合計額の10%に補助率3分の2をかけた額
- 200万円
IT導入補助金2025の申請の流れ

IT導入補助金の申請から交付決定、その後の流れを見ていきましょう。
「複数社連携IT導入枠」については流れが異なるため、この記事では割愛します。補助金の公式サイトにて確認ください。
- 1) 要件など制度内容を理解する
- 2) GビスプライムIDを取得する
- 3) SECURITY ACTION宣言をする
- 4) IT事業者や導入するツールを選ぶ
- 5) 交付申請をする→交付決定を受ける
- 6) ITツールの発注・導入・支払・活用
- 7) 事業実績報告を行う
- 8) 補助金額の確定→承認する
- 9) 事業実施結果を報告する
順に見ていきましょう。
1)要件など制度内容を理解する

まずはIT導入補助金2025の制度内容を十分に理解する必要があります。
対象となる補助の要件や申請の流れ、事業の進め方から締切まで、具体的に確認します。
2)GビスプライムIDを取得する
IT導入補助金は電子申請で行うため、それに必要な「GビズID」の「プライム」という種別のアカウントを取得します。
GビズIDとは、事業者を対象とした共通認証システムで、補助金のほか社会保険など各種の行政サービスの窓口です。アカウントの取得は、政府の「GビズID」公式サイトより行います。
GビズプライムIDの取得には審査があり、審査に2週間ほどかかるため、早めに手続きしておきましょう。
3)SECURITY ACTION宣言をする
「SECURITY ACTION」とは、中小企業などが情報セキュリティ対策に取り組むことを宣言する制度です。「一つ星」か「二つ星」の自己宣言を行います。
宣言を行うとIDが発行されるので、そのIDを補助金申請時に入力します。
自己宣言の完了までは申し込みから2~3日ですが、集中した場合は1週間ほどかかることもあるので注意が必要です。
すでに宣言済みでIDがある場合は、そのIDで申請可能です。
また、「一つ星」でも申請可能ですが、セキュリティ対策推進枠では「二つ星」が加点項目となっています。
「SECURITY ACTION」セキュリティ対策自己宣言|IPA
4)IT事業者や導入するツールを選ぶ

自社の業種や事業規模、抱えている課題を踏まえ、必要なITツールを選びます。ツールの選定には、導入をサポートしてくれる「IT導入支援事業者」に相談する必要もあります。
ITツールやIT導入支援事業者は、補助金事務局のサイトから探しましょう。事務局に登録されていないツールや業者による申請は補助の対象外です。
この時点ではITツールの「選定」までを行います。交付決定前に発注・契約や支払いなどをしてしまうと、補助金は受けられません。
ITツール・IT導入支援事業者検索|IT導入補助金2025 公式サイト
5)交付申請をする→交付決定を受ける
交付申請も、IT導入支援事業者と共同で進めます。まずはITツールについて商談を進め、事業計画を立てます。
その後、支援事業者から補助金事務局に「申請マイページ」への招待を申請、招待を受けたら申請ページに必要情報の入力や書類の添付を行います。
IT導入支援事業者がツールや事業計画に関する必要項目を入力したら、最終確認をして申請します。
事務局が申請内容を審査し、採択されれば「交付決定通知」が届きます。
6)ITツールの発注~支払いを行い、取り組みを開始する
交付決定の通知が届いたら、「補助事業者」として事業を開始します。
「4」で選定したITツールの発注や契約、支払いは、この時点から可能(補助金の対象)になります。
7)事業実績報告を行う

補助事業が完了したら、事業実績報告を作成します。事業実績報告には、ITツールの発注や契約、支払いなどの事実を示す契約書や納品書、領収書なども添付します。
作成した事業実績報告は、IT導入支援事業者に確認してもらいます。
支援事業者側で必要な入力をしてもらった後、最終確認を行い、事務局に提出します。
8)補助金額の確定→承認する
実績報告の内容に基づいて事務局の確定検査が行われ、補助金額が決定します。結果はマイページに送られます。
検査結果や補助金額は、IT導入支援事業者が確認します。内容に間違いがなければ、申請者が承認します。
承認をしないと、補助金は交付されません。
9) 事業実施結果報告を行う
補助事業の終了後、生産性の向上や賃上げなどについて、枠ごとに決められた期限内に「事業実施効果報告」を提出しなくてはなりません。
この効果報告も、提出前にIT導入支援事業者に確認してもらう必要があります。
期限までに報告がない場合や、目標を達成しなかった場合には、補助金の返還義務が発生する場合もあるので注意が必要です。
IT導入補助金2025のスケジュール
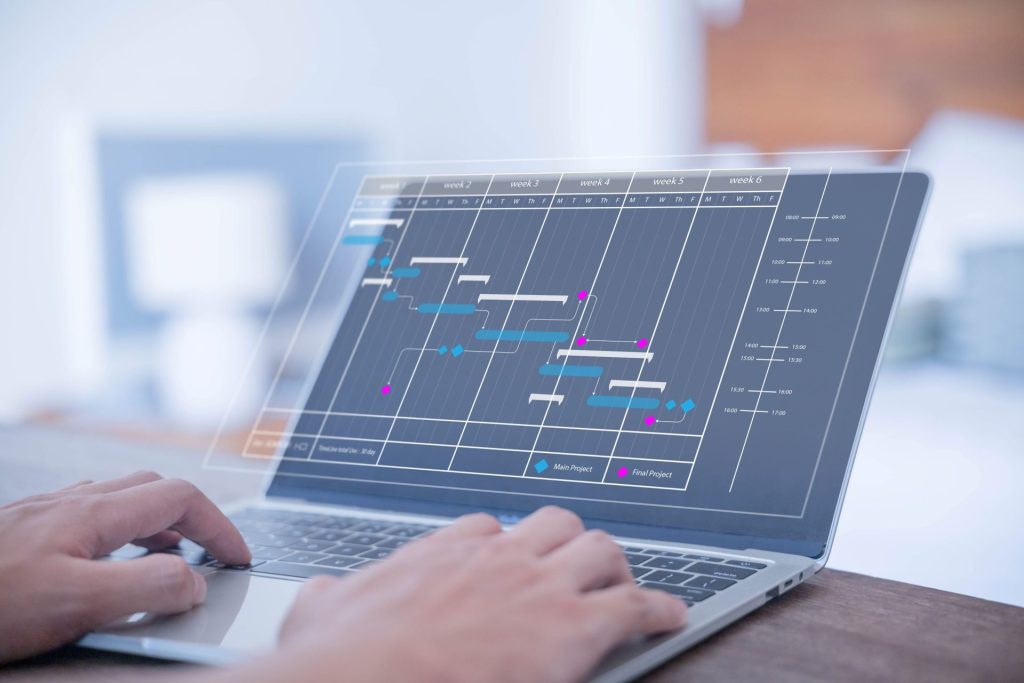
2025年のIT導入補助金について、公式サイトで公表されているスケジュールを紹介します。
まず、交付申請期間については、すでに始まっています。
| 募集期間 | 2025年3月31日(月)受付開始 |
|---|
執筆時点で、複数社連携IT導入枠以外は3次までのスケジュールが出ています。
通常枠・インボイス枠・セキュリティ対策推進枠
1次締切分
| 締切日 | 2025年5月12日(月) |
|---|---|
| 交付決定日 | 2025年6月18日(水) |
| 事業実施期間 | 交付決定~ 2025年12月26日(金)17時 |
| 事業実績報告期限 | 2025年12月26日(金) |
2次締切分
| 締切日 | 2025年6月16日(月) |
|---|---|
| 交付決定日 | 2025年7月24日(水) |
| 事業実施期間 | 交付決定~ 2026年1月30日(金)17時 |
| 事業実績報告期限 | 2026年1月30日(金) |
3次締切分
| 締切日 | 2025年6月16日(月) |
|---|---|
| 交付決定日 | 2025年7月24日(水) |
| 事業実施期間 | 交付決定~ 2026年1月30日(金)17時 |
| 事業実績報告期限 | 2026年1月30日(金) |
複数社連携IT導入枠
複数社連携IT導入枠については、1次のみ公表されています。他の申請枠の第2次と同じスケジュールです。
| 締切日 | 2025年6月16日(月) |
|---|---|
| 交付決定日 | 2025年7月24日(水) |
| 事業実施期間 | 交付決定~ 2026年1月30日(金)17時 |
| 事業実績報告期限 | 2026年1月30日(金) |
スケジュールは確定次第更新される予定のため、公式サイトでも必ず確認してください。
IT導入補助金2025の申請のポイント

IT導入補助金は、2024年の通常枠の採択率が約75%と高めではありますが、注意すべきポイントもあります。最後に見ておきましょう。
交付決定後の義務と手続きも理解する
IT導入補助金のゴールは、交付決定でないことに注意が必要です。
ITツールの導入や支払いの完了、事業の実績報告、効果測定など、段階を踏んで行う必要があるほか、怠ると補助金を返還しなくてはいけなくなる恐れもあります。
まずは、申請前に手続きの流れをしっかりと把握しましょう。補助金が交付されたからこれで終わりと油断せず、最後まで義務を果たしてください。
不正受給を指南する業者に注意
「確実に受給できる」「簡単にもらえる」などとうたい、補助金申請を促す業者には注意してください。補助の対象外と知りながら高額な手数料を請求したり、虚偽の内容で不正申請をされたりするケースがあります。
複数の補助金・助成金制度で不正受給が横行したため、審査は厳正に行われています。発覚すれば法的措置の対象にもなり得ますし、公表されれば社会的な信用も失います。
補助金・助成金に詳しい専門家に頼る
適正な方法で自社に合った補助金を受け取るには、信頼できる専門家にサポートしてもらうのが一番の方法です。補助金で頼れる専門家には、中小企業診断士や行政書士、税理士などがいます。
中でも、補助金申請の実績が豊富な専門家を選ぶのがポイントです。書類の不備などミスによる不採択を防ぎ、これまでの採択結果や傾向なども踏まえたアドバイスをもらえるでしょう。
IT導入補助金では、採択の可能性を高める加点項目があり、専門家のサポートで受給の可能性を高めることができます。
さらに他の補助金・助成金との併給の可能性も図れ、最適な制度が活用できます。
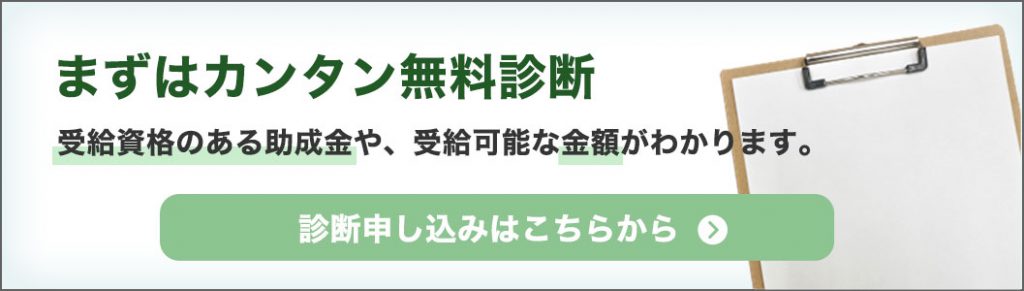
IT補助金の申請もBricks&UKにおまかせ

IT導入補助金を受け取るには、IT導入支援事業者とツールを選び、事業計画を立てて事業を遂行するなど、さまざまな手続きを経る必要があります。
まずは自社がIT補助金の対象となり得るのか、気になる場合は専門家に相談してみましょう。
当社「社会保険労務士事務所Bricks&UK」は、グループ会社である「税理士法人Bricks&UK」と提携し、IT導入補助金の申請サポートも行っています。
自社の課題解決に使える補助金や助成金はないか、といったご相談も承っています。ぜひお気軽にご相談ください。