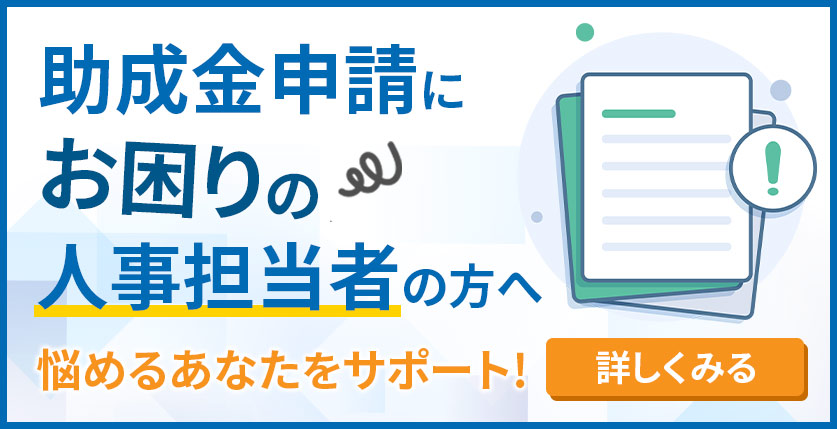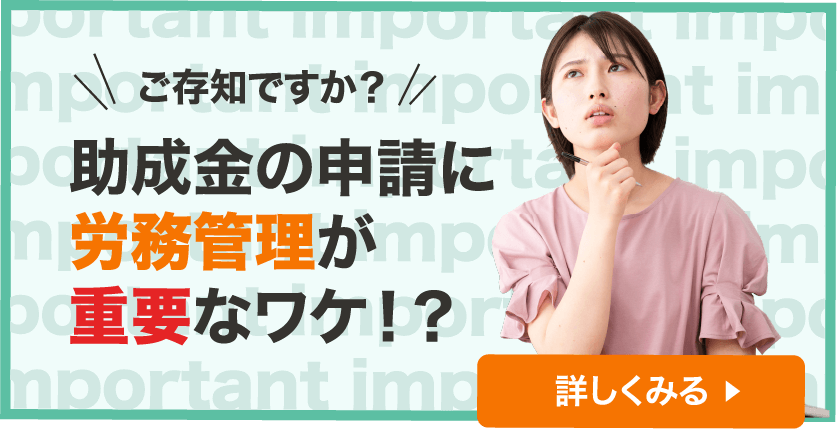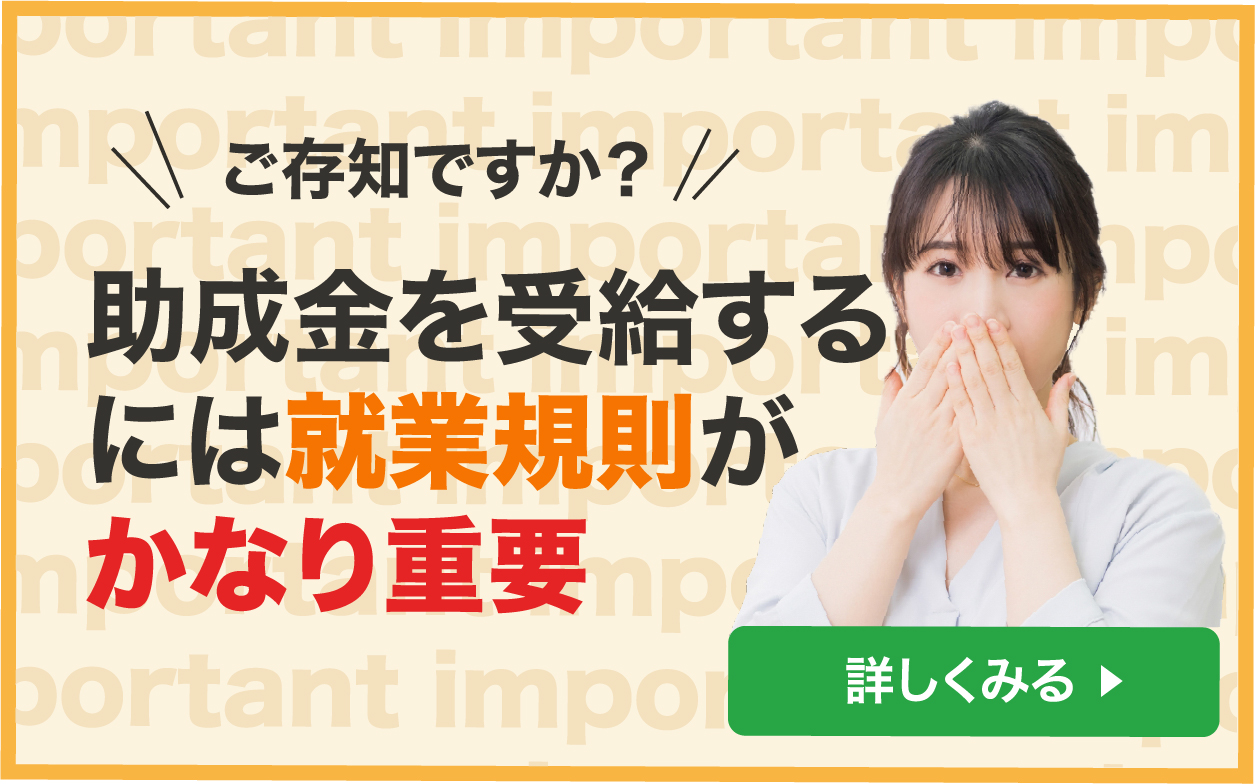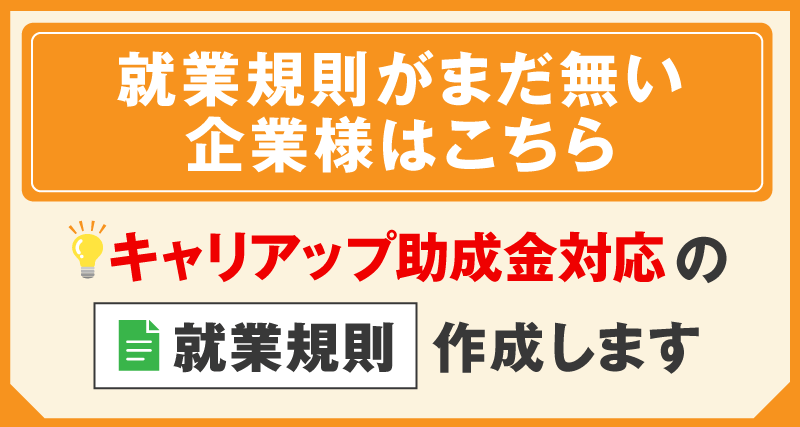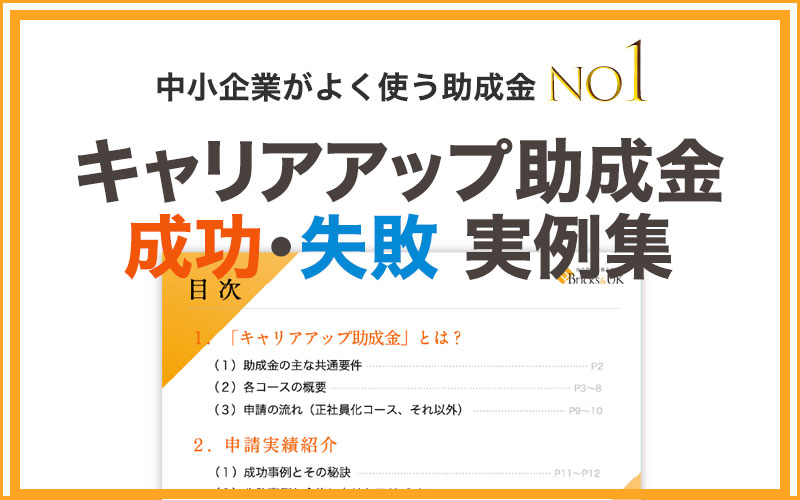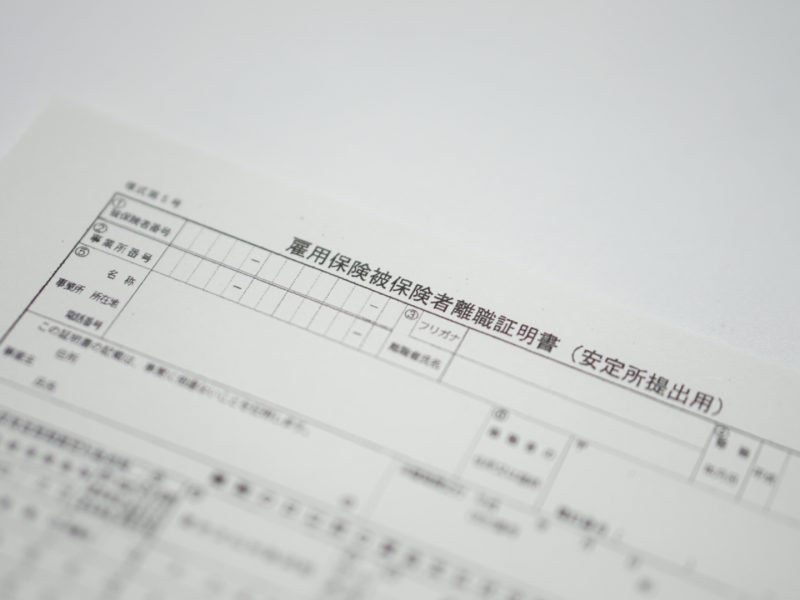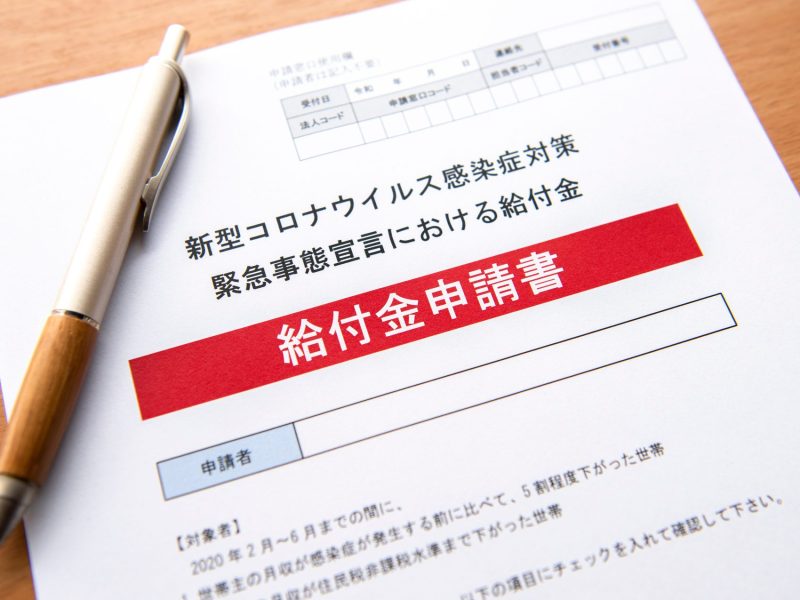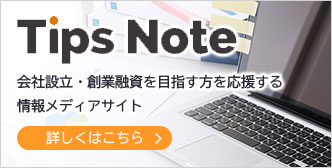雇用調整助成金の不正受給の事例紹介
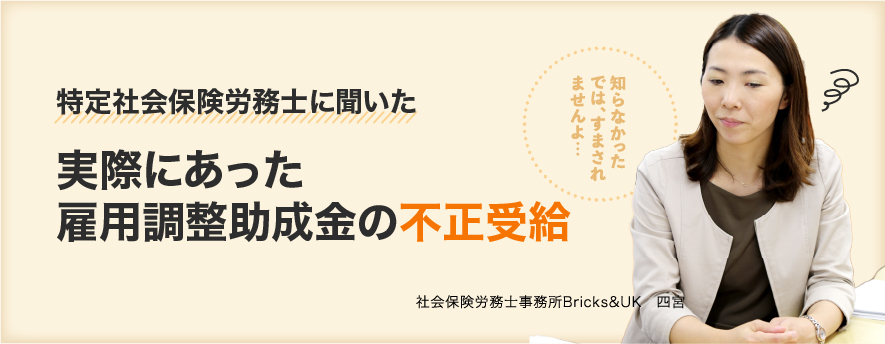
新型コロナウイルスの蔓延で事業活動に支障をきたした事業主が、従業員を解雇せず休業させるなどした場合に受給できる、雇用調整助成金のいわゆるコロナ特例。数多くの企業で活用されている一方、不正受給も多いことが問題となっています。
今回は、不正受給にはどんな事例があるのか、どのように発覚するのかなどについて、当サイトの監修者でもある特定社会保険労務士 四宮寛子さんに話を聞きました。
ランダムな調査が増加、発覚する不正受給
助成金の不正受給が増えている、というのは現場でも感じていますか?
はい、以前よりかなり増えたと感じています。雇用調整助成金の申請は令和2年の夏あたりがピークでしたが、そのころ不正受給の話はほとんどありませんでした。
ただ、おそらく当時は労働局も、申請されたものをまずはすべて受理することを優先していたのだと思います。申請から受給までの期間もとても短かかったですし。
それが今年の5月6月あたりで申請の件数が落ち着いてきたため、これまでの申請について、疑わしいかどうかに関係なくランダムに調査が入ってきている。以前よりも、調査自体が増えているのだと思います。
不正受給はどのように発覚するんですか?
労働局が事業所に立ち入り調査をして、労働者名簿や賃金台帳、出勤簿といった労働関係の書類などを確認します。申請内容に虚偽などがあれば、そこで発覚します。
例えば、休業した従業員として、実際にはいない人物の名前が記入してあったとします。その人が実際に在籍しているなら、事業場には何らかの証拠、労働の実態がわかるものがあるはずです。でも、調査で何も資料が見つからなければ、「こんな人いませんよね?」とわかってしまうわけです。
不正受給って、どういったケースがあるんでしょうか
休業の水増しや休業手当の架空支払い、退職者を在職に見せかけるといったものが多く報告されています。
もっと大胆な不正の事例では、会社を経営しているように見せかけ、さらに従業員を休業させたことにして助成金を申請…つまりすべてが架空だった、というケースもあります。
調査では決算書や元帳なども細かくチェック
それは、調査が入って初めてわかるということなんでしょうか
はい、そうです。いわゆる内部告発のようなケースは別として、過去に助成金を支給した事業所に対して、申請に問題がなかったか、支給すべきでないものを支給していないかを確認するために調査が入るんです。そこで不正だったと発覚する事例が増えています。
調査では、労働関係の書類はもちろん、決算書とか元帳、経費の領収書など細かい帳票類の提出も求められます。その1つ1つをチェックして、お金の流れで事業活動全体を把握するというような調査もされているんです。
そのほかには、休業中の従業員の活動記録のような資料も細かく見られますね。
たとえばあるメーカーでは、プロジェクトの管理表の中に、メンバーとして休業中の社員の名前が小さく入っていた。それで、「休業している人の名前がなぜ入っているのか」と質問されたそうです。
そんなところまで見られるんですね。
聞き取り調査みたいなのもあるんですか?
はい、聞き取り調査もされます。たとえば今でも全休業しているなら、その理由を聞かれたり。個別なら「この人はなぜずっと休んでいるのか」と聞かれたりもします。
もちろん、本当にコロナのせいで仕事がなく、やむを得ず休業していることが証明できれば、助成金の受給に何の問題もありません。
たとえば工場や飲食店なら、そこに行けば誰が出勤しているのかはすぐにわかりますよね。実際に休業しているかどうか、そうやって確認されたりもします。
意外なところから架空の休業が発覚
具体的な不正受給の例にはどんなものがありますか?
全社休業としていた期間中に、一人の従業員が仕事をしていたことがわかり、不正受給と見なされた事例があります。
OA機械メンテナンスの会社だったのですが、休業中にお客さんから電話で緊急の依頼が入り、修理に出かけたということでした。
行かなければそのお客さんの仕事が止まってしまうので、その対応自体は仕方のないことだと思います。ただ、その日は休業したとは言えないので、申請時の書類から除いておくべきでした。
それはどうやって発覚したんですか?
駐車場の領収書からです。調査で休業期間中の日付の領収書が見つかり、「なぜ休業した日の経費精算がされているのか」と。
それが、お客さんのところに行ったときに社用車を止めた駐車場のものだったと判明し、休業ではなかったということで不正受給と認定されてしまったんです。
上司が知らないところで休みの日に自主的に社員が出勤するって、どの会社でもありそうです
そうですね。でも、労働局の監査は厳しいものです。事業主には当然、従業員の勤務状況を把握し、管理する義務があります。知らなかったでは済まされません。
その一件で、不正受給となった部分だけでなく、受け取った助成金を全額返還しなくてはならなくなりました。しかも、ただ返還するだけではなく、延滞金が加算されて金額は2割増になるんです。
全額返還に延滞金も…厳しいんですね
それだけではないんです。不正受給となると、役員は「不正に関与した役員」と見なされ、その役員がいる会社はその後5年間、雇調金以外の助成金も一切が支給停止になります。
たとえばその役員が別の法人格の役員もしていた場合、その別の会社が助成金を申請したことがなくても、5年間は支給停止です。
「まさかこんなことになるとは」助成金の申請を後悔する人も
不正受給と判断されたら、その後や周りにも影響があるんですね
その通りです。労働局の調査が入り、「まさかこんなことになるとは」「認識が甘かった」という事業主の方もいます。
ご相談だけだったのですが、不正受給に認定されたらどうなるのかとかなり心配されていました。受給額が大きかったので、不正受給となればかなりの額を返すことになります。それだけならまだしも、企業名を公表されたら信用を失い、事業の存続も危うくなるかもしれない、と。
この方に限らず、そこまで厳しく見られるとは考えていなかった事業主の方も多いと思います。
故意ではない不正受給というのも多いんでしょうか
申請書の記載に誤りがあったケースはいくつかありました。
助成金の申請作業は、その会社の総務や労務といった事務部門が行う会社も多いので、情報共有という面で各部門の連携不足が起こりがちなんです。
現場では実際には就労した日もあったのに、事務サイドには知らされず、「休業の指示が出ているから出勤しているはずがない」と休業で書類を作成し、結果的に実態とは違う内容の申告をしてしまったりとか。
ほかにも、同じ人を2回申請してしまった、書類の転記ミスで10日の休業を20日にして申請してしまった、といった、本当に単純なミスも多いです。
「退職届の提出日」と「退職日」の間違い
申請の際、間違いやすい部分もあるんですか?
ええ。多いのは、例えば退職予定の従業員がいる場合の申請です。
退職する人がいる場合、その人については退職届を出した日までしか助成金の対象者になりません。退職日ではなく、退職届を出した日までしかカウントできないのですが、退職するまでの日数と間違えてしまうんです。結果として、日数を多く申請してしまう。
それもどの会社でも起きそうな事例ですね。
見つかってないケースもまだたくさんありそうな…
わかりにくい部分では、労働法への理解が不十分で、助成金の要件を満たさないというケースもありますね。
労基法に違反する申請ももちろんNG
一時期、小規模事業主向けの雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金には、申請した額が100%そのまま助成される特例措置がありました。
通常、1カ月の出勤日は、休日を除いて20日ほどです。1カ月休業したなら、休業日は20日間です。でもある事業主の方は、「うちは休みが週1回だから、休業日は25日分になる」と。
しかも1日の労働時間が10時間というシフトのため、25日×10時間=250時間分の給料を社員に支払い、それをそのまま申請すると言われました。
それでも申請は通るんですか?
当事務所が申請に関わったケースでは、法の範囲内で申請しています。でも、社労士を介さずご自身で申請されたりして受給したケースもあるかもしれません。
会社が従業員を働かせて、その労働時間分の給与を保障するのは当然のことです。でも、労働時間は法で上限が決まっていますし、国にはあくまで法定労働時間の枠内でしか請求すべきでないと思っています。
お客さんには、1日8時間を超えるようなシフトはダメですとはっきりお伝えして、8時間以上の部分は切り捨てて申請させていただきました。
故意なのか過失なのかが微妙なケースですね
そうですね。知っていて申請すればもちろん故意です。でも、善意というか「頑張って働いてくれた分だけしっかり保障してあげたい」という気持ちで法定外労働時間分の給料を支払い、そのままの額で助成金を申請することもあり得ると思います。
これは一例ですが、法の基準をわかっていない事業主の方は他にもたくさんいると思います。ただ、これも知らなかったでは済まされません。法に反するものはやはり不正受給になると考えています。
ほかにはどういった事例がありますか?
要件に合わない申請、つまり要件を満たしていないのに申請してしまうケースというのもありますね。これも結果的に不正受給になると考えています。
雇用調整助成金は、まず会社のお金で休業手当を支払い、その後に受け取るものです。でも、「本当にお金がないから、助成金をもらってから払おうと思った」と、まだ支払っていない休業手当を払った形にして申請したケースもあるんです。
たとえば、休業手当を200万円払ったという内容の書類を作って提出して、支給された200万円から休業手当を支払った、というようなことです。
こういったケースも、不正受給と認定されています。助成金には満たすべき要件があるので、それを満たさず助成金を受け取ろうとした時点でもうダメなんです。
計画休業しているのに長時間残業?
申請書を見た時点で「あれ?」と思うケースもありますか?
たまに気になるのは、全社的な計画休業をずっと続けているのに、個々の残業時間がかなり多くなっているようなケースですね。
その会社では、月に二度の計画休業を継続して行っている、それなのに、人によっては月40~50時間の残業をしている。
「それだけの仕事があるのに計画年休を続けなくてはならないのか」という疑問は出てきてしまいますよね。
従来の雇調金制度には、「残業相殺」といって、残業させた分は支給金額から相殺するという決まりがありました。でも今は、コロナの特例措置ということで残業相殺もされていないんです。
書類に違和感があっても、申請はそのままするしかないんですか?
やはり立場上、お客さんからお預かりした書類や資料は、信用してそのまま申請することになります。私たちは手続きの代行はできますが、申請するのはあくまでお客さんですので。
ただ、それほど忙しいのなら、休みの日でも仕事をしたいという人が多いのでは?とも思ったりはします。労働局の担当者も同じように思うのではないでしょうか。
調査が入れば、何か発覚するかもしれない?
そうですね。調査では、事業主だけでなく従業員の方にヒアリングされることもあるんです。
私が立ち会ったケースでも、調査の際はすでに休業が明けていたので、急遽「今日は〇〇さんいますか」と。もともと予定はなかったのですが、従業員さんが直接質問されていました。
そこでもし「実はこういう作業をしていて…」と答えれば、休業していなかったということで不正受給になってしまいます。
従業員本人のコロナ感染に雇調金を申請?
ちなみに、「どうやったら助成金をもらえるか」みたいな相談もありますか?
悪意ではないのですが、従業員さんがコロナに感染したケースで、本人の休業を会社で補償したいというお話は何件かありました。
でも従業員本人の感染は、会社が雇用調整助成金を使う事由にはならないんですよね。実際の感染による休業は、会社の都合でなくあくまで個人の事情によるものです。健康保険の傷病手当金の対象にはなりますけれども、助成金の目的とは異なります。
ですので、そういったご相談は、しっかりとご説明した上でお断りしています。
助成金は正しい知識で有効活用
こうして聞いていると、制度内容を理解されてないケースも多いですね
助成金の申請には細かな要件がたくさんあるので、すべてを把握するのは難しいかもしれません。それでも、利用するならやはり、制度を正しく理解していただきたいと思います。わからなければ私たち専門家に聞いていただくとか。
コロナで本当に仕事がなければ休業指示を出されるのはもちろん仕方のないことですが、助成金を申請するなら、従業員さんたちの実態もよく確認していただきたいです。
たとえば、休業させるなら「会社として絶対に誰にも仕事はさせない」というくらいに徹底する必要があると思いますね。
雇用調整助成金は、申請件数が落ち着いたことで支給済みの案件に対する調査が増えているだけでなく、かなり細かいところまでチェックされているとのこと。
助成金の受給は要件を満たすことが大前提で、要件をしっかりと把握し、事実を正しく申請しなければ不正受給につながるおそれがあることもわかりました。
休業中の自主出勤や、退職日と退職届日の間違いなどは、どこの会社でも起こり得る気がします。不正受給には返還義務だけでなく大きなリスクが伴うので、慎重に進めたいところですね。