
ものづくり補助金は、令和7年2月14日に19次の公募が開始となりました。人気の補助金ですが、過去の採択率は30~40%程度。受給は簡単ではなく、計画的に進めていく必要があります。
また、毎回変更点もあるため、過去に交付を受けた場合でも最新の情報を確認しておかねばなりません。
この記事では、19次締切のものづくり補助金について、補助対象となる条件やスケジュール、注意点を解説します。
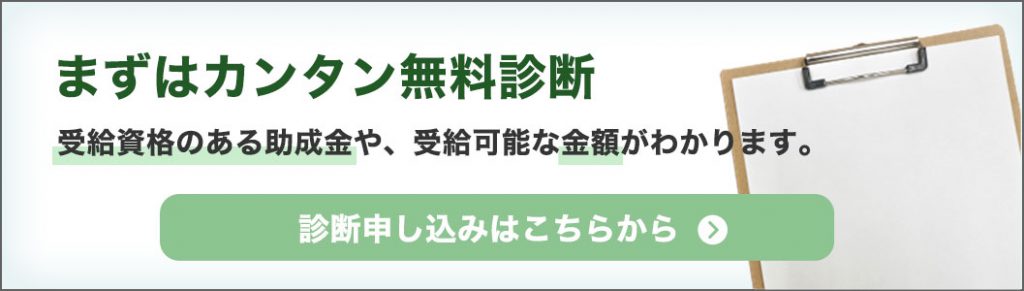
目次
ものづくり補助金の全体像を把握
まずは、ものづくり補助金の制度をおさらいしておきましょう。
ものづくり補助金とは

ものづくり補助金は、中小企業が設備投資を行った際、経費の一部を補助してもらえる制度です。
正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」であり、製造業でなくても申請できます。ただし、「生産性向上促進」とあるように、単に機械装置の購入などを行うだけでは補助されません。
生産性を向上させる新製品・新サービスの開発、生産プロセス改善など、指定の目的のために設備投資を行うことが必要です。
その上で賃金増加などの要件を満たし、目標を達成した場合に限り、補助の対象となります。
申請対象となる法人・個人

ものづくり補助金を申請できるのは、次のような中小企業や小規模事業者です。法人だけでなく、個人事業主も対象です。
- 中小企業等経営強化法にもとづく中小企業、または個人
(業種によって資本金や従業員数に条件あり。たとえば製造業では資本金3億円以下、従業員数300人以下、小売業では資本金5000万円以下、従業員50人以下)
- 小規模企業者・小規模事業者
(業種等により異なる。製造業の場合、従業員数が20人以下の会社または個人)
- 特定事業者(※)の一部 ※中小企業から中堅企業への成長途上の企業
(業種等により異なる。製造業の場合、従業員数500人以下、資本金10億円未満)
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
(従業員数300人以下、「経営力向上計画」の認定を受けているなどの要件あり)
- 社会福祉法人
(従業員数300人以下、法人税法にもとづく「収益事業」を行うなどの要件あり)
中小企業等経営強化法にもとづく中小企業や特定事業者の一部には、企業組合や協業組合なども含まれます。この法の定義に該当しない組合や連合会、財団法人や社団法人、医療法人などは対象外です。
ものづくり補助金を申請できないのは…
いわゆる「大企業」のほか、過去14カ月以内にものづくり補助金の交付候補者として採択された事業者、過去に交付決定を受けたのに状況報告書を提出していない事業者など。
過去3年間に交付決定を2回受けている事業者も対象外です。
2025年(19次)の主な変更点

ものづくり補助金は、2020年に始まり、通年で公募が行われています。ただし、要件などの制度内容は同じではないため注意が必要です。
19次は、前回の18次から次のような点が変更されています。
| 18次からの変更点 | 概要 |
|---|---|
| 申請枠が2つに統合 | 「製品・サービス高付加価値化枠」と「グローバル枠」 |
| 補助上限額の見直し | 最大4000万円 |
| 補助率の引き上げ | 最低賃金の引き上げで補助率最大3分の2 |
| 賃上げ要件の強化 | 給与総額成長率の増加、従業員21人以上の場合の一般事業主行動計画の公表必須 |
| 収益納付の廃止 | 補助金による利益を国に納付する義務なし |
次の章から、2つの申請枠の補助内容などを具体的に見ていきましょう。
製品・サービス高付加価値化枠の要件と補助内容

2つの申請枠の1つ、「製品・サービス高付加価値化枠」について見ていきましょう。
補助対象となる事業
この枠で補助対象となる事業とは、自社の技術力を生かし、設備投資などを行って、顧客に新たな価値を提供できる新たな製品やサービスを開発することです。
すでに普及している製品やサービスは対象となりません。新製品やサービスの開発を伴わない設備投資も対象外です。
たとえば、食品製造の会社が新たな冷凍方法による製品の試作を行うため、急速冷凍機など複数の機械設備を導入する、靴の製造会社が3D計測器などを導入し、短時間・遠隔でのオーダーメイド靴製造を可能にした、といったようなケースが該当します。
補助対象となる経費
新製品・サービスの開発に要した、次のような経費が補助の対象です。
| 補助対象経費 | 例 |
|---|---|
| 機械装置・システム構築費 | 機械装置や専用ソフトウェアの購入・レンタルなど (単価50万円以上) |
| 運搬費 | 運搬料、宅配・郵送料 |
| 技術導入費 | 知的財産権等の導入 |
| 知的財産権等関連経費 | 特許権取得にかかる弁理士費用など |
| 外注費 | 加工や設計などの一部を外注する費用 |
| 専門家経費 | 事業遂行のため依頼した専門家への報酬 |
| クラウドサービス利用費 | クラウドサービスの利用料 |
| 原材料費 | 試作品の開発に必要な原材料や副資材の購入 |
機械装置・システム構築費は、1つ以上、単価50万円(税抜)以上のものに限ります。それ以外の経費は、総額で500万円(税抜)が上限です。
また、それぞれの経費の上限額もあるため、経費の全額が補助されるわけではありません。
達成必須の基本要件
「製品・サービス高付加価値化枠」で申請するには、新製品・サービスの開発を行った上で、次の3つ(従業員21人以上の場合は4つ)の基本要件を満たすことが必要です。
| 1)付加価値額(※)の増加 | 付加価値額の年平均成長率を3%以上増加 ※付加価値額=「営業利益+人件費+減価償却費」 |
|---|---|
| 2)賃金の増加 | 給与支払総額の年平均成長率を2%以上増加 または 1人あたりの給与支給総額の年平均成長率を、都道府県の最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上増加 |
| 3)事業所内最低賃金水準のアップ | 事業所の最低賃金を、都道府県の最低賃金より30円以上アップ |
| 4)従業員の仕事・子育て両立支援 ★従業員21名以上 | 次世代育成支援対策推進法による「一般事業主行動計画」を策定、公表 |
「1」~「3」の基本要件については、自身で設定した目標値を達成する必要があります。
「2」と「3」の賃金アップを達成しなかった場合、交付された補助金を返還しなくてはなりません。
補助上限額と補助率
製品・サービス高付加価値枠の補助上限額と補助率は、前述のとおり経費によっても異なるほか、全体では従業員規模などによって次のように決められています。
| 従業員規模 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 5人以下 | 750万円 | 中小企業:2分の1 小規模企業・事業者、再生事業者:3分の2 |
| 6人~20人 | 1000万円 | |
| 21人~50人 | 1500万円 | |
| 51人以上 | 2500万円 |
このほか、経費ごとに決められた上限額もあります。
補助金額アップの特例要件
基本要件に加え、次の要件も満たした場合には、補助上限額の上乗せ・補助率の引き上げが受けられる特例措置があります。
| 特例要件 | 内容 | 措置 |
|---|---|---|
| 1)大幅な賃上げ | 給与支給総額の年平均成長率を6%以上増加 かつ 最低賃金を地域の最低賃金より50円以上アップ | 従業員規模により補助上限額を次のとおり上乗せ ・5人以下:最大100万円 ・6~20人:最大250万円 ・21人以上:最大1000万円 |
| 2)最低賃金の引き上げ | 2023年10月~2024年9月の間に3カ月以上、地域の最低賃金+50円以内の従業員が全従業員の30%いる | 補助率を3分の2に引き上げ |
特例用件2つの併用はできません。また、「1」では、自身で目標値を決め、従業員などに表明した上で達成する必要があります。
目標に達しなかった場合や表明をしていなかった場合、補助金の返還が必要です。
グローバル枠の要件と補助内容

もう1つの申請枠、「グローバル枠」についても見ていきましょう。
補助対象となる事業
この枠で補助対象となるのは、国内での生産性を高めるために、次のいずれかの事業によって海外での需要を開拓することです。
- 海外への直接投資に関する事業
- 海外市場開拓(輸出)に関する事業
- インバウンド対応に関する事業
- 海外企業と共同で行う事業
たとえば、海外市場開拓に関する事業には、「酒造会社が海外進出を図るため、海外基準量での瓶詰めも自動でできる最新型充てん機を導入して作業効率やスピードを高め、生産性を向上させた」というようなケースが該当します。
補助対象となる経費
国内での生産性向上と海外需要の開拓に要した、次のような経費が補助の対象です。
| 補助対象経費 | 例 |
|---|---|
| 機械装置・システム構築費 | 機械装置や専用ソフトウェアの購入・レンタル |
| 運搬費 | 運搬料、宅配・郵送料 |
| 技術導入費 | 知的財産権等の導入 |
| 知的財産権等関連経費 | 特許権取得にかかる弁理士費用 |
| 外注費 | 加工や設計などの一部を外注する費用 |
| 専門家経費 | 事業遂行のため依頼した専門家への報酬 |
| クラウドサービス利用費 | クラウドサービスの利用料 |
| 原材料費 | 試作品の開発に必要な原材料や副資材の購入 |
| 海外旅費(※) | 渡航や宿泊の費用 |
| 通訳・翻訳費(※) | 通訳・翻訳を依頼する場合の費用 |
| 広告宣伝・販促費(※) | 海外展開に必要なパンフレットや動画の作成、メディア掲載など、ブランディングやプロモーションにかかる経費 |
※印の経費は、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみが対象です。
機械装置・システム構築費は、1つ以上、単価50万円(税抜)以上のものに限ります。それ以外の経費は、総額で1000万円(税抜)が上限です。
また、それぞれの経費の上限額もあるため、経費の全額が補助されるわけではありません。
達成必須の基本要件

グローバル枠での申請には、「製品・サービス高付加価値化枠」と同じ基本要件のほか、グローバル枠のみ追加されている基本要件も満たす必要があります。
共通の基本要件
まずは、次の3つ(従業員21人以上の場合は4つ)の基本要件を満たすことが必要です。
| 1)付加価値額(※)の増加 | 付加価値額の年平均成長率を3%以上増加 ※付加価値額=「営業利益+人件費+減価償却費」 |
| 2)賃金の増加 | 給与支払総額の年平均成長率を2%以上増加 または 1人あたりの給与支給総額の年平均成長率を、都道府県の最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上増加 |
| 3)事業所内最低賃金水準のアップ | 事業所の最低賃金を、都道府県の最低賃金より30円以上アップ |
| 4)従業員の仕事・子育て両立支援 ★従業員21名以上 | 次世代育成支援対策推進法による「一般事業主行動計画」を策定、公表 |
「1」~「3」の基本要件については、自身で目標値を設定し、達成する必要があります。
「2」と「3」の賃金アップを達成しなかった場合は、交付された補助金を返還しなくてはなりません。
グローバル枠のみ追加の基本要件
グローバル枠には、上の3つもしくは4つの要件のほか、次の3つも基本要件とされています。
- 「グローバル要件①~④」のいずれかの事業で国内の生産性を高めること
- 海外事業に関する実現可能性調査を行うこと
- 社内に海外事業専門の人材を置くこと、または外部専門家と連携すること
「1」のグローバル要件①~④とは、冒頭の項で「補助対象となる事業」として紹介した、次のような事業です。
| グローバル要件 | 例 |
|---|---|
| 1)海外への直接投資に関する事業 | 国内・海外の事業をまとめて強化し、グローバルな製品・サービスを開発・提供する体制を作って国内の生産性を高める |
| 2)海外市場開拓(輸出)に関する事業 | 海外への展開を目的に製品やサービスを開発・改良、ブランディングや販路開拓に取り組む |
| 3)インバウンド対応に関する事業 | 製品やサービスの開発、提供体制を構築してインバウンド需要を獲得する |
| 4)海外企業と共同で行う事業 | 外国法人との共同研究、共同開発によって新たな成果物を生み出す |
「2」の実現可能性調査とは、市場調査や現地の規制や法令の調査、取引先の信用調査など、海外での事業の実現可能性を判断するための調査を指します。
補助上限額と補助率
グローバル枠では、従業員規模による補助上限の違いはありません。
| 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|
| 3000万円 | 中小企業:2分の1 小規模企業・事業者:3分の2 |
従業員が21人以上の場合、次に紹介する特例要件も満たせば、最大4000万円の補助金が受け取れることになります。
補助金額アップの特例要件
グローバル枠にも、「製品・サービス高付加価値化枠」と同じ特例措置が適用されます。
| 特例要件 | 内容 | 措置 |
|---|---|---|
| 1)大幅な賃上げ | 給与支給総額の年平均成長率を6%以上増加 かつ 最低賃金を地域の最低賃金より50円以上アップ | 従業員規模により補助上限額を次のとおり上乗せ ・5人以下:最大100万円 ・6~20人:最大250万円 ・21人以上:最大1000万円 |
| 2)最低賃金の引上げ | 2023年10月~2024年9月の間に3カ月以上、地域の最低賃金+50円以内の従業員が全従業員の30%いる | 補助率を3分の2に引き上げ |
2つの特例要件は併用できません。また、「1」では、自身で目標値を決め、表明する必要があります。
目標に達しなかった場合や表明していなかった場合、補助金の返還が必要です。
19次のスケジュールと申請の流れ
補助金は、数々の要件を満たすほか、期日も守らなければ受けられません。申請のスケジュールや流れも把握しておきましょう。
ものづくり補助金19次公募のスケジュール

公募開始はすでに始まっています。採択候補者の決定までは次のようなスケジュールとなっています。
| 公募開始 | 2025年2月14日(金) |
|---|---|
| 電子申請受付 | 2025年4月11日(金)17:00~ |
| 申請締切 | 2025年4月25日17:00 ※厳守 |
| 採択候補者の公表 | 2025年7月下旬ごろ予定 |
電子申請のみでの受付となり、あらかじめ準備すべきこともあるため、早めの着手が必要です。
ものづくり補助金の申請の流れ

ものづくり補助金を申請する際の具体的な流れは、次のとおりです。
- 電子申請に必要な「GビスIDプライム」のアカウント取得
- 事業計画書の作成や必要書類の準備
- 電子申請
- 審査~補助金交付候補者の採択
- 交付申請→交付決定
- 補助対象となる事業の実施
- 実績の報告→確定検査
- 補助金額の確定
- 補助金の請求→支払い
- 事業化状況報告
まずは電子申請のためのアカウントを取得し、事業計画書の作成や必要書類の準備を始めます。申請後、提出した書類などにより審査され、交付候補者としての採択が行われます。
採択されたら交付申請をし、補助対象経費が適切かどうかなどの審査を経て交付決定を受けます。ただし、ここで減額や全額対象外となる可能性もあります。
交付決定を受け補助対象事業者となった場合、対象事業を行って目標を達成することのほか、補助事業の終了後6年間にわたって事業化状況などを報告しなくてはなりません。
ものづくり補助金(19次)申請のポイント

19次公募のものづくり補助金を申請するなら、押さえておくべきポイントがあります。順に見ていきましょう。
- 採択イコール交付決定ではない
- 会社全体の事業計画との連動が必須
- 基本要件3つは目標値の表明と達成が必須
- 不適切なコンサル業者に注意
- 補助金に精通した専門家のサポートが必要
それぞれ解説します。
採択イコール交付決定ではない
ものづくり補助金は、採択されなければ交付されません。ただし、採択されたからと言って補助が受けられるとは限らないので注意が必要です。
補助金制度の場合、採択はあくまで「交付候補者」となったにすぎず、その後の審査などによって採択取消となる場合もあります。
また、補助には上限額があり、経費のすべてがまかなえるわけではないことも理解しておきましょう。
補助金獲得のための事業計画はNG
補助金の申請には事業計画の策定が必須です。しかしこの事業計画は、あくまで会社全体の事業計画でなくてはならず、補助金のための事業計画ではないことに注意が必要です。
会社全体の事業計画に沿って補助対象となる事業を行うこと、事業計画期間内に付加価値の向上や賃金アップを達成することが補助の条件です。
基本要件3つは目標値の表明と達成が必須

ものづくり補助金の基本要件(2つの枠に共通する基本要件)のうち、付加価値額の増加と賃金の増加、最低賃金のアップの3つについては、事業計画の時点で設定した目標値を達成する必要があります。
賃金についての要件は、達成しなければ補助金返還の義務が発生します。
また、設定した目標値は交付申請までに全従業員(または従業員代表者)と役員に表明しておかねばなりません。表明されていなかった場合、交付決定は取消され、補助金の返還が求められます。
不適切なコンサル業者に注意

補助金の申請をすすめる業者の中には、必要な説明をしないまま勝手に申請をすすめたり、不正受給を手引きした上、法外な成功報酬を要求したりする業者もいるので注意が必要です。
不正受給が発覚すれば、交付決定の取消はもちろんのこと、受け取った補助金に加算金を加えて返還するなどのほか、不正内容を公表されることになります。
場合によっては、5年以下の懲役や100万円以下の罰金が科され、社会的信用も失いかねません。
「確実に受給できる」「すべてこっちでやるから何もしなくていい」などと言う業者には警戒してください。
補助金に精通した専門家のサポートが必要

補助金の申請には注意すべきポイントや採択のコツがあるため、受給には専門家のサポートが欠かせません。
とはいえ、不適切なコンサル業者や補助金申請の実績が少ない専門家に頼むのは失敗のもと。単なる専門家ではなく、補助金に精通した専門家にサポートを依頼することがポイントです。
補助金には、審査に加点される条件なども存在します。そういった知識のある、実績豊富な中小企業診断士や税理士などのサポートを受けることをおすすめします。
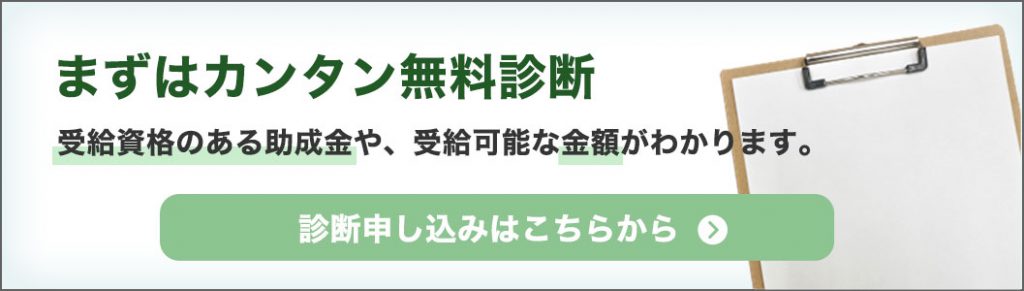
ものづくり補助金の申請もBricks&UKにおまかせ

ものづくり補助金は、製造業やサービス業などさまざまな業種で活用されている人気の補助金です。しかし、採択率は18次で36%ほどと決して高くありません。採択をされても受給できないケースと言うのも存在します。
当社「社会保険労務士事務所Bricks&UK」は、グループ会社である「税理士法人Bricks&UK」と提携し、ものづくり補助金の申請サポートも承っています。
ものづくり補助金の申請をお考えなら、中小企業の経営コンサルを得意とし、補助金申請の実績も豊富なBricks&UKに、ぜひ一度ご相談ください。












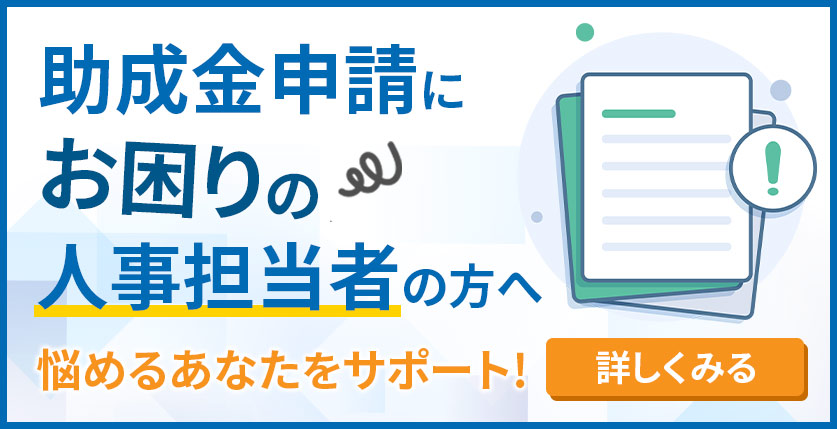
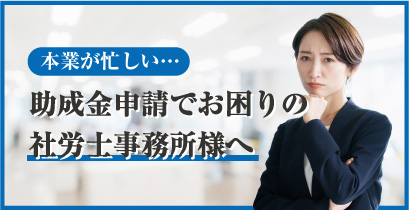
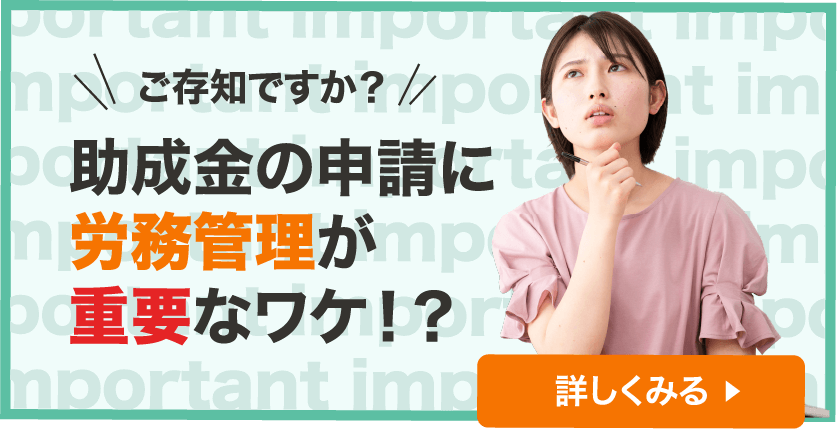
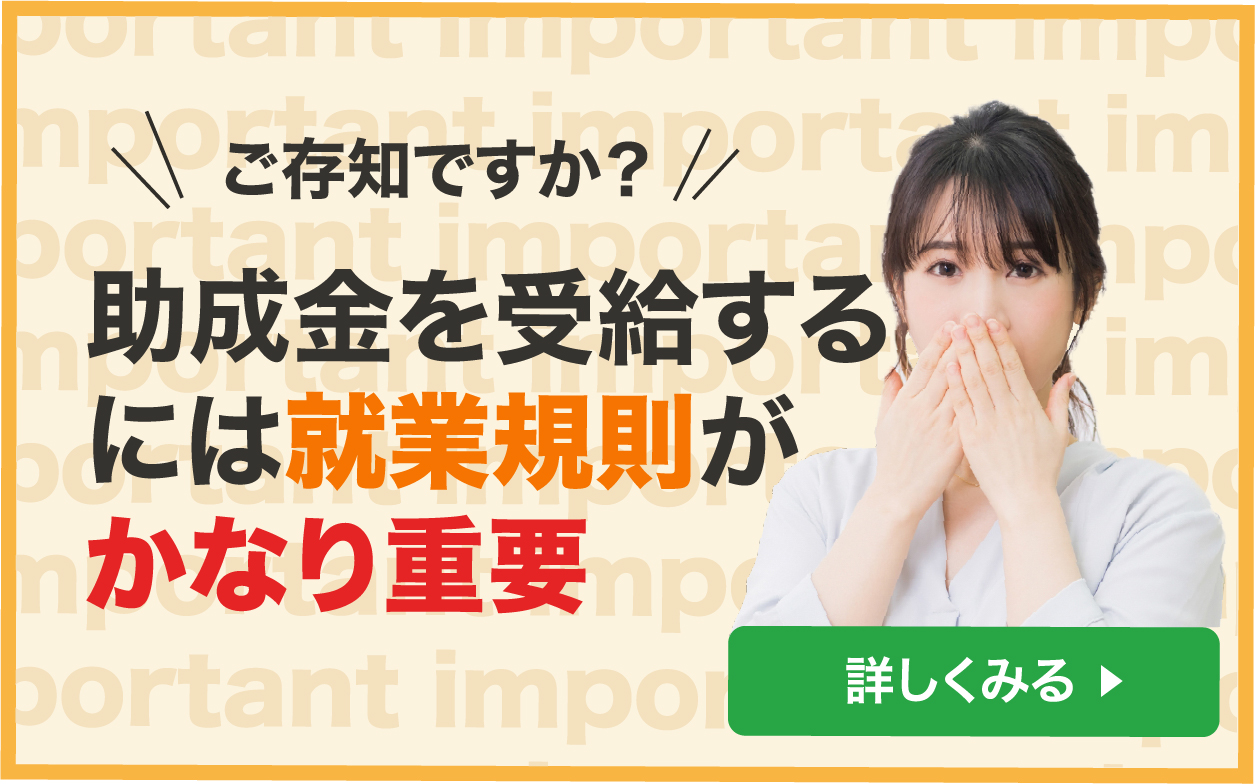

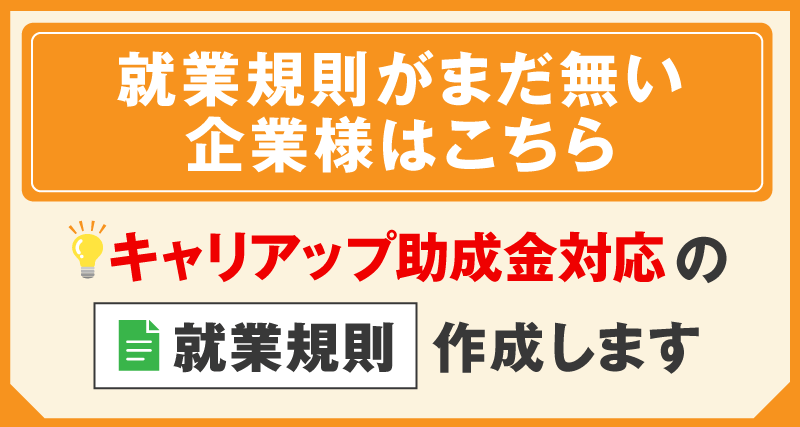
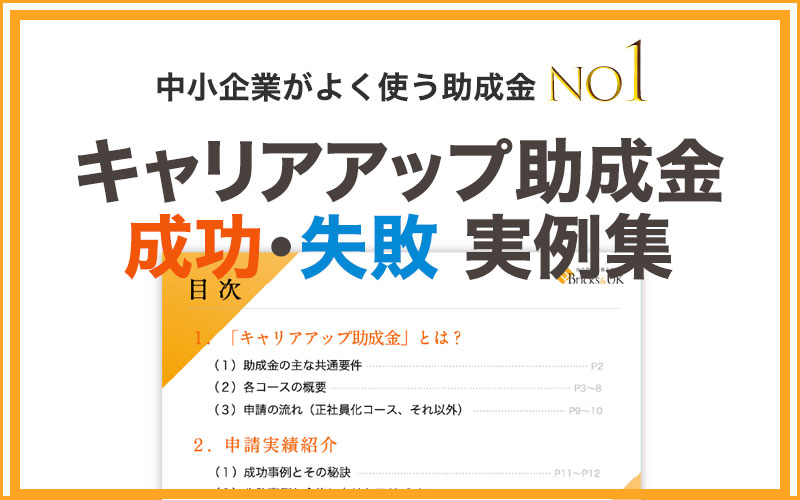


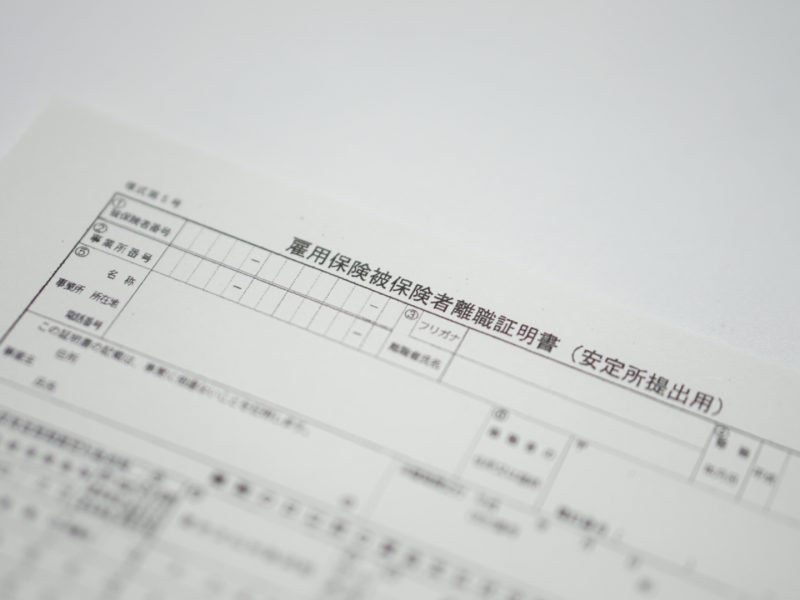

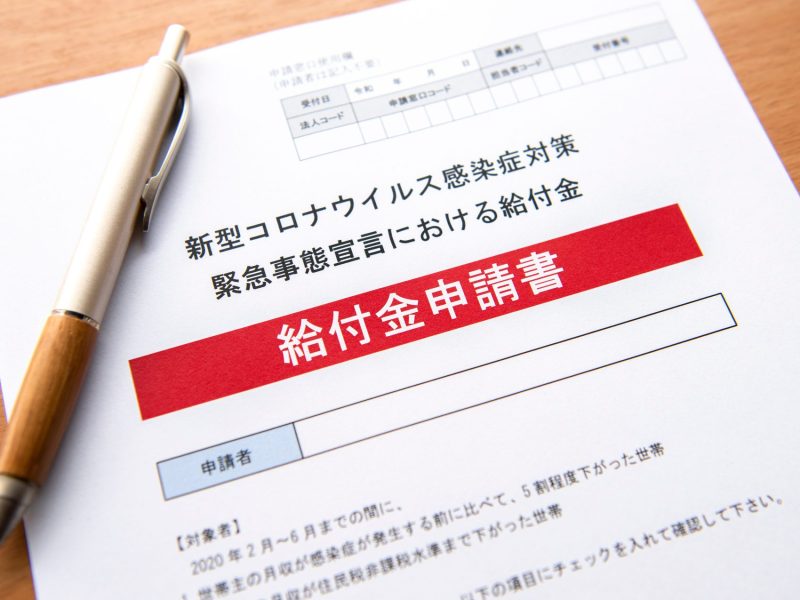
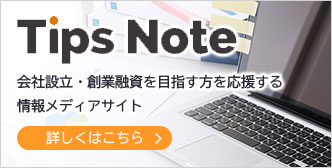


監修者からのコメント ものづくり補助金は補助金額が大きいため、申請を検討される企業が多いです。
しかし、その分審査も厳しいので、事業計画書の作成には注意が必要です。
「生産性向上」をどのように示すかがポイントになりますので、
申請をお考えの方はぜひお気軽にご相談ください。