
企業が従業員の職業能力開発のため教育訓練を行った場合に、その経費や賃金の一部が支給される「人材開発支援助成金」という助成金制度があります。
人材開発支援助成金には6つのコースがあり、それぞれの対象となる内容や助成額、申請方法などが異なります。
この記事では人材開発支援助成金について詳しく解説します。
目次
人材開発支援助成金とは

人材開発支援助成金の対象となるのは、従業員に教育・訓練を行って職場定着率の向上や生産性向上を促し、人材不足の解消につなげた事業主です。
訓練の種類などにより6つの種類があり、訓練にかかった経費や、訓練期間中の賃金の一部などが助成されます。
1)人材育成支援コース
職務に関連した知識や技能を習得させるOFF-JTや、OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせて訓練を行った場合に支給されるコースです。
2)人への投資促進コース
高度デジタル人材育成のための訓練や、IT分野未経験者の即戦力化のための訓練、サブスクリプション型の研修サービスによる訓練など、5つの助成メニューがあります。
3)事業展開等リスキリング支援コース
新規事業展開に伴い、新たな分野で必要な知識や技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合に対象となるコースです。
4)教育訓練休暇等付与コース
有給の教育訓練休暇制度を導入し、従業員がこの休暇制度を利用して社外の教育訓練や各種検定などを受けた際に助成されます。
5)建設労働者認定訓練コース
従業員の技能向上のため、認定訓練を実施した中小の建設事業主に助成金が支払われます。
6)建設労働者技能実習コース
建設業の事業主が、雇用している建設労働者に有給で技能実習を受講させた場合に助成されます。
(障害者職業能力開発コース)
このコースは、令和5年度をもって廃止となりました。
令和6年4月からは、 障害者雇用納付金制度による「障害者能力開発助成金」に移行されています。助成対象や助成額・助成率は原則、従前の「人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)」と同じです。
人材開発支援助成金の各コースの詳細

人材開発支援助成金の6つのコースについて、具体的な内容と助成額や助成率について見ていきましょう。
助成の内容はコースにより異なりますが、主に従業員に支払った賃金に対する賃金助成と、必要とした経費に対する経費助成、OJTを実施したことへの助成の3種類があります。
また、訓練終了日翌日から1年以内に基本給(毎月決まって支払われる賃金)を5%以上増加させたり、資格等に対する手当を就業規則等に規定して支払い、基本給を3%上昇させたりした場合には、「資格等手当要件」の加算が受けられる訓練もあります。
人材育成支援コース

人材育成支援コースでは、次の3種類の訓練が対象です。
- 職務に関連した知識や技能を習得させるための10時間以上の訓練が対象となる「人材育成訓練」
- 厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練である「認定実習併用職業訓練」
- 有期契約労働者等に対し、正規雇用等に転換するための訓練である「有期実習型訓練」
助成の対象となる経費は、事業主がOFF-JT訓練を実施した際の、部外の講師への謝金・手当・旅費、会場使用料、教科書などの購入・作成費などです。
また賃金助成の対象の従業員は、事前に提出が必要な訓練実施計画の「訓練別の対象者一覧」に記載された雇用保険の被保険者であること、訓練を受講した時間数が訓練時間数の8割以上であることが条件です。
訓練ごとの助成額と助成率は、次の表の通りです。( )内は中小企業以外の助成額・助成率です。
人材育成訓練(OFF-JT)
人材育成訓練の経費助成率は、訓練対象となった従業員の雇用形態により異なります。
| 助成種別 | 助成額(1人あたり) ・助成率 | 賃金要件等を 満たした場合 |
|---|---|---|
| 賃金助成額 | 760円(380円)/時 | 960円(480円)/時 |
| 経費助成率 | 正規雇用者:45%(30%) 非正規雇用者:60% 非正規→正社員:70% | 正規:60%(45%) 非正規:75% 正社員化:100% |
認定実習併用職業訓練(OFF-JT+OJT)
「認定実習併用職業訓練」とは、ジョブカードを活用し、教育訓練機関での講座受講など(OFF-JT)と、社内での実習(OJT)を組み合わせた実践的な訓練です。
| 助成額(1人あたり) ・助成率 | 賃金要件等を 満たした場合 | |
|---|---|---|
| 賃金助成額 | 760円/時 (380円) | 960円/時 (480円) |
| 経費助成率 | 45%(30%) | 60%(45%) |
| OJT実施助成額 | 20万円(11万円) | 25万円(14万円) |
賃金助成と経費助成は、OFF-JTが対象です。
有期実用型訓練(OFF-JT+OJT)
「有期実用型訓練」は、パートやアルバイトなど有期契約の従業員あるいは新入社員に対し、正社員化に必要な能力の習得・見極めを目的に実施する訓練です。
| 助成額(1人あたり) ・助成率 | 賃金要件等を 満たした場合 | |
|---|---|---|
| 賃金助成額 | 760円/時(380円) | 960円(480円)/時 |
| 経費助成率 | 非正規雇用者:60% 正社員化:70% | 非正規:75% 正社員化:100% |
| OJT実施助成額 | 10万円(9万円) | 13万円(12万円) |
賃金助成と経費助成は、OFF-JTが対象です。
人への投資促進コース

人への投資促進コースは、人材育成支援コースに比べて助成率が高いのが特徴です。訓練の種類によって、次の5つに分けられています。
- 高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
- 情報技術分野認定実習併用職業訓練
- 定額制訓練
- 自発的職業能力開発訓練
- 長期教育訓練休暇等制度
それぞれの概要と、助成額・助成率を見ていきましょう。
高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
「高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練」は、DX推進や成長分野における高度人材を育成するための訓練や、大学院での訓練を対象としています。
| 高度デジタル人材訓練 | 助成率・ 助成額(1人あたり) |
|---|---|
| 経費助成率 | 75%(60%) |
| 賃金助成額 | 960円/時(480円) |
| 成長分野等人材訓練 | 助成率・ 助成額(1人あたり) |
|---|---|
| 経費助成率 | 75% |
| 賃金助成額 | 960円 (国内大学院のみ) |
情報技術分野認定実習併用職業訓練
「情報技術分野認定実習併用職業訓練」では、IT分野が未経験の人材に対して訓練を実施した場合に助成されます。
| 助成額(1人あたり) ・助成率 | 賃金要件等を 満たした場合 | |
|---|---|---|
| 賃金助成額 | 760円/時(380円) | 960円/時(480円) |
| 経費助成率 | 60%(45%) | 75%(60%) |
| OJT実施助成額 | 20万円(11万円) | 25万円(14万円) |
賃金助成と経費助成は、OFF-JTが対象です。
定額制訓練
サブスクリプション型の教育訓練を受講する際に対象となるのが「定額制訓練」です。
| 助成率 | 賃金要件等を 満たした場合 | |
|---|---|---|
| 経費助成率 | 60%(45%) | 75%(60%) |
定額制訓練には、賃金助成はありません。
自発的職業能力開発訓練
「自発的職業能力開発訓練」は、従業員が自発的に教育訓練を受講した場合に活用できます。
| 助成率 | 賃金要件等を 満たした場合 | |
|---|---|---|
| 経費助成率 | 45% | 60% |
自発的職業能力開発訓練も経費助成のみです。
長期教育訓練休暇等制度
「長期教育訓練休暇等制度」は、働きながら教育訓練を受講できるようにするための休暇制度や、訓練を受けるための短時間勤務制度を導入した場合に、助成が受けられます。
| 長期教育訓練休暇制度 | 助成額 (1人あたり) | 賃金要件等を 満たした場合 |
|---|---|---|
| 賃金助成額 | 960円/時 (760円) | -(960円)/時 |
| 制度導入助成 | 20万円 | 24万円 |
賃金助成は、制度で対象とする休暇を有給休暇とした場合のみが対象です。また、賃金助成の加算は、元が高く設定されていることから、中小企業は対象外です。
長期教育訓練休暇制度は、最低でも合計30日以上の休暇を付与する制度でなくてはなりません。
| 教育訓練短時間勤務等制度 | 助成額 | 賃金要件等を 満たした場合 |
|---|---|---|
| 制度導入助成 | 20万円 | 24万円 |
教育訓練短時間勤務等制度は、30回以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除のいずれも利用できる制度である必要があります。
事業展開等リスキリング支援コース

事業展開等リスキリング支援コースは、次のような場面で雇用する労働者に対し、計画に沿った訓練を実施した場合に活用できます。
- 新たな製品の製造もしくは商品やサービスを提供することにより、新たな事業を展開する
- DX推進により業務の効率化を図る
- 徹底した省エネや再生可能エネルギーの活用等により、CO2等の温室効果ガスの排出を全体として ゼロにする
助成額は次の表の通りです。
| 助成率・ 助成額(1人あたり) | |
|---|---|
| 経費助成率 | 75%(60%) |
| 賃金助成額 | 960円/時(480円) |
教育訓練休暇付与コース

教育訓練休暇制度を導入して、労働者が実際に教育訓練休暇を取得した場合に、導入に関わる経費と教育訓練休暇中の賃金の一部が助成されます。
教育訓練休暇の期間によって「教育訓練休暇制度」「長期教育訓練休暇制度」「教育訓練短時間勤務等制度」に分かれています。
このうち、「長期教育訓練休暇制度」「教育訓練短時間勤務等制度」は前述の「人への投資促進コース」として助成され、令和8年度までの措置となります。
教育訓練休暇制度は、3年間に5日以上の教育訓練休暇制度を導入する場合に活用でき、有給の教育訓練休暇を付与する制度であることが必要です。
助成額は次の表の通りです。
| 教育訓練休暇制度 | 助成額 | 賃金要件等を 満たした場合 |
|---|---|---|
| 制度導入・実施助成 | 1事業主あたり 30万円 | 36万円 |
この助成は、1事業主につき1回のみの支給です。
建設労働者認定訓練コース

「建設労働者認定訓練コース」には、経費助成と賃金助成があります。
経費助成の対象は、訓練費用について都道府県より広域団体認定訓練助成金または認定訓練助成事業費補助金の交付を受けている中小建設事業主です。
賃金助成の対象は、前述の人材開発助成金「人材育成支援コース」の支給決定を受けた中小建設事業主です。
助成額と助成率は次の表の通りです。
| 助成の種類 | 助成額(1人あたり)・助成率 |
|---|---|
| 経費助成 | 広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金における補助対象経費の1/6 |
| 賃金助成 | 3,800円/日 |
| 賃金要件等を満たした場合 | +1,000円/日 |
建設労働者技能実習コース

建設労働者技能実習コースも、中小企業事業主の建設労働者を対象とするコースです。従業員に有給で技能実習を受けさせた場合に助成を受けられます。
助成内容は、従業員(雇用保険被保険者)の数などにより異なります。
中小建設事業主(20人以下)の場合
| 助成額(1人あたり) ・助成率 | 賃金要件等を 満たした場合の加算 | |
|---|---|---|
| 賃金助成額 | 8,550円(9,405円)/日 | +2000円/日 |
| 経費助成率 | 4分の3 | 20分の3 |
中小建設事業主(21人以上)の場合
| 助成額(1人あたり) ・助成率 | 賃金要件等を 満たした場合の加算 | |
|---|---|---|
| 賃金助成額 | 7,600円(8,360円)/日 | +1750円/日 |
| 経費助成率 | ・35歳未満:10分の7 ・35歳以上:20分の9 | 20分の3 |
中小建設事業主以外の建設事業主
中小規模に該当しない建設事業主の場合、建設労働者である女性従業員への技能実習に対してのみ助成が受けられます。
| 助成率 | 賃金要件等を 満たした場合の加算 | |
|---|---|---|
| 経費助成率 | 5分の3 | 20分の3 |
中小建設事業主以外の場合、賃金助成はありません。
建設事業主のみを対象としたコースは特に、要件や対象訓練が細かく指定されているため、申請前に支給要綱を十分に確認しておく必要があります。社会保険労務士などに相談することをおすすめします。
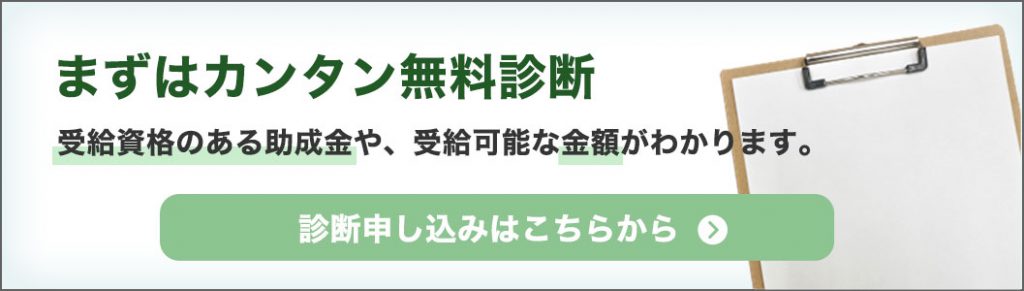
人材開発支援助成金におけるこれまでの改正点

人材開発支援助成金制度は、制度やコースの整理統合・廃止が毎年実施されているので、申請の際には変更点を把握して、最新の要件を確認する必要があります。令和5年4月以降の改正内容については次の通りです。
令和5年4月1日からの主な改正内容
生産性要件が廃止され、代わりに「賃金要件」と「資格等手当要件」が創設されました。
助成金を活用しやすくするため、特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コースを統合し、人材育成支援コースに一本化されました。また、OFF-JTの最低訓練時間は10時間以上に統一されました。
そのほか、人への投資促進コースの対象者と対象訓練の拡充、計画届の提出方法の変更が実施されました。
令和6年4月1日からの主な改正内容
長期教育訓練休暇制度・自発的職業能力開発訓練・高度デジタル人材訓練の対象訓練について拡充が行われました。
また人材育成支援コースにおける申請書類の簡素化など、コース共通での添付書類の簡素化も実施されました。
このような改正が今後も行われるため、申請前には必ず最新情報を確認する必要があります。
人材開発支援助成金を活用するメリット・デメリット

人材開発支援助成金の活用には、メリットとデメリットの両面があります。メリットだけでなくデメリットも知っておきましょう。
人材開発助成金のメリット
人材開発支援助成金の最大のメリットは、国から助成金を受給することで、経費や賃金の負担を軽減させつつ人材育成ができることです。
また、助成の上限額が高いこともポイントです。コースにより異なりますが、1年度あたり最大2500万円と、高い限度額が設定されています。
従業員1人あたりの研修費用の平均は、32,412円(2023年度の実績額/産労総合研究所「2023年度 教育研修費用の実態調査」より) です。従業員数の少ない中小企業にとって、大きな助けとなるでしょう。
さらに、助成対象となる教育・訓練等が多種にわたることもメリットと言えます。助成対象となる教育訓練の中から、自社の課題解決や事業計画の推進に役立つものを選んで活用できます。
人材開発支援助成金のデメリット
デメリットは、受給への準備・申請手続きが複雑で難しいことです。
各コースの資料はなかなか複雑で、コースによっては難なく申請できるものではないこともあります。わかりにくいというだけではなく申請自体も煩雑で、かなりの手間がかかります。
人材開発支援助成金は、教育訓練が終了した後に支給申請を行い、審査を受け、問題がなければ支給されます。
そのため、申請するなら、受給が訓練実施後になることを織り込んだ上で資金繰りを含めた計画をする必要があります。不備などにより助成金が受給できないとなれば、教育はできても財政面で大きな痛手となってしまいます。
人材開発支援助成金を受給するまでの流れと注意事項

最後に、人材開発支援助成金の受給の流れと、特に注意すべきことについて解説します。
人材開発支援助成金受給の流れ
人材開発支援助成金は、コースによって手続きや必要となる書類が異なります。この記事では、人材育成支援コースを例に紹介します。
1.計画届の提出
訓練を開始する1カ月前までに、「訓練実施計画届」「年間職業能力開発計画」「訓練別の対象者一覧」などに、必要書類を添えての管轄の労働局かハローワークに提出します。
なお、OFF-JTとOJTを組み合わせた実習併用職業訓練を対象として、人材開発支援助成金を申請する場合は、訓練実施日の2カ月前までに厚生労働大臣の認定の申請をする必要があります。
2.計画変更
計画を変更する時には、変更前に計画していた訓練実施予定日または変更後の訓練実施日のどちらか早い方の日の前日までに、「計画変更届」の提出が必要となります。
3.支給申請
訓練が終了日の翌日から起算して2カ月以内に、「支給申請書」に必要書類を添えて管轄の労働局に提出します。
4.「賃金要件」「資格等手当要件」を満たし申請
すべての対象労働者に対し、要件を満たす賃金または資格等手当を3カ月間継続して支払い、「支給申請書」に必要な書類を添えて管轄の都道府県労働局に提出します。
申請は、賃金または手当を支払った日の翌日から起算して5カ月以内にしなくてはなりません。
人材開発支援助成金申請時の注意事項

助成金は、基本的には要件を満たせば支給されるものです。しかし、不支給や対象外となってしまうケースもあります。特に次の点に注意してください。
申請期限の遵守は必須
必要書類を揃え、正しい手順で申請しても、期限を1日でも過ぎれば受給できません。
期限には、申請の期限だけでなく計画書の届出期限もあります。例外は認められないため、スケジュールを組んで確実に進めていくことが重要です。
計画に沿った訓練実施も必須
訓練実施計画を提出した後、変更になった場合には「計画変更届」の提出が必要です。
提出なく計画とは違う日時・場所、カリキュラムなどで実施した場合、その部分は助成の対象外になります。
併給できない助成金がある
助成金は原則として、支給対象が同じ助成金を重複して受給することはできません。これを併給調整といいます。
併給不可の複数の助成金で対象となりそうな場合、どちらの助成金を活用するかで受給できる金額も変わるため、判断が難しいところです。
また、助成金の組み合わせによっては、支給対象が同じでも併給が可能なケースがあります。詳しくは、助成金の専門家である社会保険労務士や、労働局・ハローワークにて確認してください。
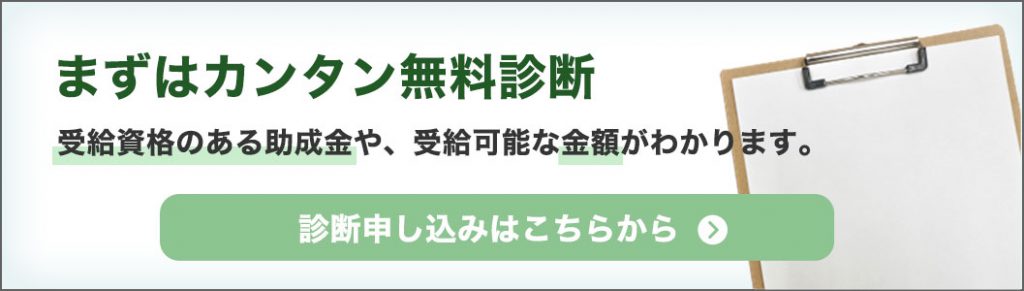
人材開発支援助成金の申請ならBricks&UKにおまかせ

人材不足の深刻化が問題となる中、企業には新規雇用だけではなく、人材育成による労働力の維持・確保も重要な課題です。
そこで活用したいのが、教育訓練のコスト負担が軽減できる人材開発支援助成金です。
しかし、制度内容は非常に細かく、専門知識がなければスムーズな申請は困難を極めます。そのため、助成金の申請には、専門家である社会保険労務士に依頼するのがおすすめです。
Bricks&UKでは、社会保険労務士が助成金の申請を代行するだけでなく、就業規則の整備や活用可能な助成金の提案など、さまざまなサポートを行っています。ご検討の際はぜひ、お気軽にご相談ください。
貴社で活用できる助成金をカンタン診断しませんか?
助成金をもらえる資格があるのに活用していないのはもったいない!
返済不要で、しかも使い道は自由!種類によっては数百万単位の助成金もあります。
ぜひ一度、どんな助成金がいくらくらい受給可能かどうか、診断してみませんか?
過去の申請実績も参考になさってください。
















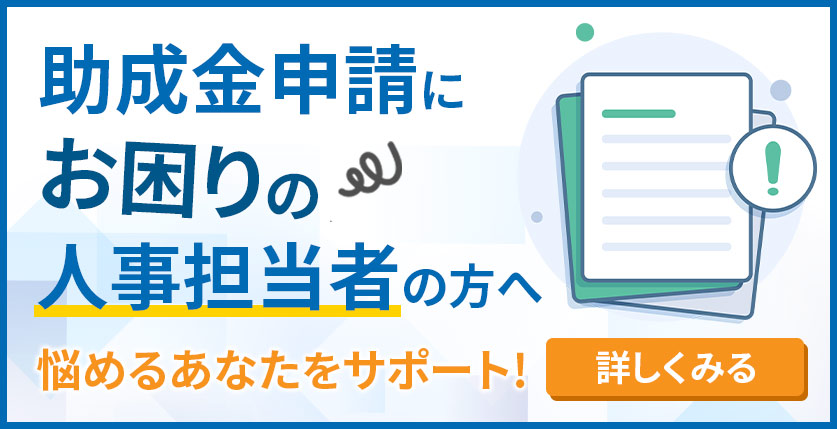
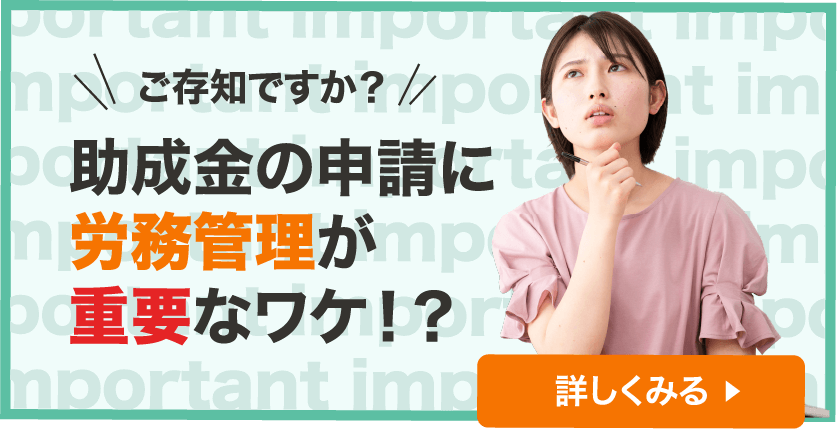
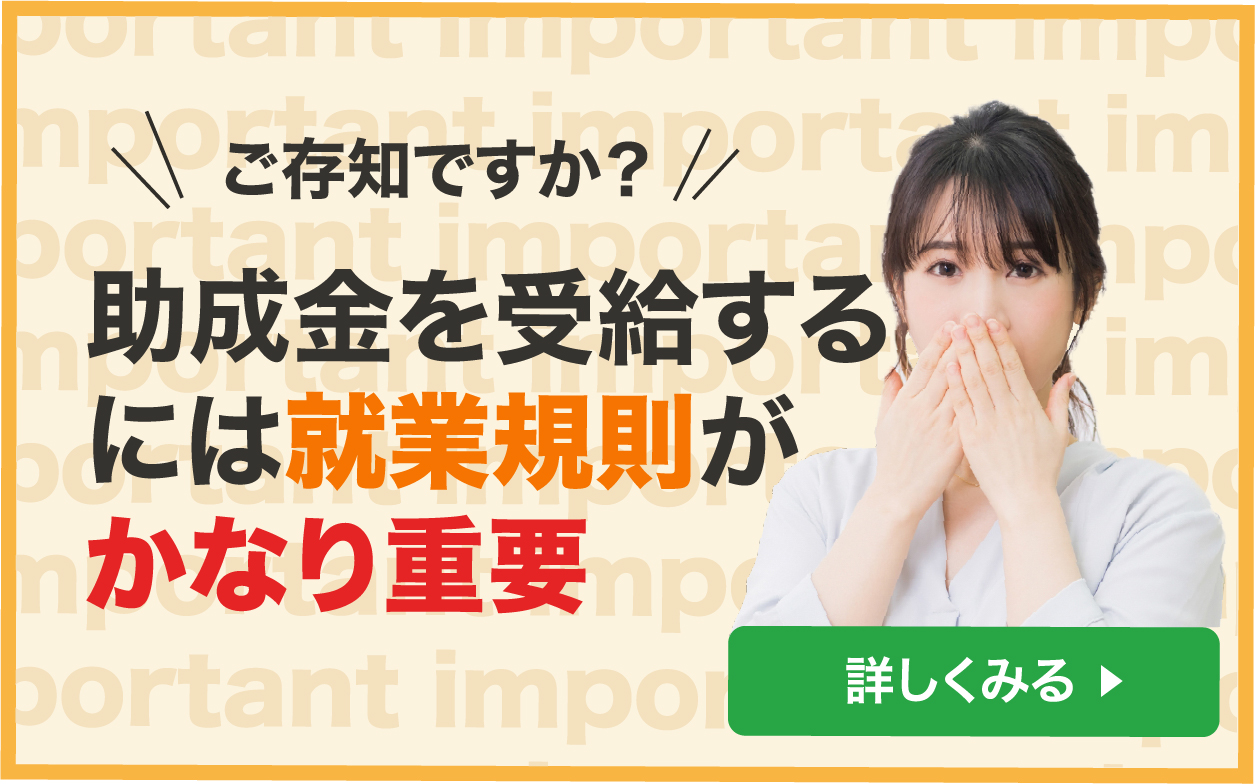

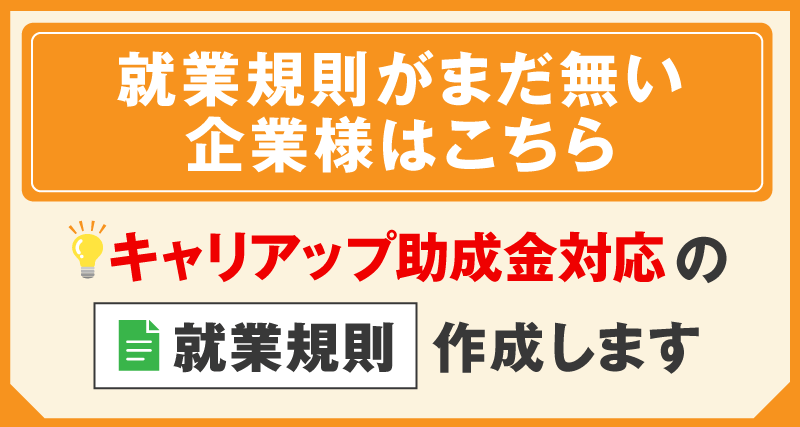
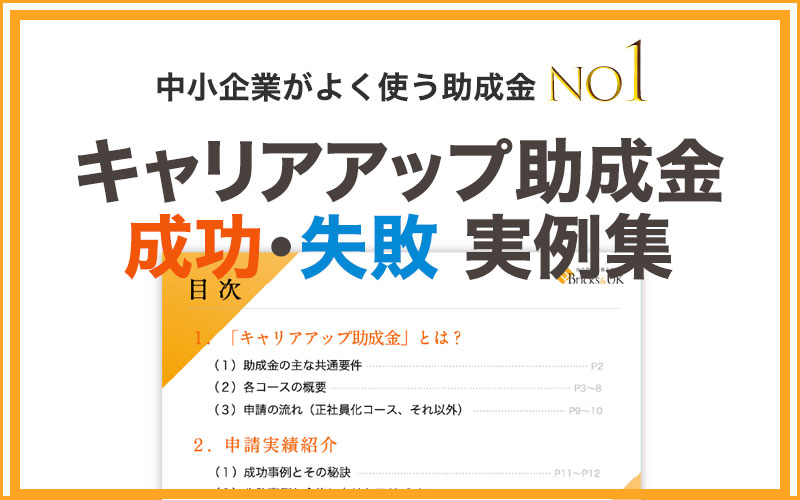


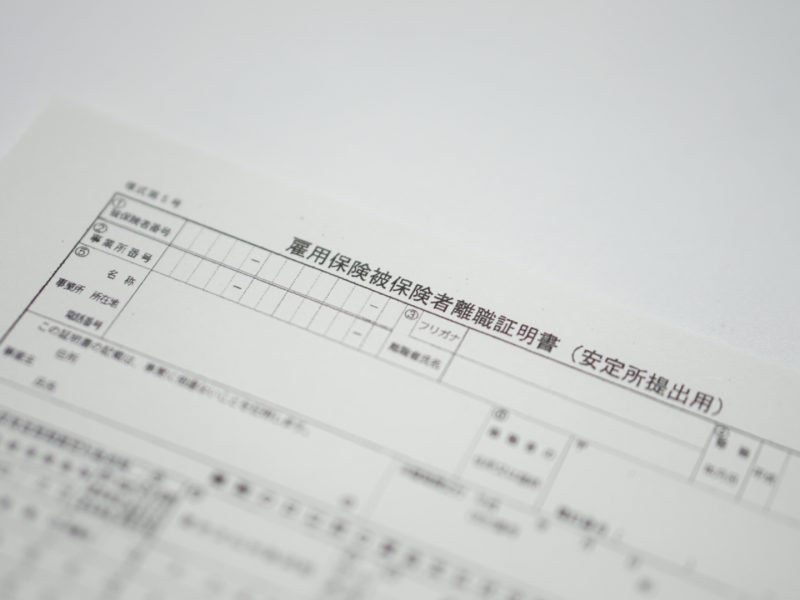

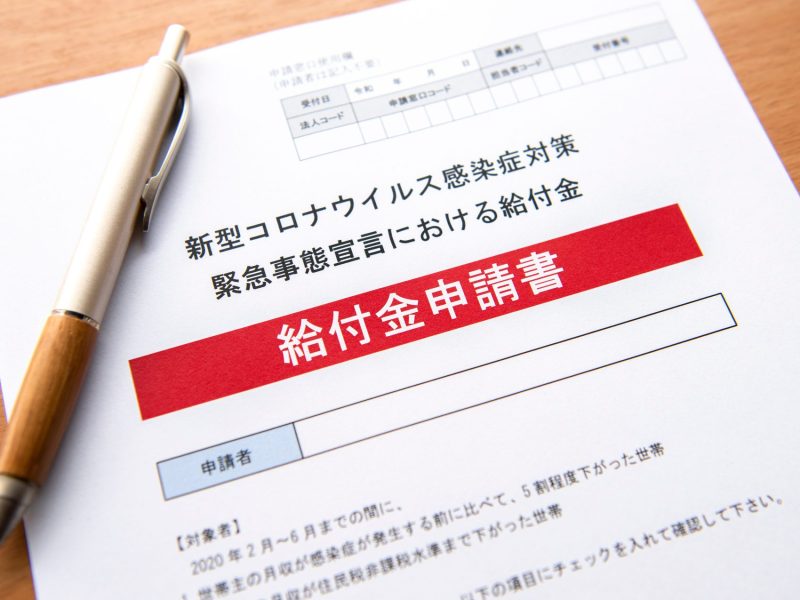
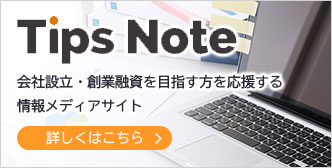


監修者からのコメント この助成金は事前に訓練計画を策定するところがポイントとなります。 どのように計画を立てれば良いのか、対象となる訓練がどのようなものかなど、初めて取り組まれる事業主様では判断に迷うケースもあるかと思います。 Bricks&UKでは、訓練計画の策定からサポートいたします。 ぜひお気軽にお問い合わせください。